現在、カスピ海周辺から中東・北アフリカ一帯にかけて戦火が絶えませんが、それらの本質を理解するためには、少なくとも三つの要因を分析する必要があります。
第一に、宗教の対立です。と言っても、今現在ではキリスト教とイスラム教よりも、むしろサウジアラビアを盟主とするスンニ派と、イランを盟主とするシーア派の対立が先鋭化しています。シリアがその宗派紛争の舞台になっているんですね。
第二に、大イスラエル構想です。ユダヤ人たちはアラブ人の土地に新国家を創ることに成功しました。それが「表の政治活動」だけの成果に拠ると信じ、陰謀の存在を否定する人は、当の陰謀者たちが作った価値観の犠牲者です。彼らが内心で何を企み、どう動こうとしているのかを読まずして、中東の今後を占うことは不可能だと思います。
以上については、前二回の記事で、かなり説明しました。ま、説明というより、ほとんど私の考えというか、推理の類いですが(笑)。で、今回追及するのが以下。
第三の、石油(又天然ガスも含む広義の地下資源)です。今回はもっぱらこれについて述べます。しかも、もったいぶらず、最初に結論から言ってしまいます。
私は長い間、欧米支配層が帝国主義的な野心から、カスピ海から中東・北アフリカ一帯にかけての地下資源を強奪しようとしているのだと、単純に信じてきました。
これは私だけでなく、大半の日本人がそうだと思います。実は、それは間違いではないのですが、正確でもないようです。彼らの想いは「石油利権目当て」という単純な欲望とは一線を画します。彼らがこの地域を眺めた時、そこに眠る地下資源は「元々自分たちの正当な所有物なのだ」という想いが憤りと共に沸いてくるらしい。
どうやら、これがキーでした。まあ、全然共感できませんが。
これが分かって、はじめて欧米支配層の中東政策も理解できると思います。そのためには石油をめぐる過去の因縁を紐解いていかねばなりません。
戦略物資「石油」をめぐる戦い
対イラク戦争の数年後、FRB元議長のグリーンスパンなど何人かの米の要人が「戦争は石油目当てだった」と主張しました。ただし、私はもう少し事情は複雑だと思っています。私は以下の記事で次のように記しました(*傍線は今の筆者)。

かつて“新保守”を自称し、世界の現状をホッブスのいう「万人の万人に対する闘争」、すなわちアナーキーで野蛮なジャングルになぞらえ、その中にあっては軍事力こそが秩序を保つ唯一の手段であり、よって悪者を叩き殺すことは正当であり、この論理を理解しえぬヨーロッパは仲間ではないと主張したPNAC(Project for the New American Century:アメリカ新世紀プロジェクト)は、公然と中東の軍事占領を画策した。それに基づいて実行されたのがフセイン・イラクへの攻撃であるが、(略)ここで着目したいのは、占領政策の失敗が明らかになった「後」のアメリカの行動だ。
当時のブッシュ政権はネオコンをパージし、国務省系の人材を入れ始め、エネルギー政策を180度転換した。そして「2005年度版エネルギー政策法」を可決し、中東石油からの依存脱却を鮮明に打ち出した。以来、アメリカは17年度までに、主にバイオエタノールの導入拡大と燃費改善によってガソリン消費の20%削減を達成しようと動いている。
つまり、米国は2005年に方針転換した。そして、その記事内でも触れているように、オバマ政権の時にはさらに石油脱却に向けた政策を推し進めました。
ちなみに、世界の現状を“アナーキーで野蛮なジャングルになぞらえ”たのは、ネオコンの理論的指導者のロバート・ケーガンで、彼の奥さんがクリントン・オバマ政権のヌランド国務次官補です。「影の政府」内では彼女のほうが大統領より上かもしれません。


ただし、ネオコンのPNAC(ピーナック)が猛威を振るっていた頃は、石油資源を押さえることが「動機の一部」であったことは間違いないと思います。
このように、歴史的に見れば、欧米の中東政策には、常に「石油」という戦略物資とそれをめぐる争奪戦も関係していたと思われます。
カスピ海と中東における石油開発の始まり
まあ、これは常識の範疇かと思います。で、もともとこの地域の石油開発は徐々に「南下」していく傾向があったんですね。以下の記事でも触れたように、最初はフランス・ロスチャイルドがカスピ海の石油を掘り当てました。

当時、ロックフェラーとは競争関係にありました。またの機会に触れますが、世界支配層からすると、ロックフェラー一世は本物の謀反人だった人です。巷間でよく言われている「ロック対ロス」の関係とはまた異なります。ロックフェラー一世は鎮圧され、両者の間で取引があって、二世から支配層にメンバー入りしたと私は推測します。

1世とデビッド・ロックフェラー
で、当時の仏ロスは、いったん傘下のロイヤル・ダッチ・シェルに油田を払い下げました。そして、ソ連の“同胞”にプレゼントしました。もちろん、教科書的な歴史では「共産党が資本家から接収して国有化した」ことになっていますが。
大雑把ですが、こうして19世紀末にカスピ海、そこからトルコ、イラク・イラン、そしてようやく1930年代に入ってからアラビア半島というふうに、おおむね石油開発は南下していきました。サウジの巨大「ガワール油田」が発見されたのが1938年ですね。これらに共通するのは、パイプを突き刺しただけで原油が噴出するという、いわゆる「イージーオイル」であることです。しかも、ことごとく大油田でした。
対して、当時、石油貧乏の日本は戦争へと突っ込んでいきました。インドネシアの油田があれば十分足りていたし、もっと我慢していれば、満州には大慶油田(1959年発見)もあったわけですが、ともあれ英米秩序に挑戦して叩きのめされました。
中東諸国のナショナリズムの前に撤退を余儀なくされた欧米資本
ただし、その代わりといっては何ですが、第二次大戦後には、アジア・アフリカでも「民族自決」「植民地独立」の運動が起きます。当然、中東においても「アラブ・ナショナリズム」が勃興しました(*イラン人はアラブ人ではないのですが、大半のアメリカ人には区別がつかないようです)。しかも、その矛先が向いたのが石油でした。

石油国有化の先駆者・イランのモサデク。1951年、首相に就任すると、英資本のアングロ・イラニアン石油を国有化。その後、米英の秘密工作によって政府が転覆させられ、逮捕・失脚させられた。
中東の人々の目には、それがたまたま居住地の地下に埋まっていようが、「欧米諸国がおれたちのモノを盗んで、不当に儲けている」と映ったんですね。
対して、欧米資本からすれば、「黒い液体がとんでもない宝の山であることが分かって、現地人たちが強欲にも要求を吊り上げ始めた」と映った。
当時、スタンダードオイルやロイヤル・ダッチ・シェルなど、「セブン・シスターズ」と呼ばれた欧米石油資本が、生産から販売までをほぼ独占していました。で、当初は「もっと分け前をよこせ」という“現地人の要求”を撥ね付けるか、少々の契約改訂でお茶を濁していました。
しかし、民族自決の気運から来る資源ナショナリズムの勃興という時代の波には、しょせん抗いきれません。この辺は細かく話すとキリがないので大雑把に言うと、要は石油資本側が自分たちに都合のいい政権を作ったり、現地側がそれに対して革命を起したりということを繰り返して、結局は中東諸国のモノになります。
1970年代に一挙に主従が引っくり返りました。リビアやイランなどは最終的に欧米資本を叩き出して、石油産業を国有化してしまいます。

1969年、カダフィはクーデターを起こし、政権を掌握。国王イドリス1世を廃位させ、共和政を宣言、自らは最高権力機構の評議会議長に就任した。石油国有化など、徹底的に欧米に対抗するが、2011年、リビアが内戦化し、欧米も軍事介入、反政府勢力により殺害された。
そこまで至らなかった国でも欧米資本側より優位に立ちました。そして、オイルショックを契機として、資源国側の組織であるOPEC(石油輸出国機構)が完全に主導権を握るようになりました。
以来、世界の石油市場の大半を支配していた欧米資本は押される一方で、現在では国営資本系が資源ストックの大半を押さえています。かつてのセブン・シスターズは合併して今なお世界最大級の企業ですが、独占時の威光は見る影もありません。
「おれたちの利権を横取りされた!」という欧米支配層のドス黒い恨み
さて、客観的真実はどうあれ、ここで重要なのは、結果としての「欧米支配層側の主観」なんですね。彼らはそれに基づいて行動しているわけですから。
欧米エリートからすれば、「現地人のやつらは結局、契約を反故にして、われわれのモノを横取りしやがった!」となるわけです。とくに彼らにとって「契約」は絶対の約束です。しかも「現地人にも配慮して、寛大にもそれなりに分け前をやっていたぞ」と信じ切っている。確かに「欧米帝国主義だ」「石油資源目当ての戦争だ」と糾弾するのは容易い。ただ、「盗人にも三分の理」というが、「もともとオレたちのモノだったのに強欲な現地人によって奪われた」という欧米支配層の不満も、全然分からないではない。
これが今なお欧米と中東諸国のトラブルの根幹にあると私は思います。彼らにしてみれば、こういう契約違反の不当な仕打ち(と彼らは思っている)は、いくら時間が経とうが、絶対に許せないわけです。彼らの立場で考えてみましょう。
カスピ海と中東に眠るエネルギー・ソースは何百兆円分にもなります。もしかすると、日本円基準だと、「兆」より一桁上の「京」(1京=1万兆円)レベルの資産価値かもしれません。彼らの考えでは、それは本来「自分たちの正当な所有物」なわけです。

しかも、リスクを背負って原油を掘り当てたのも彼ら欧米資本です。原油を精製し、内燃機関を発明し、石油化学を生み、ゴムやプラスチック製品を発明し・・と、様々な利用方法を考えたのも、すべて彼ら。だから、欧米エリートの自負心たるや、どれほどのものでしょう。しかも、彼ら的には、他人のモノを盗んだわけではなく、ちゃんと契約を結んで、正当に手に入れたわけです。何も悪いことをした覚えはない。
さらに、彼らの聖書的な思考でいえば、こういうのは「神が与えしもの≒嗣業(しぎょう)」に当たるんですね。日本風に分かりやすくいえば、世界支配層にとってエネルギー産業とは、金融と並んで「家業」だったんです。それを横取りされた。
だから、彼らの怒りと執着心、そして復讐心は、いかばかりのものか・・。それは単純な帝国主義的野心や欲望よりも、もっと複雑で厄介な感情なのです。
重ねて、私は共感しないと断言しますが、彼らには彼らの真実があるわけです。









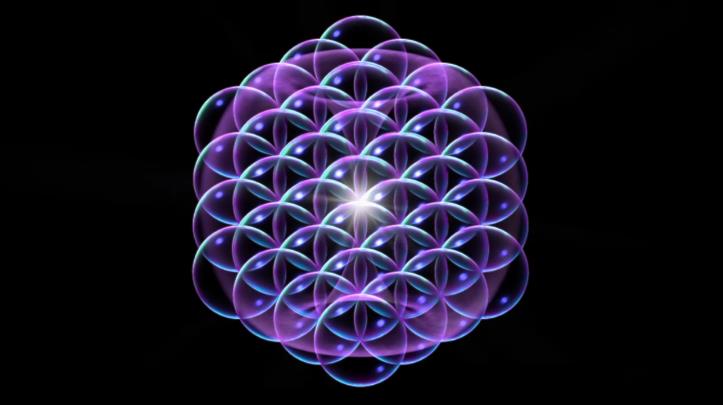


スポンサーリンク