後編です。(前編はこちら)
いきなりですが、小説の、小説らしい点とは何でしょうか?
それは「人の内面を克明に描写できること」だと思います。
これは小説の一番の長所です。映像ではなかなか難しいです。だから、心理描写に長けた小説を映画化すると、たいてい失敗作に終わります。
この短編は、実はそういった小説的長所を生かすことを意識しました。
ドラマは外部の世界にだけでなく、人の内面にもあるんですね。
松本清張の『顔』などはその代表例でしょう。
それでは後半をどうぞ。
脅迫者の報酬(後編)
社長の青山が日に日に憔悴していくのを見て、中村はしてやったりとほくそえんだ。
やはり、あの「キムチ、暴力団、覚セイ剤」という文言が効いたらしい。思いのほか的の真ん中を射たのかもしれないと思った。
この「成功」は中村を悪い意味で勇気付けた。社長が心理的に追い詰められるのに比例して、その秘書はますます邪悪になった。
いつしか中村は青山から大金を毟り取るべく、思案するようになった。
もっとも、それは彼にしてみれば、本来ストックオプションで受け取れるはずのお金だったので、いわば正当な権利であり、よって犯罪との認識はなかった。
わずかに疼く良心も、「おれがこんなことをせざるをえなくなったのも貴様のせいだ」という責任転嫁と、「部下からこんな風に思われる社長のほうこそ悪いのだ」という自己正当化の論理によって、跡形もなく消し飛んだ。
ダークサイドに堕ちた中村は今や、傲慢な青年実業家に対して、このおれが「罰」をくれてやるのだというような錯覚すら催していた。
考えた末、匿名口座を用意し、そこに大金を振り込ませるアイデアに落ち着いた。
むろん、その口座を獲得するプロセスで、己の素性がいかなる形であっても表に露出してはならない。それ以上に課題といえるのは、金の引き出し方法である。匿名のキャッシュカードを使用しても、ATMの防犯カメラに、ばっちりと容姿を録画されてしまう。強請られているとして青山が警察に駆け込んだ場合、警察は直ちにその録画を彼に照会するだろう。その瞬間、脅迫者が秘書であることを特定されてしまう。
中村は解決策を熱心に模索した。誰でも己の利益に直結することにはかけては勤勉な調査マンに変貌するものである。彼が行き当たった解決策は、その都度「出し子」を雇うというものだった。高額報酬を餌に、その場限りのバイトを雇えばいい。渋谷の繁華街にたむろしている少年たちで十分だ。互いに身元を知る必要もない。
結論は出た。目的はあくまで大金の入手である。
◇
よく晴れた平日の昼間だった。椅子に腰掛けて店番していた李文烈は、一見してその客を不審に思った。店先に現れたのは、サングラスで目元を隠し、口ひげを生やした長髪の男だ。右手に紙袋を提げている。
男は入店するなり、しきりに店内をきょろきょろとし始めた。怪しいが、品物を見定めているので、一応は客なのだろう。
やがて、男は店内の冷蔵ケースに入ったキムチの桶を指差すと、紙袋からタッパーを取り出し、「これに入れてくれ」と注文した。近所の、なじみの客はよくこういった買い方をするが、一見では珍しい。通常はビニール袋に入れたものを買っていく。
桶に入っているのは半分になった白菜なので、李は「一個ですか、それとも二分の一、四分の一ですか」と尋ねた。
男は一瞬躊躇したが、「このタッパーに入るだけ」と返事した。
李はタッパーの容積を適当に見繕って、まな板の上で白菜をカットした。
「毎度あり」李文烈はキムチを入れたタッパーを男に手渡そうとした。
しかし、男の顔を見ると、その目はあらぬ方角へと向いていた。
サングラス越しの視線の先を追うと、店内の隅で積み重なった新聞紙に行き当たった。それは包み紙として利用しているものだ。
その束の一番上がたまたま「日刊Jスポーツ」だった。なぜかは分からないが、客の視線がその数日前のスポーツ新聞の表紙に釘付けになっていた。
男は、眼前にキムチの入ったタッパーが差し出されていることに気付くと、慌ててそれを受け取り、「どうも」と口ごもってお金を手渡すと、逃げるように店から出て行った。
(最近は)李文烈は思った。(変な客が多い……)
◇
暗闇の中――。青山勇の顔が不気味な紫色の光線に照らし出されていた。
青山が変装してまで李文烈に直接、タッパーを手渡したのには訳があった。
彼の指紋を採るためである。青山は少しでも犯人に近づく手段として、脅迫状から独自に指紋を採取することを思いついたのだ。
タッパーのそれと比較してみれば、李文烈が犯人か否かもすぐに分かるはずだ。
青山はそのための方法を、わざわざ専門書やインターネットで調べた。
テレビドラマや映画などでは、警察の鑑識係が事件現場で指紋を採取している場面がよく登場する。あれは主としてアルミ粉末を指紋に吸着させてゼラチンシートに転写する手法である。だが、今日では捜査科学が進展したおかげで、指紋をくっきりと浮かび上がらせて採取する方法は、より多岐にわたるようになった。むろん、大半は特殊な薬品や技術を必要とするが、中には素人が比較的入手しやすく、また扱い易いのもある。
青山が選んだのが後者である。方法は、耳掻きの綿に蛍光粉末をつけ、それをはたいて指紋に吸着させ、紫外線ライトを照射するという、ごく簡単なものだ。こうすると、暗くした部屋の中で指紋がくっきりと浮かび上がる。道具は東急ハンズでもそろう。
青山としては、妻に心配をかけたくない気持ちもあり、今度の出来事を一切、家庭に持ち込みたくなかった。だから、日曜日のオフィスに出社するや、内側から執務室に鍵をかけて作業を開始した。
青山は、脅迫状の本文に蛍光粉末をはたき、紫外線ライト――いわゆるブラックライトを当てた。すると、黄緑色に光る指紋が多数、浮かび上がった。
「やったぞ!」青山は快哉を上げた。
どうやら脅迫犯は、自分の指紋を手紙に残すことまでは気が回らなかったようだ。
しかも、幸いなのはその種の無頓着だけでない。どうやら犯人は脅迫文をしたためるときに緊張し、通常よりも手の平の発汗が多かったに違いない。指紋は驚くほど鮮明だった。これならば素人でも他との違いを容易に判別することができる。
虫眼鏡を覗きながら、青山は思った。少しでも自力で犯人に近づくのだ、と。
彼がとくに注目したのが親指の指紋である。なぜなら、親指の指紋はひとりにつき左右ひとつずつしかない。それが右手のものか左手のものかも、他の指に比べて判別しやすい。
たとえば、調査対象を左手の親指の指紋ひとつに絞れば、その一種類がひとりの人物に対応するため、何人の人間が手紙を触ったかも分かるはずだ。
しばらくして、結果が出た。脅迫状本文に付着している親指の指紋は、青山のそれを除けば、ひとつだけだった。これは脅迫状がひとりの人物によって書かれ、青山が開封するまでは、その他の誰にも手に取られなかったことを意味する。
つまり、犯人は単独犯である可能性が高い。これが分かっただけでも収穫である。
青山は封筒のほうも調べてみた。こちらのほうには、多種類の指紋が付いていた。親指の指紋の痕から判断するに、どうやら五、六名がこの封筒に触れているようだ。そして当たり前ながら、その内の一つの指紋は、脅迫状本文のそれと一致していた。
一致しない残りの指紋は、集配や仕分けなどの郵便業者のものと、社内の人間のものだろう。社内では、総務部のアルバイトと秘書の中村がこれに触れているはずだ。
青山は緊張しながら、次にタッパーに付着した李文烈の指紋を浮かび上がらせてみた。直ちに脅迫状のものと比較してみたところ、二つはまったく異なっていた。
青山はその場で、思わず安堵のため息をついた。
やはり、あのキムチ屋の老人は脅迫者ではなかったのだ。
彼がそんなことをするはずがないとは思っていたが、それが改めて証拠付きで確認できたことは、今回の大きな収穫だった。
だいたい、店内に「日刊Jスポーツ」が積み重なっていたところを見ると、李文烈はかつて密輸に雇っていた青年が今や事業の成功者となっていることを、とうの昔に知っているのだ。にもかかわらず、今まで青山と連絡をとろうとすらしなかったということは、李老人には青山を強請ろうとか、たかろうという気持ちが毛頭なかったことを意味する。
だが、それが確信できたからといって、問題そのものが解決したわけではない。あくまで犯人を突き止めることが最終目標である。
いずれにしても、脅迫者本人の指紋は入手した。今、探偵のZ社に故李永吉周辺の暴力団関係者を洗わせている。調査の対象はさらに広がった。リストが出来上がれば、次の段階としてその中で「怪しい」と思われる者順に、指紋を入手していけばいい。そして脅迫者のそれと照合していく。こうして相手に対する包囲を徐々に狭めていくのだ。
むろん、それで犯人を特定することができるか否かは、今の段階では分からない。容疑者が今度の包囲網にかかるという保障はどこにもない。
だが、仮に特定することができれば、それなりに対処しようもある。
犯人が「影の存在」であることが余計に不安を掻きたてるのだ。だから、なんとしても独自に犯人を絞り込んでいかなくてはならない。
とりあえず今は、Z社からの報告書待ちである。
◇
中村はインターネットの「闇サイト」を片っ端から当たっていた。
「お手持ちの銀行口座を高価買い取りします」とか「売ります」といった類いの広告は、思いのほかたくさんあった。
どうやら、裏の世界では、金さえ出せば、通常の都銀の銀行口座はおろか、郵便口座やネット銀行の口座まで簡単に手に入るらしかった。
中には、免許証や国民健康保険証、プリペイド式携帯電話まで売りに出しているところもあった。わざわざ「当方は闇金融や振り込め詐欺等とは一切関係ありません」などと断りを入れているものもあり、失笑させられた。
中村はそんな広告の一つに連絡を入れた。それは携帯電話の番号だった。どうせ匿名のプリペイド式であろう。中村は身元が割れないよう、公衆電話を使った。
電話に出たのは中年の男だった。男は待ち合わせの場所と期日を指定してきた。都心の某駅前である。目印は中村がコカコーラの赤い缶を持っていること。
当日、取引は驚くほど簡単に済んだ。
赤い缶を持った中村に、ふいに男が話しかけてきた。
男が提示するところによると、著名な都市銀行の口座がひとつ三万円。中村がキャッシュで支払うと、相手はその場で通帳とキャッシュカード、そして暗証番号のメモを手渡した。通帳の残高は一円で、まったく見知らぬ人物の名前が記されていた。
むろん、互いに身元を明かす必要もなかった。相手が誰かなど、知りたくもなかった。
中村茂はこうして匿名口座を持つことに成功した。
◇
中村のもとに、探偵事務所のZ社から連絡が入った。報告書が出来たので、すぐに取りに来て欲しいとのことである。
中村は二番目の報告書を手にすると、さっそく中身を取り出し、コピーした。そして自分で用意した探偵事務所の社名入り封筒に厳封しなおし、青山に手渡した。
中村は自宅でゆっくりコピーに目を通した。
どうやら、青山の出した第二の依頼とは、故永吉周辺の暴力団関係者を調べることだったらしいと推測がついた。報告書には該当者として十数名が記載されていた。
李文烈の息子の永吉はすでに他界している。ということは、その永吉の周辺にいた人物から今度の脅迫状が出てきた可能性が高い…青山はそう考えたのだろう。
なにしろ永吉は六田組とかいう暴力団の元幹部で、その周辺の者も当然ながらすねに傷を持つ者たちである。彼らを怪しいと睨んだのは妥当な判断だろう、通常ならば。
中村は報告書のコピーを読みながら、さすがの青山も脅迫者がまさかすぐ目の前にいる人間だとは気付くまいと、ほくそえんだ。
◇
青山勇は二番目の報告書に目を通していた。
彼が覚せい剤の密輸に関わっていた過去が何らかの形で外部に漏れたとすれば、それは元締めだった李永吉の周辺だと推測するのが妥当だ。
報告書には、永吉と繋がりの濃かった暴力団関係者として、十数名がリストアップされていた。その中で九名が六田組の関係者だ。当時の若頭や舎弟など、会社組織でいえば永吉の上司・同僚・部下にあたる者たちである。
探偵の調査に拠ると、彼らの近況は様々だった。
今も落ち目の六田組にしがみついている者もいれば、独立して小さな組を構えている者、足を洗って堅気になった者までいる。表向き不動産会社社長として数千万円もの年収を稼いでいる者もいれば、定職のないチンピラ風情や住所不定・無職の者もいた。さらに周辺の人間として、スナック経営者になっている元愛人や、風俗店のオーナー、自動車修理工場の経営者、個人的な友人であるトラック運転手なども挙げられていた。
果たして、この中で彼の過去を知り、彼に脅迫状を送りつけた人物は誰だろうか。
やはり、怪しいのは金に困っている者である。つまり、経済状態を基準として、調査の優先順位を振ればいい。幸い、報告書には該当者の簡単な経済状態も記されている。
Z社への次の依頼は、この優先順位ごとの指紋の入手だ。これは今までのように間接的に調査するのとは訳が違うので、探偵事務所としても厄介な仕事だろう。ヘタすれば相手ともニアミスしかねない。当然、報酬アップを要求されるだろうが、背に腹は代えられない。そして入手した指紋を、自らの手で、脅迫状のそれと照合していくのだ。
青山は、改めて「脅迫者はこの十数名の中の誰だろうか?」と考えた。
◇
次からは金を強請っていくぞ……中村茂はそう決心していた。
だが、そのためには、青山にとってさらに具体的な恐怖が必要だろう。
幸い、第二の報告書のコピーを手に入れたことで、新たな文言を盛り込んだ脅迫状を作ることが可能だ。
その報告書には多数の暴力団関係者の名前が記されている。青山は彼らから脅迫状が送りつけられている可能性が高いと思い込んでいる。ならば、その思い込みを利用して、そう臭わせる文言を挿入してはどうだろうか。これは真犯人である自分から調査の矛先をうまく反らせるという意味でも、有効な方法であるように思われた。
中村は、これまで社長に送りつけた脅迫状を、改めて振り返ってみた。
最初は「オマエノ過去ノ秘密ヲ知ッテイルゾ」だ。
次は「二十代ノ前半ニ何ガアッタカ、知ッテイルゾ」である。
その次は少し変えて、「二十代ノ前半ニ何ヲシタカ、知ッテイルゾ」とした。
その後、第一の報告書の入手に成功したことにより、「手錠ヲカケラレタイカ? キムチ、暴力団、覚セイ剤」という文言を考え出すことができた。
青山の様子を見るに、この文言はかなりのショックを与えたらしい。
おそらく、脅迫状が段々と具体化していくことで、社長の青山は、目に見えない脅迫者の足音が徐々に迫ってくるような恐怖感を覚えているに違いない。
中村は考えた末、第五の脅迫状を次のような文面にした。
「ワレワレハ、オマエガ知ラレタクナイ過去ヲ知ッテイルゾ。組織ヲ見クビルナ。秘密ヲバラサレタクナケレバ、次ノ口座ニ百万円ヲ振リ込メ」
中村はこの前、手に入れたばかりの匿名口座の番号と期限日を記した。
今までは主語を記さなかったが、今回は初めて「われわれ」という主語を置いた。「組織」という単語と併せ、青山は自分を脅しているのは複数の六田組関係者と疑うだろう。
百万円という金額は、とりあえず相手を試したものに過ぎない。そのために払いやすい金額に設定した。むろん、これがうまくいけば、次々と要求を重ねるつもりだった。
成功すれば、金がひとりでに湧き出てくる金庫を手に入れたのと同じである。
◇
「社長!」中村が右手に一枚の封筒、左手に郵便物の束を抱え、さも心配げな表情で呼びかけた。「匿名の手紙がまた来ていますが、どうしますか? 一応、社長宛てのものはすべてお渡しするようにしていますが、これからはこちらで弾いておきましょうか?」
青山はその封筒を見るなり、さっと青ざめた。そして、手紙をひったくった。
「いや、いいんだ、今までどおりで。おまえは気にするな」
中村はいつものように郵便物の束を社長の机の上に置くと、一礼して去った。
六本木の本社には毎日、大量の郵便物が届く。それを部署ごとに仕分けるのは、総務部に所属するアルバイトの仕事だ。むろん、社長宛ての郵便物も少なくない。それを重要度ごとに仕分けなおして青山の机に置くのが、秘書の中村の仕事だった。
今回は青山の反応を直接、確かめてやろうと思い、このような仕儀に及んだのだった。換言すれば、どれだけ慌てふためくか、その情けない面を目の前で拝んでやろうという加虐的な思いつきから出た、気分的な行動だった。
青山は明らかに憔悴していた。このところ、食事も喉を通らない様子で、忙しいとの口実で来客も半数をキャンセルしていた。秘書としての仕事もめっきり暇になった。
(ヒヒヒ…)中村は内心で高笑いした。(相当、焦っていやがるな。今度の文面を見て、吠え面かくなよ)
傲慢な雇い主をビビらせてやったという思いは、それまで無理して卑屈に振舞ってきた彼の復讐心を、それなりに満たした。むろん、この青年実業家を完璧に「打ち出の小槌」に変えるまでは、彼の復讐は果されないのであった。
◇
青山は第五の脅迫状の文面を見た瞬間、ぎょっとした。と同時に、「やっぱり…」という言葉が無意識のうちに口をついて出た。
相手は散々揺さぶった後で、とうとう金を要求してきた。当然だろう。
しかも、「ワレワレ」とか「組織」などと記しているところが、いかにも六田組の関係者を想起させた。
もっとも、相手が複数犯と思える一方で、単独犯が複数のふりをしているようにも思われた。なぜなら、脅迫状の文面からは未知の指紋が一種類しか検出されていないからだ。だが、複数犯の中で、脅迫状作成の担当者が固定されているだけかもしれなかった。
青山はその夜遅く、社長執務室に閉じこもると、蛍光粉末と虫眼鏡を用意し、デスクの上でブラックライトを灯した。
「さあ、どうする? いよいよ破滅の到来か……」
ため息と共に、そんな独り言が漏れるのだった。
◇
中村は勝利を確信していた。
金を要求する脅迫状を送って以降、青山の憔悴ぶりは想像以上だった。今では社員も異変に感づいて噂するほど、見た目にもはっきりと表れていた。どうやら、脅しているのが複数の組関係者だと臭わせたことが、予想以上に効いたらしい。
ある日の夕方、中村は社長執務室に呼び出された。
げっそりと頬のこけた青山は、椅子に腰掛けるというよりは身体を支えていた。
「だいぶんお疲れのようですね」
秘書は目の下にクマを作った青年社長をねぎらった。だが、無精ヒゲを生やし、ネクタイをだらしなく緩めた男は、額を手で押さえてため息をつくだけだった。
「中村」青山が額を押さえたまま棚を指差した。「すまんが、そこのバーボンをとってくれ」
「よろしいんですか?」そう訊き返しつつも、中村は言われた通りにした。
青山は瓶の口の辺りを掴むと、グラスに琥珀色の液体を注いだ。そして間髪を入れずにぐいと飲み干した。
その様子を間近で観察しながら、中村は大金が手に入る日も近いとほくそえんだ。
「私でよかったら、社長の力になります。何なりとご相談ください」
青山は「そうか」と言ったが、信用していないのか、妙に暗い表情のままだった。
(おれも相当のワルだな)中村は内心で笑いを噛み殺した。
青山は机の引き出しから例の特殊な封筒を取り出すと、それを中村に差し出した。
「これをまたZ社に頼む…」
三番目の依頼書である。中村は受け取ると、すぐに探偵事務所に足を運んだ。
◇
今日は脅迫状に記載した支払い期限の日だった。
中村は前日からドキドキしていた。青山は結局、警察に相談しなかったようだし、あれだけ追い詰められた様子から察すると、要求された金額をそのまま飲むであろうことに疑いを差し挟む余地はなかった。
考えてみれば、ここに至るまで、まるで綱渡りのようだった。
すべては、試しに「オマエノ過去ノ秘密ヲ知ッテイルゾ」という、思わせぶりな文言を送りつけたことから始まった。すると、意外なほど効果が現れたことから、思い切って二通目を送ってみると、青山は彼を通して探偵会社への調査を依頼した。
そして、彼は探偵会社の名義入り封筒を入手することで、その報告書の内容を盗み見することに成功した。さらに、そうやって知った情報を脅迫状に反映させることで、より真に迫ったものとなり、今や闇サイトを通じて匿名口座までもを獲得した。
我ながら神業だと、中村は自画自賛した。今日、ようやくその成果が日の目をみるのだ。それまでの努力を思うと、感慨深かった。そしてここまで苦労したのだから、百万円の報酬を得ることは、もはや当然の権利であるように思われた。
夜の九時ごろ。背広姿をした仕事帰りの中村は、JR新宿駅北側に位置するアルタ前の広場で、「出し子」をやってくれそうな若者を探した。ここはフリーターやギャングっぽい若者たちで溢れかえっている。数人目で、該当者が見つかった。
「えっ、金を下すだけで一万円もくれんの?」二十代前後と思しき、鼻の穴の横にピアスをした若者が途端に喜色を浮かべた。「ホントかよぉ?」
「もちろんだ」
ふたりはさっそく近くのATMに向かった。
中村はそこから数十メートルほど離れた位置で、若者にカードと通帳、暗証番号のメモを持たせ、とりあえず五十万円の引き落としを指示した。
中村は若者が万一にも下した金をもって逃走しないよう見張りつつも、一方で己の計画の完全性を頑なまでに信じていた。匿名口座から金を下すに当たっては、その都度、今回みたく「出し子」を雇えばいい。そうすれば彼は一切、尻尾を掴まれることがない。
まさに無限の金を振り出す「打ち出の小槌」を手に入れたも同然である。
完璧な計画だった。中村は己の犯行に酔ってすらいた。
しばらくして、若者が戻ってきた。眉間に皺をよせ、妙な表情をしていた。
「あのさあ、リーマンの兄サンよぉ。ぜんぜん引き落とせないんだけどさあ…」
「なにぃ!?」
中村は通帳をひったくり、開いた。残高は一円のままだった。一瞬、匿名口座の売人に、使えない偽物口座を掴まされたのかと思った。
「暗証番号は合っていたけど、残高が足りねえから、引き出せねえってさ」
「…………」
つまり、青山が要求された金を振り込んでいなかったのである。
「くそっ!」中村は思わず顔を真っ赤にして激怒した。
その剣幕に躊躇しつつも、若者が片手を差し出した。
「あのう…バイト代…」
中村は財布から乱暴に一万円札を引き抜くと、若者に手渡した。
◇
翌日。中村はまだ怒り狂っていた。
この仕打ちに関して、相応の報いをくれてやらねばと決意していた。
とりあえず、青山の様子を偵察するのだ。スケジュールの確認という用事を作って、執務室に閉じこもる社長のところへ出向いた。
青山は、相変わらず、げっそりとしていた。無精ひげがさらに濃くなっていた。
中村が社長のスケジュールについて確認していた最中だった。
その間、青山は上の空で、なにやらぶつぶつ言っていた。
「…ばれたら、身の破滅だ。…まだ時効じゃない…。ベンチャー企業の社長ともあろう者が……空前のスキャンダルだ。…マスコミのやつらは…ハイエナみたいに、一斉に飛びつくぞ…。連日、パパラッチに追い回され…フラッシュの雨だ…。財界への復帰は…いや、それどころか、社会復帰も難しいかも……」
ところどころで聴こえてくる独り言は、まるで絶望の歌声だった。
社長は頭がおかしくなりつつあるのだろうか。もしかして追い詰めた過ぎたのかもしれないと、中村は本気で心配した。
青山は適当に「分かった」と相槌を打って、もういいぞという風に手で払う仕草をした。
去り際だった。ドアのノブを握った中村の耳に、背後から独り言が耳に入った。
「やるしかない……やるしか…」
中村がぞっとして振り返ると、椅子を回転させた青山が窓の向こうを虚ろな表情で見つめていた。
◇
中村は新たな脅迫状をしたためた。今度は何日もかけて文面を練った。
それは強い非難を含んでいた。また、「百万円」という安すぎる金額が、かえって相手に悪戯との印象を与えてしまったのかもしれないと反省し、金額を一気に二千万円に引き上げることで脅迫者側の本気度を示した。
「ナゼ期日マデニ百万円ヲ振リ込マナカッタ? 罰トシテ今度ハ金額ヲ増ヤス。組織ヲ甘ク見ルナ。オマエハ二十代ノ前半ニ人ニ知ラレテハマズイコトヲシタ。ワレワレハ、オマエノ秘密ヲ知ッテイル。オマエヲ破滅サセルコトナド容易イ。ソレガ嫌ダッタラ、今度ハ期日マデニ必ズ二千万円ヲ振リ込メ。モシ金ヲ支払ワナケレバ、組織ハオマエニ制裁ヲ加エル。コレハ単ナル脅シデハナイ」
中村は匿名口座の番号と期限日を最後に記した。そして、今度こそ金を支払わせてやるという決意を込めて、池袋のポストから投函した。
自信はあった。青山は最近、秘書を含め、容易に他人を近づけなくなっていた。社長執務室に閉じこもり、用事があればそこから連絡をよこした。
それは彼が心理的に絶壁にまで追い詰められている証拠だった。そのおかげで、秘書としての仕事が減った中村も、暇をもてあまし気味だった。
むろん、相手に対する同情など露ほどもなかった。心の中にあるのは、傲慢社長をここまで打ちのめした己の力量に対する誇らしさと、復讐してやったりという満足感、そして絞れるだけ搾り取ってやるぞという貪欲で固い決意だけだった。
もう一押しのはずだった。
◇
それから一週間ほど経った頃だった。Z社から中村のもとに連絡が入った。第三の報告書が完成したという。中村は探偵事務所に赴いた。
「実は、これが完成したその日に、新たな事態が生じまして…」担当者が封筒を持ち上げつつ言った。「それで、ページの最後に、そのことを追加した格好になりました」
「新たな事態とは何ですか?」
「お読みいただければ分かると思います」
担当者はあくまで口頭では明かさなかった。
まあいい、と中村は思った。どうせ盗み見すれば分かることだ。
中村は封筒を開封すると、例のごとく中身をコピーした。その際、「追加」と銘打たれた、報告書の最後のページにだけ目を通した。
「東上野のキムチ屋夫妻の失踪の件について」と題されていた。
一瞬、目を疑った。最後のページに添付されたその臨時の報告書によると、数日前から李文烈(イムンヨル)と妻の朴秀美(パクスミ)が姿を消しているという。
いったい、どういうことだろうかと中村は訝った。とりあえず、自分で用意したZ社の社名入りの封筒に報告書を入れなおし、それを青山のもとに届けた。
社長執務室にいた青山勇は、まだ日が降りていないにもかかわらず、酒臭かった。最新の脅迫状がさらに心理的な打撃となったのだろうと、中村は推測した。
青山の表情は奇妙だった。なぜか、クマに縁取られた目だけが輝いていた。
それはしばしば狂気の域の入った者が見せるような、妙に爛々とした光だった。そして、しきりと「やってやったぞ」などと、ぶつぶつ独り言を口にしていた。
中村は少し怖くなって、用事が済むなりそそくさと部屋を出た。そして、外で場所を作って、三番目の報告書に目を通し始めた。
探偵の調査は、元六田組の組員であるDとGを中心に進んでいた。どうやら、青山は前回の十数名の中から、この二人にあたりをつけたらしい。
あるいは、調査対象を絞ったというよりは、単に調査の優先順位なのかもしれない。というのも、二人とも経済状態が一番悪い部類に属するからだ。前回の報告書では、どちらも住所不定・無職とだけ簡潔に記されていた。
新たな報告書によると、Dは山谷地区の「ビジネスホテル」に暮らしており、Gは友人・知人の家を転々とする居候らしい。二人とも無職のチンピラといって差し支えなく、収入も日雇い労働など不安定で、その日暮らしのようだ。
いずれにしても、青山がまったくの別人を犯人だと思い込んでくれているのは、都合がよかった。
中村は改めて報告書の追加分に目を通した。あのキムチ屋の主人が忽然と姿を消したらしいが、よく読むと近所の人への聞き込み内容も記されていた。誰に訊いても「分からない」という返事だという。中村はこれが何を意味しているのだろうかと考えた。
その時だった。突然、先日の青山の姿が脳裏に蘇った。
彼は窓の外を見ながら「やるしかない…」と呟いていた。
「まさか…そんな…」中村は背筋が凍るのを感じた。
そして、ついさっき、異様に目を輝かせた青山がぶつぶつと口にしていた独り言の内容が、唐突に思い出された。中村は顔面蒼白になった。
青山はたしかに「やってやったぞ」と言っていた。
◇
中村は自分の目で確かめることにした。
東上野のキムチ屋に向かった。店は平日にもかかわらずシャッターを下していた。
その日は通り過ぎただけだったが、数日後、また様子を見に行った。やはり、シャッターが閉じていた。中村は近所の人に尋ねてみた。
「いきなり店を閉めたんだよ」
李夫妻と知り合いだという中年の女は、不審そうに口を尖らせた。
「隣近所に対して『少し店を閉める』とか、そういう伝言はなかったんですか?」
「ないさね。おかげで、ここの美味しいキムチが食べれなくて困っているよ。警察に届けたほうがいいのかしらねえ…」
その翌日だった。中村はいきなりZ社から呼び出しを受けた。
前回の依頼に関係して、また追加の報告があるという。
中村はZ社から薄い封筒を受け取った。中を開けてみると、報告書も数ページしかないぺらぺらの代物だった。その文面を見た瞬間、中村は衝撃を受けた。
「調査中だったDが突然、行方不明になっただと?」
中村は思わず独語した。
「そんな馬鹿な…」
その書面には「最近、殺されたらしいとの噂も流れている」と記されていた。
キムチ屋夫妻に続いて、Dまでが消えた…。
偶然ではありえないと中村は思った。おそらく、彼らは殺されたのだ!
Dに関しても、李夫妻のように直に確認したかったが、ドヤ街に住んでいては、それも不可能だった。
そして、殺す動機を持っている人間といえば、この世にただひとりしかいない…。
中村は報告書をZ社名義の封筒に入れて厳封しなおすと、社長執務室を訪ねた。
そして、恐る恐る青山の顔を見た。
彼は狂人めいた顔をしていた。とくに目つきが尋常ではなかった。
中村は臨時の報告書を手渡した。すると、青山はその場でいきなり封筒をビリビリに破いてデスク脇のゴミ篭に捨てた。それは今までになかった行動だった。
「読まなくていいんですか?」
青山は答える代わりに、「もういいぞ」という風に手で秘書を払った。
中村がドアから退室しようとしたその瞬間だった。
突然、背後で狂ったような笑い声がした。彼はぎょっとして振り返った。
報告書を手に持った青山が、勝利感に酔った表情で、半ば涙目で笑っていた。
◇
ほどなくして、中村にも何となく事情が見えてきた。
数人のヤクザ者から会社に電話が入るようになった。相手は組織名こそ名乗らなかったが、それでも口調からその筋の人間であることが察せられた。
相手はいつも「合田からだと伝えてくれれば分かる」とか、「おれは吉田だ」とか、そういう連絡の入れ方をした。
青山にそのことを報告すると、両者はすぐに長電話に入った。
また、中村は久しぶりに秘書として運転手をさせられるようになった。しかも、行き先が今まで行ったことのない派手なクラブなどだった。
そこで青山は、いかにもヤクザ者という風貌の男たちと落ち合った。
そんなある時、中村は驚くべき光景を目にした。青山とヤクザ者たちが一緒にクラブから出てきた時だった。別れ際、ヤクザ者のほうが腰を低くして「それじゃあ、例の件は調べておきやす」と言った。それに対して、胸を反らした青山が「おう、頼んだぞ」と横柄に言った。青山が車に乗り込むと、ヤクザ者たちは「行ってらっしゃいやし」と、お辞儀をして見送った。その光景は誰が見ても仲間内の上下関係だった。
「だ、誰ですか、あの方たちは?」中村は思い切って尋ねてみた。
後部座席にふんぞり返った青山は、ぞんざいに返事した。
「おまえは知らなくてもいい」
中村は恐怖に近いものを感じ始めていた。自分は今までとんでもない思い違いをしていたのではないかと考え始めた。青山勇という人物は、暴力団関係者と何らかの繋がりがあるというよりは、関係者そのものではないのか。
つまり、この「ワーカーズドア」という会社は、いわゆる「舎弟企業」ではないのか。
「おれはもしかしてヤクザの会社を強請っていたのか…」中村は慄然とした。
仮に開業資金が暴力団から出ていたとすれば、自分は今まで、彼らが世間から隠しておきたい、まさにその弱みを激しく突付いていたことになる。
おそらく、己の過去の秘密を握られ、強請られたと思った青山は逆襲に出たのだ。自分を強請ったと思われる者をリストアップし、闇の勢力を動かして消しにかかった。あのキムチ屋の夫婦も、山谷に住んでいるというDも、そうやって殺されたに違いない。
中村は社長の恐ろしい素顔を知った気がして、ぞっとした。大変なことになったと震え上がった。なぜなら、彼らの矛先がいつ自分に向いてくるやもしれないからだ。
しばらくして、再び異常事態が起こった。
またしてもZ社が臨時の報告書を出した。中村はそれに目を通すなり、くらくらとした目眩を覚えた。
なんと、今度はGが姿を消したという。
急に寒気がして、鳥肌が立った。
報告書でそのことを知るなり、青山は狂気めいた笑みを浮かべた。
「あの野郎、やってやったぜ」本性をむき出しにして、青山が叫んだ。
中村は無言で一礼し、一刻も早く執務室を去ろうとした。
「どうした、中村?」
いきなり背後から声をかけられ、飛び上がりそうになった。
「え?」恐る恐る振り返った。
「顔が蒼いぞ」
◇
二千万円の振込みを指示した第六の脅迫状の期日は今日だった。中村はとてもではないが確認する気にはなれなかった。このような追加の脅迫がさらに青山を激昂させ、犯人探しを加速させたであろうことを思うと、後悔すら襲ってくるのであった。
青山がZ社に第四の依頼書をしたためた。中村はいつものようにその書類の入った封筒を無事に先方に届け終えると、帰社するなりそのことを社長に報告した。
「ちょっとこっちに来てくれ」青山が彼を呼びつけた。
社長執務室に入るなり、中村はぎょっとした。部屋の中が真っ暗だった。青山の顔が紫の光線に照らし出されて不気味に光っていた。
「な、なんですか、それは?」
「これはブラックライトってやつだ」紫の光の中で青山の目がいっそう狂人めいた光を放った。「実はこのところ、会社に悪戯の手紙が来ていてな」
青山が例の脅迫状の入った封筒を掲げてみせた。
「い、悪戯ですか…」
「ああ。それも相当、タチの悪いやつだ」
「け、警察に届けたほうが…」
「あん?」青山は眉間に皺をよせ、ひどく怪訝な表情を浮かべた。「別にポリ公の力なんか必要ねえ。自分の問題は自分できっちり落とし前つける」
「し、しかし…」
青山が机の上に置かれた小瓶を手に取り、揺すってみせた。中には黄色く光る粉末が入っている。それは闇の中で奇妙に美しかった。
「実は、この蛍光粉末とブラックライトを利用して、手紙の主を調べているんだ」
「え!?」
「脅迫状の本文から、なんとか相手の指紋が取れたよ。指紋はひとり分だけだった。あとは相手を探し出して、落とし前をつけるだけだ」
「!」中村はハッとした。
自分は今までずっと素手で脅迫状や封筒を触っていた。指紋のことまで気が回らなかった。そこまでやるかと思った。
「さっきZ社に届けてもらった依頼だけどな」青山が不気味な笑みを浮かべた。「脅迫状の封筒に付いた指紋を片っ端から調べてもらうことにしたんだ。郵便ポストからおれのところに手紙が届くまで、いろいろな人間が触っている。ポストの収集人、局内の仕分け人、この地区の配達人…探偵を使ってそれぞれの指紋を手に入れるつもりだ。そうやって封筒から無関係な指紋を排除していく。むろん、社内で触った者も例外じゃない」
「で、ですが、犯人はひとりで、指紋も取れているとしたら、わざわざそんなことをする必要はないのでは…」
「たしかに本文にはひとりの指紋しかないが、それは脅迫文の作成者がひとりであることを意味するだけであって、必ずしも犯人が単独犯であることを意味するわけではない」
「と言いますと・・」
「たとえば、犯人が複数いて、文章を作成する人間と郵送する人間とに担当が別れていれば、その他の犯人の指紋が封筒に付いていることも考えられるわけだ。だから、封筒を触ったと思われる関係者の指紋を片っ端から採って照合していけば、正体不明の指紋、つまりはその他の犯人のものと思われる指紋が浮き彫りになる可能性もあるというわけさ」
青山はそう言って、凄みの利いた笑みを浮かべた。
(関係者の指紋を片っ端から採っていく…)
中村はガクガクと膝を振るわせた。暗闇であるのが幸いだった。
◇
その一週間後。
中村はまた社長執務室に急に呼び出された。
青山が代表席で身を反り返らせて、ゴルフクラブのヘッドや軸を磨いていた。
「よう、中村、おはよう」青年社長はやけに機嫌がよかった。「実はな、郵便関係者の指紋がすべて採れてな。急いでいたんで、Z社に連絡をして、いつものようにおまえを介さずに直接、こっちに届けさせたんだ」
「そ、そうですか…」
「封筒に付いた指紋との照合も済ませたよ。これで残る正体不明の指紋は、あと数個に絞られた。今度は、順番に社内の人間を調べていくつもりだ」青山はタオルの動きを止めると、上目遣いに中村を見た。「当然、おまえにも協力してもらうからな」
中村は顔面蒼白で立ち尽くしていた。彼は自分の身体が小刻みにぶるぶると震えていることにすら気付いていなかった。
突然、青山が椅子をくるりと半回転させると、座ったままダーツの矢を投げた。それは執務室の壁に掲げられた的に命中した。
「必ずやってやる!」青山が激昂して叫んだ。「誰が金なんか払うもんか! 地の果てまで追いかけて殺してやる! おれを強請るやつは、すべて地獄行きだ!」
◇
中村は追い詰められていた。彼は恐怖のあまり、完全に不眠症になってしまった。
脅迫状を送りつけたのが彼だとばれるのは、もはや時間の問題だった。そしてその時、彼を待ち受けているのは、李夫妻やDやGと同じ運命だ。
中村は必死で頭を回転させた。
このままでは自分も消される。いったいどうすればいい? いっそうのこと、青山に対して洗いざらい白状し、土下座して謝罪し、命だけは助けてくれと懇願するか?
いやいや、今さら許してもらえないだろう。なにしろ、社長の秘密を知り、強請ってしまったのだから。
それに、彼らはすでに四人もの人間を消している。自分だけお目こぼしに預かると期待するのは、まったく甘い見通しと言わざるをえない。
だが、謝罪が通用しないとなれば、他にどんな方法があるのか。
殺される前に、警察に逃げ込むか? しかし、自分が脅迫者であることも打ち明けなくてはならず、前科者になってしまう…。
だが、命あっての物種である。背に腹は代えられないと中村は決意した。
◇
「助けてください、このままでは殺されまる!」
中村は最終手段として、自分が罪をかぶることを承知で地元の警察署に駆け込んだ。
彼は応対に出た刑事相手に、次のように必死で訴えた。
つい出来心で、会社の社長に悪戯の脅迫文を送りつけてしまった。すると社長はキムチ屋の老夫婦が脅迫者だと疑った。探偵事務所に調査も依頼しています。しばらくしてその老夫婦が失踪しました。おそらく殺されたと思います。それから、社長は元六田組の組員であるDとGを脅迫者だと疑った。彼らも相次いで姿を消しました。ふたりとも殺されたと思います。殺ったのは、うちの会社の社長と彼が関係する裏の組織に間違いありません。もうすでに何人も消されている。今度は私の番なんだ! このままでは私も彼らと同じように消されてしまう! 刑事さん、なんとか私を助けてください!
中村はこれまでの出来事を洗いざらいぶちまけた。殺されるよりマシだった。
地元署の刑事たちは、彼の証言に驚愕した。
本当なら連続殺人事件の可能性がある。彼らは直ちに捜査を開始すると約束した。
しばらくして、刑事たちは中村を呼びつけた。
「ガセを掴ませたな!」彼らはひどく怒っていた。
なんでも、しかるべき筋にちゃんと確認をとったという。
「そんな馬鹿な!?」中村は必死で抗弁した。「本当の話なんだ、信じてくれ!」
刑事たちは中村のほうを調べた。血液や毛髪も採取したが、薬物を使用した形跡は見当たらなかった。彼を拘留する理由はなかった。
中村は「私の身を保護してくれ、自分は脅迫罪を犯したから逮捕してくれても構わない!」などと訴えた。だが、刑事たちは「何の罪も犯していない者を逮捕するわけにはいかない」と返答して、取り合わなかった。
中村は警察署から追い出された。彼は呆然として、地元署の玄関を振り返った。
どうやら、警察は彼のことを守ってくれそうにない。中村はふと、青山が金をばら撒いて、警察にうまく手を回したのではないかと勘繰った。そうに違いないと、彼は己の思いつきに納得した。その考えは、すぐに彼の中で「事実」と化した。
なんということだ、と戦慄した。
彼は警察の腐敗ぶりに絶望した。もはや恐怖で理性は失われていた。
週末の深夜だった。突然、自宅に電話がかかってきた。青山からだった。
「夜遅くすまんな」青山の口調は不自然に機嫌がよかった。「実は、今度の日曜日だが、S山にキャンプに行きたいんだ。すまんがおまえに運転手をしてもらいたい…」
休日出勤を命ぜられたのは初めての経験だった。中村は直感した。脅迫状の主が彼であることを、やつらがついに探り当ててしまったのだ、と。
とうとう、追求の手が彼にも伸びた。連中はキャンプにかこつけて、人里はなれた山奥で彼を殺害するつもりなのだ。中村は恐怖で発狂寸前になった。
(もう駄目だ。このままでは確実に命はない…)
中村はやむなく、日本から逃げることを決意した。
◇
預金の全額を下した中村が、東京の住まいを引き払って慌てて東南アジアに逃亡したという報告をZ社から受けた青山は、突然、にんまりと微笑んだ。
それはまるで雲間から陽が射したような笑顔だった。
彼は久しぶりに無精ひげを剃り落すと、髪を整え、クマに見せかけた目の下の化粧を拭った。それからデパートに向かって、飛び切り高価なワインを買った。
「今日は乾杯だ!」
帰宅するなり、青山は手に持ったワインを掲げた。
「あら、どうしたの、あなた?」美香子が不思議そうに微笑んだ。「しばらくお髭を伸ばすって言ってなかったかしら」
「もう、いいんだ、そんなことは」
美香子は、妙に祝杯ムードの夫の気持ちを量りかねていたが、それでも愛する夫が幸せそうな様子だと、自分もつい嬉しくなるのであった。
その夜、青山勇は、意味も分からぬまま微笑むと妻と、ワインで乾杯した。
◇
実は、中村はひとつだけミスを犯していた。
それは、青年社長が狼狽する様を直接拝んでやろうという加虐的な思いつきをし、その喜悦に屈したことである。その精神的な欲が仇となった。彼はそのため、社長の目の前で脅迫状の入った封筒を掴むという、致命的な失敗を犯したのである。
中村が封筒を掴んでいた位置には、当然、彼の親指の指紋がくっきりと付着している。青山が例によってブラックライトと蛍光粉末でその手紙を調べた際に、中村が握った位置にあった指紋と、手紙の本文にある指紋とが完全に一致した。
当初、青山は「まさか?」と驚いた。何かの間違いではないかと思った。
今までは無意識のうちに「犯人の指紋と中村の指紋が同じであるはずがない」という思い込みがあり、本文と一致する指紋が封筒の表面に付着していても、それはあくまで「犯人のもの」であって、中村のものではないと信じていた。中村の指紋は「一致しないその他複数の指紋の中に含まれるひとつである」と、ずっと思い込んでいたのだ。
だが、中村が彼に封筒を差し出して見せた際の、その時の手の位置関係は、青山の記憶に鮮明に焼きついている。その位置にある指紋が中村のものであることは、間違いなかった。にわかに、それまで無意識のうちに当然としてきた、「犯人の指紋と中村のそれとは別である」という常識や前提が揺らいだ。
青山は最初、自分を疑った。自分の「勘違い」かもしれないと思った。そこで、それを確かめるためにも、中村を執務室に呼びつけて、バーボンのボトルを握らせ、さらに鮮明な彼の指紋を採った。改めて調べてみた結果、やはり中村の指紋は、脅迫状本文に付いているそれと一致した。もはや間違いなかった。脅迫状を送っていたのは、自分のすぐ身近にいた男、それも秘書だったのだ。
なんということか、と青山は思った。
驚愕すると共に「なぜ?」と青山は考えた。思い当たるフシがあるかどうか、考えてみた。動機面については、しょせんは本人の心のうちなので、よく分からなかった。
だが、金を要求してきたことから、金が目的であるのは確かだと思われた。いずれにせよ、脅迫者の正体が判明したことで、青山は急に冷静な自分を取り戻すことができた。
考えてみれば、脅迫者は今まで、核心部分である「青山が覚せい剤の密輸に従事していた」という事実については一切、触れようとしなかった。なぜだろうか。もしかして、知らなかったからではないか。
つまり、具体的なことは何も知らずに、脅迫を開始し、それがたまたま青山が潜在意識下に封じ込めてきた恐れをうまく刺激することに成功したのではないだろうか。
そう推測して、青山は改めて過去の脅迫文を振り返ってみた。
最初は「オマエノ過去ノ秘密ヲ知ッテイルゾ」だ。二番目は「二十代ノ前半ニ何ガアッタカ、知ッテイルゾ」。そして三番目が「二十代ノ前半ニ何ヲシタカ、知ッテイルゾ」である。今にして思えば、初期の三通は、極めて曖昧な文ばかりだ。
青山は突然、あることを思い出して、ハッとした。それは以前、ある雑誌が行ったインタビューだった。記者はその時、ビジネスを始める際の種銭について彼に質問した。その際、彼は妙に躊躇し、笑ってごまかしてしまった。思えば、その取材を手配したのが秘書の中村だったのだ。彼はインタビューの最中、すぐそばに立ち、その様子を見守っていた。おそらく中村は、社長の狼狽振りを見逃さなかったのだ。
仮に中村が、彼がビジネスをスタートさせた際の資金の出処に疑問を持っていたとしたら、この初期の三通については十分に説明がつく。
だが、だとしたら、四通目の脅迫文はどう説明するのであろうか。それは「手錠ヲカケラレタイカ? キムチ、暴力団、覚セイ剤」という、実に具体的な名詞を含んでいる。
謎の答えはすぐに思い浮かんだ。この四通目が届いたのが、Z社が作成した第一の報告書の後であることに気付いたからだ。仮に中村がその報告書に目を通すことができれば、そのような具体的な字句を脅迫状に挿入することも可能だ。
つまり、そのことから、中村が何らかの方法で開封していたに違いないと推測することができた。だが、仲介役の中村が、Z社への依頼の中身も、またそのレスポンスである報告書の中身も知ることができないよう、手を打っていたはずではなかったか。
実際、中村が彼に届けていた報告書は、常に厳封されたままだった。開封した痕跡がないにもかかわらず、彼はどうやって中身を知ることができたのだろうか?
新たな謎が生じた。そこで青山は、例の指紋検出の手法で、本来は指紋を採取する必要のなかった、報告書の入った封筒のほうも調べてみることにした。
その結果は青山を驚かせるに十分だった。なんとZ社の封筒からは、青山の指紋以外には、中村の指紋しか検出されなかったのだ。これは本来、ありえない話である。Z社の封筒には同社の関係者と思しき指紋が多数、付着していなければおかしいからだ。
さらに奇妙なのは、Z社の封筒だけではなく、厳封されているはずの報告書それ自体にも中村の指紋が多数、付いていたことだ。
だが、これで「中村が何らかの方法で開封していた」という推測が裏付けられた。
青山は彼の使った手口を考えてみた。その結果、この封筒自体がZ社の用意したものではないという結論に行き着いた。中村は何らかの方法で、探偵会社のネーミングの入った封筒を手に入れたのだ。
おそらく、それを刷っている印刷屋を見つけ出し、直接、封筒を買い取ったのであろう。中村は、Z社から報告書の入った厳封封筒を受け取る度に、それを破いて報告書を取り出し、自分で用意したそれに入れ直して青山に提出していたのだ。報告書はその場で目を通すか、コピーすればいい。中村はこうして、四通目の脅迫状に「キムチ、暴力団、覚セイ剤」という具体的な字句を挿入することができたのであろう。
いずれにせよ、脅迫者の正体が判明し、報告書開封の手口についてもあたりがついた。
そしてその時から、両者の逆転が始まったのである。
◇
今度は、一転して青山のほうが中村を追い込む番となった。
青山は最初、すぐに警察に届けようと思った。もちろん、秘書が社長に脅迫状を送りつけていた事件ともなれば、マスコミの興味を引くだろう。ましてや今を時めくベンチャー企業のスキャンダルともなれば、格好の餌食ともなりかねない。だが、当初はそれを覚悟で警察沙汰にする他ないと思っていた。
だが、よくよく考えてみればそれは賢い選択ではなかった。なぜなら、キムチ屋の件を中村が知ってしまったからだ。
あの男はまた、青山がそのキムチ屋に関連する「何か」を恐れていることまで知っている。それがビジネスを始める際の資金に関わることも。
仮に、脅迫者が中村であるとして警察に届けるとなると、たしかに彼は逮捕されるだろう。だが、その結果、警察に売られたと思った中村が報復行動に出るかもしれない。あることないことを供述して青山を陥れようと画策する可能性もある。
中村の供述次第では、キムチ屋の李文烈と彼との関係について警察が疑い、探ることもありうる。もし警察が本格的に動き始めれば、キムチ屋を経営する李文烈の息子が、かつて六田組の幹部だった李永吉であることくらい、すぐに調べがつくだろう。
そしてそこから、六田組が過去に実施していた覚せい剤密輸の手口についても嗅ぎつけるかもしれない。さらに、その運び屋をしていたのが青山であったことまで・・・。
実際、両者の過去の関係とは、そういうものだったのだ。
雑魚を葬ることに異議はないが、そのためにわざわざ己が刺し違えたのでは何の意味もない。よって警察に届けるのは控えたほうがいいように思われた。
では、どうすればいいのだろうか。
青山は考えた。要は、中村が何を言ったところで、警察が相手にしなければいいのだ。仮に中村の信用性を失わせることができれば、彼が警察に駆け込んだところで、その証言はまったく見向きもされないだろう。
つまり、警察における中村の信用を失墜させると同時に、自発的に脅迫ゲームを止めさせ、かつ会社を辞めさせればいいのだと思い立った。
幸い、中村はZ社の社名入り封筒を用意することはできても、青山が依頼書を入れるために用意した特殊な封筒は自前で調達できないらしい。
つまり、彼は依頼書の中身を覗き見ることはできない。ならば、探偵事務所側と連携して中村を罠にはめることも可能なはずだ。
青山は初めて、中村の頭越しにZ社に連絡をとった。Z社サイドでも、中村が単なる仲介役に過ぎない事情は承知していたようで、真の依頼者――しかも追加の支払いを惜しまない富裕な実業家――の登場を歓迎した。
両者は密かに作戦を練った。その結果、青山が実はヤクザ組織の人間で、自分を脅迫したと疑った者たちを闇のコネクションを使って片っ端から消しにかかったと、中村に思わせることにした。そしてその矛先が最終的に自分に向かってくると錯覚させることで、恐慌に駆られた中村がトンズラするように仕向けることにした。
青山は心理的にますます追い詰められていく演技をし、探偵たちは彼と関係しているヤクザ者のふりをした。中村は、青山が自分の頭越しに探偵事務所を抱き込んでいるとは露とも知らず、次々と人が「消されて」いく報告書の内容を真に受け、戦慄した。
青山は李文烈とも再会した。李老人はすでにマスメディアを通して、青山がベンチャー企業の社長であることを知っていた。彼は青山の出世を、まるで我が息子のことのように喜んだ。ふたりは長い間、話し合った。李は息子が亡くなったことを一種の天罰と考えていた。覚せい剤を広める手助けをしてしまったことについて、彼は心から悔い、社会に対して申し訳ないと思っていた。その想いは青山もまったく同じだった。彼が交通遺児基金などに寄付をしているのも、社会に対するせめても償いとのことだった。青山はその志に共感した。彼は財団設立の構想をさらに進めることにした。
青山は李夫妻を一ヶ月の海外クルーズに招待した。
当然、李夫妻は大喜びした。ただし、青山は条件を出した。ひとつは店のアルバイトに対して有休扱いで給与を支給すること。もうひとつは、そのことを近所の人には一切教えず、また店のシャッターに長期不在をわざわざ通知する張り紙はしないこと。
李文烈は「せっかく招待してくれるのはありがたいが」と前置きし、前者についてはともかく、後者については困ると言った。青山は当初「空き巣を招くようなものだから」などと説明を試みたが、それでも李老人が納得しなかったので、仕方なく自分が脅迫されている事実を話し、その男を担ぐために協力してほしいと頼み込んだ。
さて、中村の「告発」を受けた警察は、当初、仰天し、当然ながら捜査を開始した。
警察は、青山勇という青年実業家と、彼の会社であるワーカーズドアが、ヤクザ組織やその資金と何らかの繋がりがあるかどうか、捜査した。
その結果は完全なシロであった。
また、東上野でキムチ店を構える李夫妻の行方を追った。その結果、夫婦そろって海外クルーズに出かけたことが判明した。アルバイトたちの証言も得た。彼らは、その間は有休扱いだといって喜んでいた。つまり、李夫妻は「消されて」などいなかった。
元六田組の組員であったDとGに関しても調べが行われた。Dは山谷地区の簡易宿泊所のひとつに泊まっており、またGは友人宅に居候していた。
ちなみに、Z社がなぜ「殺される」役としてDとGを選んだかというと、ふたりとも住所不定の人物であり、捜査機関やプロの探偵ならともかく、中村のような素人ならば真偽を確認しようがないと踏んだからだ。
警察は探偵事務所のZ社にも問い合わせた。同社は「わが社は中村なる人物から調査の依頼を受けたこともなければ、そんな報告書を作った覚えもない」と、木で鼻をくくったような返答をした。これもまた、中村が持っているとすればZ社の作成した書類のコピーでしかなく、それが本物だと証明する術が彼にないことを見越した上での対応だった。
むろん、警察は青山本人にも問い合わせた。
「脅迫状が来ましたか?」
「はあ? 脅迫状? いったい、なんの話ですか?」
警察は「そちらの社員の中村氏が言うには…」と必死で説明するのだが、青山は途中で笑い出して、呆れた風にこう言った。
「中村はたしかに私の秘書をしていますが、最近、言動がおかしいので、解雇しようかと思っていたところです。彼はどうも幻覚を見ているようなので、警察のほうでちょっと調べてもらったほうがいいかもしれませんねえ…」
捜査の結果、警察は中村の言ったことが全部デタラメだと知り、憤慨した。
◇
事件の後、青年社長が一転して社内で笑みを振りまいたため、会社の雰囲気が明るくなったことは言うまでもない。
その後、青山の「ワーカーズドア」は東証二部への上場を果たした。
彼の会社は優良ベンチャー企業として、投資家の注目度も抜群で、若き経営者は一気に数百億円もの資産を手にした。
「しかし…」と青山は考えた。
今回、自分は秘書の裏切りにあった。いつもの彼だったら、相手を恨んでいたところだが、今回は己の不手際のように思えて、そういう気分になれなかった。
自分は一番身近にいる部下の人心すらも掌握できなかったのだ。
これは自らの不徳の致すところであり、組織のリーダーとしてどこか欠点を有していることを意味するのではないだろうか。
他人を批判する前に今一度、己自身を省みろ、と彼は己を叱咤した。
今回の出来事を通じて改めて痛感したことは、本来なら自分は犯罪者として逮捕されてもおかしくはない身だということだった。だが、裁きを受けて当然のところを、天から特別にお目こぼしに預かったうえ、あまつさえ事業の成功と充実した人生、そして巨万の富という報酬までいただいた。まったく身に余る光栄ではないか!
自分は過去、薬物を社会に広めることに加担してしまった。その結果、大勢の中毒患者が生まれ、たくさんの家庭が破壊されたに違いない。
社会に害毒を撒き散らした責任は重い。今さらだが、それを実感する。
この罪は一生をかけて償っていくしかない。仮に別荘でパーティー三昧の暮らしをしていては、いつか自分は天罰を受けるだろう。
青山勇は今回の事件を「教訓」であり、また天からの「警告」と受け取った。
幸い、よき妻の助言がヒントとなり、彼は慈善事業に乗り出すことを決意した。
会社の上場からしばらくして、彼は私財の一部を投じ、薬物依存症の患者やその家族を支援するための財団法人を設立した。
財団は都内に事務所を構えた。そして、長野県の諏訪にリゾートホテル顔負けの本格的な更正施設をオープンさせた。
この施設は基本的には民間からの寄付と基金の運用収益によって運営されるが、足りない分は青山がこれからも私財を投じていくつもりだった。
この構想は、もともとは己の犯罪が世間に明るみになった場合に備えたセイフティネットだった。慈善事業をしていれば世間の見る目も違うだろうという算段だ。
世間は「青山は過去を悔い、改心しているからこそ薬物中毒者の更正施設を建てたのだ」と考えてくれるはずだ……そんな計算高い思惑から始めた構想だった。
ところが、いざ建設に着手してみると、青山は心の底から慈善事業の成功を望んでいる自分を発見した。たしかに、マスコミも彼の行為を褒め称え、真の成功者だともてはやした。彼の名声はますます高まった。
だが、それ以上に、彼は内的な喜びを感じていた。思えば、ついこの間までは、己の犯罪が発覚するのではないかと怯え、恐怖と不安に苛まれる毎日だった。だが、その暗いトンネルの先にあったのは、むしろ幸福だったのだ。
「これも神の計らいか」青山はそう思った。
花壇に彩られた厚生施設の除幕式には、多数のマスコミも駆けつけた。
青山勇は参列者を前に演説をした。
会場の前列には妻の美香子もいた。彼女がこれほど幸せそうに微笑んでいる姿を見るのは久しぶりだった。
招待客として李夫妻の顔も見えた。彼らも寄付者に名を連ねていた。
青山はマイクに向かって力強く叫んだ。
「…企業はただお金を儲ければいいというものではなく、その儲けを積極的に社会貢献に回さねばなりません。それが真の成功というものではないでしょうか」
参列者たちが総立ちとなり、会場は割れんばかりの拍手に包まれた。
(了)







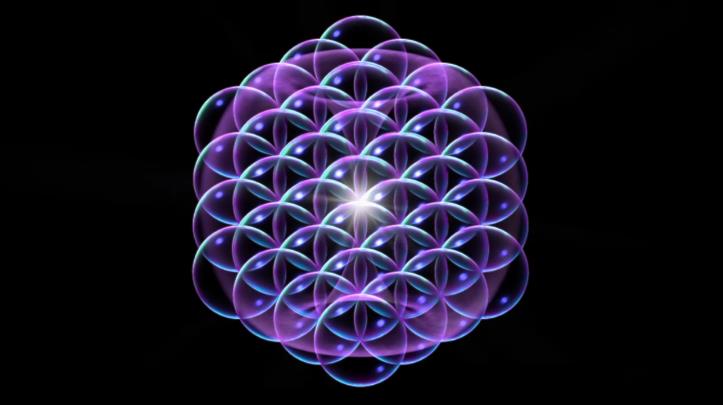




スポンサーリンク