みなさん、こんにちは。
これは私が以前に書いたミステリー&サスペンス短編です。
残念ながら、当「フリー座」では、文化系記事の人気は低い。
その人気のない文化系カテゴリーにあって、私の小説はさらに人気が低い(笑)。
しかし、読んでみれば、それが食わず嫌いであることが分かると思います。
ただし、どんな小説でも、面白くなってくるまで、ある程度のページ数まで進む必要があります。それまでは一定の忍耐が必要です。
この短編も、途中で投げずに三分の一くらいまで読めば、きっと面白くなってくると思います。春の夜長に、暇潰しにもってこいです。
脅迫者の報酬(前編)
青山勇(あおやまゆう)は若き成功者である。
二十代半ばのとき、数千万円の資金を元手に「ワーカーズドア」を設立し、人材派遣業をスタートさせた。この業種を起業の対象として選んだのは、事務所と電話さえあればすぐにでも営業が始められる手軽さゆえである。要はピンハネ商売なのだ。
折しも、バブル経済崩壊後のときである。企業は経費削減の手段として正社員に代わりパート・アルバイトを積極的に登用し始めていた。
青山がつくった会社は、期間労働者やスポット派遣と呼ばれる短期の労働者の派遣を収益の柱に置いたので、たちまち売り上げが伸びていった。会社は軌道にのり、青山は自分が実業家として幸運なスタートを切ったことに一応の満足をえた。
もっとも、起業時の興奮が冷めるのに反比例して、ある気持ちが次第に強まっていくことも否めなかった。「思ったほど儲からない」という失望である。
たしかに、期間に応じて労働者をよこしてくれという企業はいくらでもあった。人材派遣業者はそういった企業側からの注文に応じて、とにかく人を集めなければならない。その人集めの力量こそが、その業者としての能力でもある。
だが、ここで中小派遣業者としてのハンデを必然的に負った。いわゆるフリーターたちの間で会社のネームヴァリューが低いため、経費に占める人集めの宣伝費の割合が大手に比べると必然的に高くなってしまうのだ。
では儲けを大きくするためにピンハネ率を上げればいいのかというと、事はそう単純ではない。なぜなら、労働者側の取り分を少なくすれば、今度はますます人が集まりにくくなるからだ。この辺りのジレンマは、この業種が常に抱えるものである。
ゆえに、青山の「ワーカーズドア」のような中小業者は、ピンハネ率を最大限に上げても業界大手の水準を追随するのがやっとであり、通常はむしろそれより下げ気味にしなければならないくらいだった。
やがて、彼の不満の矛先は、切っても切れない関係にある求人広告誌の掲載料へと向き始めた。誌面上の、花札一枚分くらいのスペースの値段が、なんと五万円もする。それで最低価格なのである。人材派遣業者として、人集めのためには広告を多数、打ちつづけなければならない。この掲載料が常に大きな負担となり、経営を圧迫していた。
しかも、雑誌の印刷流通の関係で、掲載は申し込んでから二週間も後ときている。
高すぎると思った。また、遅すぎると思った。
青山はそれがいつも不満であった。
都市部の書店やコンビニ、キオスクなどにことごとく配本されるような求人広告誌を取り扱っているのは、ほんの数社の企業だけだった。いわば寡占状態である。しかも、広告料も暗黙のカルテルを結んだ状態にあるらしいと想像がついた。
青山は考えた末、一念発起した。
「よし、それならば自分でやろう」と
実は、彼にそう決意させたのが、1990年代後半における、ある新しいメディアの勃興であり、その急速な普及だった。インターネットである。
青山の「ワーカーズドア」は、それまでの儲けをすべて吐き出して、自前でサーバーを購入し、ネット上に求人広告サイトを運営する新規事業を立ち上げた。
勝算はあった。広告掲載料は雑誌よりはるかに安価であり、しかも申し込みの即日に掲載される。あらゆる点で雑誌媒体より優れている。
彼はサイトが連日、賑わう様を想像し、己の先見の明を誇った。
ところが、いざ新事業を初めてみると、期待はものの見事に裏切られた。
原因はユーザーの閲覧数の少なさである。わずかな訪問者しかいないネットサイトに、お金を支払ってまで広告を掲載しようと思う企業はなかった。
むろん、青山の会社は必死で営業に回り、広告主を獲得した。だが、反響がないため、その顧客もそれっきりで掲載を打ち切ってしまう。
なにはともあれサイトへの訪問者数を増やさねばならないと思った青山は、宣伝に資金を投じた。しかし、求職者が興味をもってサイトにアクセスしても、求人広告の数があまりに少ないため、実用に耐えないと考えるらしく、二度と訪れようとしない。しばらくすると元の閑散とした状態に戻ってしまう。そこで再び宣伝費を投じるものの、やはり一時的に閲覧数を増やす効果しかなく、結局、また元の状態へと戻ってしまう・・。
青山の新規事業は、この悪循環の堂々巡りに陥った。
やがて資金が底をつき始めた。追い討ちをかけるように、銀行からも融資を断られた。
青山は断崖絶壁へと追い詰められた。インターネットの利用者は増えているのに、自分たちのサイトの利用者は一向に増えない。宣伝費にいくら金をかけても一時的なカンフル剤にしかならず、投資効果が低い。
なぜだ、どうすればいいと、悩む日々が続いた。いくら考えても答えは出なかった。日に日に会社の金は蒸発していく。焦れば焦るほど空回りしてしまうのだった。
だが、倒産寸前にまで来た時、ようやく、ふいに発想の転換が訪れた。
要は、閲覧数を増やせばいいのである。ならば、求人広告一本にこだわらなくてもよいではないか。極端な話、それは「オマケ」でもいいではないか……。
青山は自社のサイトに、楽しい情報をふんだんに盛り込むことにした。最新の映画の話題から、レストランなどのグルメ情報、芸能、スポーツ、タレントのコラムまで。
それこそ求人とは何の関係もないが、ただしフリーター層が好むであろう情報を幅広く取り扱い始めた。ニュースや路線、地図情報を提供する業者とも連携した。
青山はこの方針に賭けた。
やがて、閲覧数が少しずつ伸び始めた。それにつれ、求人広告の掲載を希望する企業の数も次第に増え始めた。それがまた求人広告の閲覧それ自体を目当てとする求職者をも引きつけ始めた。そして、その現象がまた広告主を増やす効果をもたらした。
ついに「上昇のスパイラル」が始まった。
会社の業績は一転して上がり始めた。増収増益が続いた。気が付けば、彼はそれまで大手の寡占状態にあった求人情報市場の一角に食い込んでいた。
青山の快進撃は留まるところを知らなかった。
携帯電話からもサイトの閲覧を可能にした。さらに、賃貸住宅情報や中古車情報、はては個人売買の仲介にまでビジネスの枝を伸ばしていった。
青山勇が三十五歳の誕生日に元女優を妻に迎えたときには、「ワーカーズドア」の年間売上高は二百億円をこえ、純利益も数十億円をたたき出すまでになっていた。
仕事とプライベートの両面で順風満帆だった。今では同業者が乱立したために売り上げの伸び率はやや頭打ちだが、それでも十分に先行者利益を享受していた。
求人サイトの運営企業として屈指の存在となった青山の会社は、著名な六本木の高層ビルに本社を構えた。ゆくゆくは自社ビルを建てる目算だ。「勝ち組」「成功者」としての彼の名声も広がり、上場を勧める証券関係者の日参も相次いでいた。
青山はベンチャー向けの新興証券市場を跳び越し、一気に東証二部への上場を予定していた。実は、上場が遅すぎたくらいである。というのも、広告ビジネスはキャッシュフローが豊富に転がり込む。つまり、手元の自己資金が常に豊富である。たしかにサーバーを維持管理する必要はあるが、雑誌の発行費に比べれば安かった。
だから、彼の会社は他者の資金をあまり必要としなかった。実際、無借金経営にしようと思えば、できた。それをあえてしないのは、法人税の節税が関係しているからに他ならない。だから、会社としては必ずしも上場を必要としなかった。
だが、彼個人にそうではない事情が生じた。
それは青山が「大富豪」としての生活を望むようになったことである。
若き成功者は今や、都心に数百坪もの豪邸を建て、避暑地に大掛かりな別荘を有したいと考えていた。そこで著名人を呼んでパーティーを催し、数十億円ものプライベートジェットや大型クルーザーを乗り回すといった、より派手な暮らしを渇望していた。
青山は世間に自分が成功者であることをもっとアピールしたかった。その夢を手に入れるためには、個人的な巨額の上場益が欠かせない。それがこの度「ワーカーズドア」の上場を決意した理由であった。そして、その夢は、手の届くところにあった。
「だが…」と、青山は思った。
彼は一枚の手紙を手にとった。
「代表取締役 青山勇様」宛てだ。送り主は「匿名希望」とあり不明。
局印を見るに、何者かが池袋のポストから投函したらしい。中には、A4サイズの無地の紙が一枚入っており、大きめの油性ペンの字でこう記されていた。
「オマエノ過去ノ秘密ヲ知ッテイルゾ」
手紙の宛先同様、字は角がとがり、意図して筆跡をごまかしているのが見て取れる。
今までもおかしな手紙はあった。「政治団体」からの寄付の要請、「NPO法人」からの慈善事業へのお誘いといった、強請りやたかりの数々。その他、殺すとか、会社を爆破するなどといった脅迫の類い…。成功者につきものの代償であろう。
だが、このような内容の手紙は初めてだった。明らかにそれまでとは異質だった。
次第に不安が募った。まるでどす黒い染みが広がるように。
いったい「過去の秘密」とは何のことなのか? 送り主は誰だろうか? そして目的は何なのだろうか…と。
手紙の文面が、脳裏でいつまでも木霊し続けた。
考えるにつれ、疑念はますます膨れ上がっていく。掌にじっとりと汗が滲んできた。
「もしや、あのことが…」
青山は息を呑んだ。
“それ”が表ざたになることは、彼の破滅を意味していた。
◇
青山勇はひとり苦悩していた。事が事だけに、唯一の理解者である妻にも、会社の顧問弁護士にも相談できずにいた。
不安を覚えつつも無視を決め込んでいると、しばらくして、前回と同じ人物と思われる者から、第二の手紙が送られてきた。
「二十代ノ前半ニ何ガアッタカ、知ッテイルゾ」
文面に目を通した瞬間、胸にナイフを突き立てられた気になった。頭が真っ白になり、次の瞬間には身体が震えだした。
どうやら間違いない。送り主は「あのこと」を知っている人物らしい…。
だとすれば、その対象はある程度、絞られる。
それにしても、いったい何が目的だろうかと思った。事業の成功者を脅迫し、大金を強請りとろうという魂胆に間違いないと思うが、詳しくは今後の出方を待つほかない。
考えてみれば、今度のことは、成功への階段を踏み出して以来、なんとなく心の底で不安に思ってきたことであった。いつかこんな時がくるのではないかと内心、恐れていたのだ。それがついに現実となって、目の前にやって来たということだ。
その日、青山勇は代表席に座り、秘書の中村茂から今日のスケジュールの説明を受けていた。そこは一般社員の席とはパーティションで仕切られているだけだ。フロアには「社長執務室」と銘打った個室もあるが、社員とのコミュニケーションの関係上、あまり使用しない。本日、通常の仕事のほかに、財界や官界からの客人が数組ほどあるらしいが、意識が時々あらぬ方向へと飛んでしまうせいか、どうも説明が頭に入ってこない。
「社長、なにか心配事でもあるのですか?」
二十代後半の若者は眉間に皺を寄せていた。
「あ、いや…」青山はハッと我にかえった。「別に、なんにもないが…」
青山は内心ではこの青年をあまり買っていなかった。というのも、当初は、その卑屈ともいえる臣従ぶりが気に入って秘書に就けたものの、最近では今ひとつ仕事に身が入っていないというか、妙に機械的・惰性的になりつつあるからだ。
秘書の主な仕事は、社長のスケジュール管理と社内外の連絡役、対外折衝などである。中村は、一応は彼の手足となって動き、それを無難なくこなすものの、今ではなぜか以前ほどのサービス精神や気配りは見られなくなっていた。
だから機会をみて秘書を別の有能な社員に挿げ替え、中村を社内の適当な部署に追いやろうかと考えていた矢先だった。実際、上場企業になればさらに露出の機会も多くなるし、広報の意味でも若い女性を秘書にしたほうがいいだろうと思っていた。
「私にご相談ください。社長のためでしたら、ご尽力いたします」
ほう、と青山は思った。たしかに、こちらの顔色をうかがう中村の目には、雇用主を救おうという熱意なのか、妙に爛々とした輝きが満ちている。
この男も捨てたものではないと、少しは見直したが、かといって今度の心配事は、こんな若輩者に解決を託せる筋のものでもなかった。
「いや、結構。ありがとう」
一瞬、中村は失望をあらわにした。青山は机の書類に視線を移した。それは秘書に対して「もう用事はないから行ってよい」というジェスチャーでもあった。
中村が一礼して去った、その時だった。
ふいにある考えが脳裏に閃いた。
「ああ、待て、待て」青山は彼を背後から呼び止めた。「ひとつ頼みがあるんだ…」
◇
社長の話を聴きはじめて、中村茂は内心、「ほらほらきたぞ」とほくそえんだ。
中村が青山に揺さぶりをかけることを決意したのは、最近のことである。
その理由は、自分がストックオプションの対象からもれたことだった。
予定されている株式上場に伴い、社長の青山が全社員に提示したストックオプションの条件は「二〇〇X年のX月までに入社した者に限る」というものだった。
その年までの入社組ならば、創業または創業時のメンバーに比較的近い、会社躍進の功労者と見なして、会社の株を譲り別ける、というのである。
当然、その後から入社した者は、漏れることになる。
まさに中村がそうだった。仮にその条件から程遠ければ、諦めもつこう。だが、不運なことに、彼の入社日はその条件からわずか数ヶ月遅れているだけだった。
たったそれだけのことで、彼は上場益にあずかれなくなってしまったのである。
中村はこれが許せなかった。仮に他人も平等に上場益にあずかれないとすれば問題はない。しかし、他人が恩恵を受けて、自分が受けられないことが彼にとって問題なのだ。
それまでも中村は、若くして成功した社長の何気ない言動や振る舞いに屈辱を覚えてきた。実際、青山はときに人を人とも思わぬ傲慢な態度をとることがあった。
彼は昔からこうだったわけではない。人が変わったのは、成功に伴う負の副産物だった。そんな社長の下で傷つき、耐えながらも、中村は彼なりに必死で努力し、会社のため、また社長個人のために身体を張ってきたつもりだった。気に入られるために奴隷的忠実さで仕え、卑屈かつ臣従的な姿勢を己に強いることも厭わなかった。その過程で生じた憤り・不満・屈辱などのマイナスの感情は、すべて意識下に封じ込めてきた。
だが、その身を切るような犠牲に対して、若き成功者は報いようとしなかった。
中村は憤激した。「裏切られた」と感じた。
一転して、それまでの反動がやって来た。意識下に抑圧し、鬱積していた、何か黒々とした邪悪なものが、一挙に表面に噴出してきた。
(そっちがその気ならばこっちだって…)
彼自身は認めたくなかったが、そこには成功者に対する激しい嫉妬や羨望、そして劣等感も渦巻いていた。社を率いる男を間近で見ていて彼が常々感じていた、「おれはこの男には敵わない」という敗北感は、完全に敵意へと変化を遂げた。中村の傷ついた自尊心は、よもや目の前の男が苦しんだ末に破滅することによってしか修復を果たせなかった。
結局、ありとあらゆる負の感情が心のフラスコの中で複雑に混ざり合い、化学変化して生成されたのは、何のことはない、純粋な憎悪の結晶だった。
そして今や中村は、その結晶ストーンから生じる憎悪のパワーによって動かされていた。
実は今回、脅迫状の送付にあたってヒントとなったのが、一年ほど前に青山に対して行われたマスコミの取材だった。
当時、ある雑誌から「ワーカーズドアの社長にインタビューをしたい」という申し入れがあり、中村がそれをアレンジした。社の応接室で行われたそれは「若き成功者の秘密を探る」というありきたりな題名にふさわしく、「初期の逆境や失敗をこうして乗り越え…」等の陳腐なやり取りだったのだが、独創性のない記者の質問にあくびをもらしそうになったそのとき、ふと彼の注意を引き付ける場面が訪れたのだ。
それが、青山がビジネスを始める際の運転資金、すなわち「種銭」について、記者が何気なく質問を投げかけたときだった。
「若いのによく小さくない資金が貯まりましたね。何か秘密でも?」
なぜか青山は一瞬、青くなった。
そして次の瞬間には笑ってごまかし、もちろん必死で働いただけですよ、眠い目をこすりながらね、ハハハハと笑って、うまくはぐらかしてしまった。
やり手社長が今まで人前で見せたことのない、奇妙な表情であり、態度だった。
そばで見ていた中村は、それを見逃さなかった。そして「何かある」と直感した。
考えてみれば、青山勇という人物には謎の一時期があった。すでに公に喧伝された彼の立志伝は、次のようなものだった。
神奈川県平塚市の貧しい小売店の家に生まれる。地元の高校を卒業後、新聞奨学生として苦学し、千葉のT私大に進学するものの、二年で中退。以後、アルバイト三昧の暮らしを送りながら資金をコツコツと溜め、二十六歳の時に一念発起して起業した…。
問題は、大学を去った二十歳から起業までの六、七年間である。この時期の彼を知る者は少ない。いわゆるフリーターとして、将来への夢と不安の狭間で漂うがごとく、首都圏各地を転々としていたという。孤独で、謎に包まれたこの人生の漂流期に、彼が本当は何者で具体的に何をしていたのか、会社の人間で知るものは誰もいない。
貧しい若者が本当に自分だけの力で、あるいは百%完全に合法的な手段で、数千万円もの資金を用意することができたのだろうか。
このマスコミの取材をきっかけに、中村は心のどこかでそれが引っかかっていた。若き成功者は、何か世間に知られたくないことを隠しているのではないかと疑ってきた。
そう思っていたところに、今度のこの「仕打ち」を受けたわけである。
中村は、かつてある男が、まったく面識のない医者や美容外科医たちに対して、片っ端から証拠もないのに「脱税の証拠を握っているぞ」という脅迫文を送り付け、多額の金を騙し取ることに成功した事件を思い起こした。
無差別に送ったにしては、意外にも振込み率が高かったという。見知らぬ人物に弱みを握られたと錯覚した人間の心理というのは、案外そんなものかもしれない。
この事例を参考にして、中村は青山を陥れることにした。
なにしろ憎むべき相手である。恵まれすぎた男から少しくらい掠め取るくらい、どうということはない。開き直りというか、自己正当化の思いが強かった。罪悪感も躊躇もなかった。思わせぶりな手紙を書いて、青年実業家の反応を探ることにした。
むろん、青山がすぐに警察に相談するようであれば、この危険なゲームは直ちに中止せねばなるまい。だが、仮にそれが警察にも知られたくない過去だとすれば、相談はしないはずだ。今回の脅迫状送付は、それを判別する試金石の意味あいもあった。
そうしたら、ドンピシャリだった。
社長は一通目に関しては無視を決め込んでいたが、それでも様子がどことなく変なのが傍で見て取れた。「おや?」と思い、思い切って二通目を送ってみた。
すると、この反応である。どうやら「カマかけ」は成功を収めたらしい。
やはり青年社長は「何か」の過去を隠しているのだ。
勝負はこれからだぞ、と中村は脅迫者としての闘志を燃やした。
◇
「…というわけで、会社の名前も私も名前も一切、表に出したくないのだ。だから、あくまで君個人が調査しているということにしてくれないか?」
「分かりました」
中村は青年社長に向かって頷いた。
「うむ、助かる」青山は珍しく秘書に対して軽く頭を下げた。
社長が言うには、要は青山が「中村茂」の名前でしたためた依頼書を、中村が開封することなく探偵会社にそのまま渡してほしい、ということである。
そして、先方からの報告書もまた同様にして、青山に届けなければならない。
つまり、中村はただ名義を貸すだけなのだ。
もっとも、中村は内心で「開封するなと言われれば開封したくなるのが人情というものよ」などとぺろりと舌を出していた。
数日後、青山からその文書の入った封筒の現物を手渡された。
「なるほど、敵もさるものだ」中村は思わず唸った。
いったいどこから用意してきたのか、それは特殊な色の封筒だった。青みを帯びた銀色とでもいおうか。市販のものとしては見たことがない。当然、厳封されている。
青山と探偵事務所の間でこの封筒の情報が共有されていれば、中村が別のものにすりかえることはできない。それは中身を開封できないことを意味する。
中村は指定された新宿の探偵事務所の門を叩く前に、大きな文房具店に入って商品棚を覗いた。だが、同じものは見当たらなかった。また、店主に実物を見せて尋ねても「こんな封筒は見たことがない」と言って首をかしげるばかりだ。
開封したくとも代替品が用意できないので、中村は困り果てた。文書には日付が入っているであろうから、手渡されたその日のうちに指定されたZ探偵事務所に持ち込まなくてはならない。そうこうしているうちに時間切れとなり、依頼書の中身を盗み見てやろうという彼の目論見は脆くも崩れ去った。
中村はやむなく新宿のZ社に向かった。Z社は業界でも屈指の調査力で評判だ。
事前に指示された通り、中村は封筒と巨額のキャッシュを相手側に手渡した。そして、一応、依頼者は彼という建前なので、「中村茂」の名で契約書にサインした。
Z社の玄関を出たとき、中村はひどく腹を立てていた。
彼はとうとう依頼の内容を知ることができなかった。社長の青山は、個人的なことは一切秘密で通すつもりだ。やはり、秘書といえども、彼はまるで信用されていないのだ。
実際に脅迫状を送ったのが自分であることも忘れて、そのことが癪に触って仕方がなかった。そして、それが彼をしてますます加虐的な心理へと追いやった。
「ようし、そうまでおれを信用しないなら、もっといたぶってやるぞ」
◇
その日、青山勇は仕事を終えると、まっすぐ帰宅した。自宅は赤坂のタワーマンションの最上階にある部屋だ。百五十平米ほどで二億円もした物件である。
「お帰りなさい、あなた」
九時を回っていたが、妻の美香子が夕食を作って待っていた。
二年前に結婚した美香子は、夫の目から見ても美しかった。かつては青山もプレイボーイ気取りで多数の女性と浮名を流したものだが、結婚してからは彼女一筋だった。
美香子は元女優だ。もっとも、一流ではなかった。グラビア界でも映画界でも、結局は泣かず飛ばずで終わった。ただ、青山が気に入ったのはまさにその点だった。
青山が付き合った女性の中には、芸能界で成功を収めていた女優もいないわけではなかった。だが、映画にドラマ、CM出演等で忙しい毎日を送っていれば、必然的に家庭がおろそかになる。とくに問題になるのは子育てだ。相手が売れっ子女優の場合、本業から足を洗ってもらわなくては、家庭を切り盛りすることは難しいと青山は考えた。その点、売れっ子になれずじまいの美香子はちょうどよかったのである。
青山の考えが正しかったことは、一緒に暮らしてみて、すぐに証明された。
美香子は料理が得意で、インテリアと園芸の趣味に秀でていた。彼女は無機質な高級マンションの一室をうまくコーディネイトし、たちまちくつろげる空間へと作り変えた。
今では彼女の存在こそが、ホッと安らげる一番の理由だった。なんだかんだといって、男にとってはこれが一番、家庭に求めることだった。
そのことに気づいた時、青山は美香子を選んで本当によかったと思った。
世間一般では、大物実業家たる者、愛人のひとりやふたりを作って当然だし、逆にそうでなくては器量不足と見なす風潮すらあるらしいが、今の青山にとって妻以外の女性と関係を持つということは、まったく想像すらできないことであった。
夕食中もふたりの会話は弾んだ。
「もうすぐ上場するからな」
「まあ、またその話?」美香子が呆れて笑った。「もう何十回聞いたかしら。今でもお金が使い切れなくて困っているのに、どうしたらいいか分からないわ、あたし」
このところ夫の口癖になっているのは、数百億円の創業者利益が手に入るので一躍、富豪の仲間入りができるぞという夢物語だった。
「おまえがもっと贅沢すればいいじゃないか。どんどん使っていいって、いつも言っているだろう」
「でも…」
美香子は嬉しいのか困ったのか分からない表情をしていた。
彼女は見た目が華やかなせいか、一見、派手好きに見えた。だが、人は見かけによらない。中身は全然、違っていた。夫と同様、裕福でない家庭で育ったが、夫と違うのは彼女の経済感覚がいつまで経っても庶民のままだということだった。青山と知り合う以前は、スーパーマーケットのチラシを睨んで特売品を探す毎日だったという。彼女にとって、高級洋菓子店で一個千円もするそれを買うことは、未だに決断を要する出来事らしかった。
「一億円のダイヤの指輪を買ってもいいんだぞ」
「関節炎になるわ」
「自宅だって、こんな狭いマンションじゃなく、渋谷の松濤辺りの一軒家にするか。別荘はどのあたりがいい?」
「そうねえ…軽井沢かしら? よく分からないわ、あたしには」
「ありきたりだな。沖縄のどこか、プライベートビーチのあるところにしよう。そこに橋桁を作ってクルーザーを横付けするんだ。近いうちに船舶免許もとるよ」
「まあ、夢があってよろしいこと」
「ああ、ずっと夢に見てたよ。アジアに事業を拡大すれば、プライベートジェットも買うぞ。それで世界中を行き来するんだ。成田とか羽田のあの混雑は、もう真っ平だ」
「フフフ…」美香子が笑った。目を伏せて言う。「私は今のままでも十分に幸せだわ」
「相変わらず無欲なやつだなあ」
いつものことだが、妻は富豪としての暮らしにそれほど執着する風ではない。
「ねえ、あなた」美香子が目を上げた。瞳にちょっと真剣な色が混じっている。
「なんだい?」
「上場益が入ったら、少しどこかに寄付するっていうのはどう?」
「寄付だって?」
「そう。そうすれば、もっと社会の役に立てると思うわ」
「あのなあ…」勇はちょっとむくれて見せた。「今でも十分、社会の役に立っているじゃないか。情報産業の一翼を担い、職を探す人と人を探す企業との間を取り持って…」
言っている最中から、企業広告みたいなセリフの陳腐さに自分で萎えていた。
そして、本当に自慢できるほど、おれは世の中の役に立っているのだろうかと、内心で首をかしげた。
◇
二週間ほど経った頃だった。中村はZ社から呼び出しを受けた。
その間、中村は、前回の脅迫状の文面を少し変えて、「二十代ノ前半ニ何ヲシタカ、知ッテイルゾ」という字句の三通目を社長に送りつけていた。
「中村様のご依頼の件ですが…」Z社の担当者は、やはり厳封されたA四サイズの水色の封筒を差し出した。「ご希望通りにして、こちらに収めておりますので」
と言われても、中村は「はあ」と曖昧に返事するしかない。社長の指示で、中村は受け取ったこの報告書をそのまま彼に渡さなければならないのだ。
今度は社名入りの封筒である。あくまで中村が開封できない仕掛けなのだ。
昼食に立ち寄ったファミリーレストランの席で、この封筒を前にした中村は、「はて、どうしたものか」と腕を組んで考え込んだ。
中村はとりあえず、太陽の光に透かしてみたり、理化学教材店で買ったアルコールで拭いたりして、中身を覗こうとした。しかし、中身の字句の判別は不可能だった。
だが、ある閃きをえた中村は、さっそく行動を開始した。
彼はこの社名入り封筒を印刷した印刷会社を探すことにしたのだ。
ただし、報告書には日付が入っているだろうから、あまり提出が遅いと青山に疑われる。焦った。脚が棒になり、途中で何度も諦めようかと思った。
だが、夜の帳が下りた頃に、ようやく目的の印刷所を探し当てることができた。
急きょZ社の社員に偽装した中村は、「ちょっと緊急に必要になった」と言い、社名入り封筒を百枚ほど刷ってほしいと頼んだ。むろん、支払いはキャッシュであり、「請求書はよこさなくていい」とも言った。印刷所の所長は少し不思議そうにしたものの、商売になれば何でもよいのであろう、気前よくその場で封筒を刷ってよこした。
中村はZ社から受け取った封筒を破いて報告書を取り出した。とりあえずコピーした。なぜか、依頼書が入れてあった青みを帯びた銀色の封筒――当然、開封済みで、Z社の押印もある――も一緒に同封されていた。理由は報告書を読めば分かるだろう。
中村は、自前で調達した社名入りの封筒の一枚にそれらを入れ直して厳封し、待ちかねている社長の青山のもとへ、うやうやしく提出した。
◇
中村は報告書のコピーを自宅に持ち帰るなり、さっそく目を通すことにした。
報告書のあて先は「中村茂様」となっている。読み始めて、彼は青くなった。
まず、型どおりの挨拶文が終わると、次の一文が目に飛び込んできた。
「依頼書の入った封筒が厳封でない場合は依頼が無効であること、又その封筒に弊社の社印を押して一緒に送り返してほしいとのお客様のご要望等につきましては、了解する旨…」
危ない、危ない、と中村は冷や汗を垂らした。
仮に中村が依頼書の封筒を開封したままZ社に渡せば、探偵事務所はその依頼を無効と見なして動かない。また、封筒を別の物にすりかえれば、たとえ厳封したとしても、封筒の現物が送り返されることから、その事実がたちどころに青山に分かってしまう。
どうやら、社長の青山は、徹底して秘書を信用していないらしい。
おそらく、探偵のZ社も、事務所を直接訪問した中村なる人物が、真の依頼者とZ社との間の緩衝材に過ぎないということは、とうに承知しているだろう。そして、このような取り決めを奇妙に思いつつも、一応は客の頼みであるから遵守するだろう。
中村は社長がこのような予防策を張っていることを腹立たしく思ったが、一方で開封しなくてよかったと、心から胸を撫で下ろした。
とりあえず、これからも社長が記した依頼書のほうは読まなくていい。調査サイドの報告書を熟読することで、ある程度の推測をするしかない。
さて、肝心の報告書の中身であるが、それはある人物たちについての記述だった。
「李文烈(イムンヨル)は二〇一×年現在、六×歳。東京都台東区東上野××番の土地を所有し、妻の朴秀美(パクスミ)とともに当地で地元客相手のキムチ屋を営んでいる。
店の売り物は、主力商品が自家製のキムチとカクテキであり、その他、韓国製の焼酎や香辛料、乾物なども扱っている。キムチは在日韓国人だけでなく、近隣の日本人にも評判であり、年間の売上高は数千万円に達する。
現在では融資も完済しており、いかなる借金もなく、経済状態は裕福なクラスに属する。店舗は二・三階が自宅を兼ね、裏が漬物工場になっており、もっぱら数名のアルバイトに指示して作らせている。
家族構成は長男と次男がともに亡くなっているため、夫婦ふたりきりである。そのせいか、ふたりとも子供好きで、同胞苦学生の奨学金や交通遺児基金などに寄付をしている。
李文烈は真面目な性格として知られ、趣味と呼べるものは散歩以外にほとんどないが、ようやく近年になって、妻の誘いで日韓の国内旅行をよくするようになった。酒は少したしなむ程度で、ギャンブルには一切手をつけず、女関係の噂は昔からまったくない。
妻の朴秀美も夫に忠実で真面目な女であり、働き者として知られるが、長男の病死にひどくショックを受け、そのせいで次男を溺愛し、結果的に誤れる道を歩ませてしまった(後述)ことを今でも悔いている模様である。現在は温泉地巡りを愉しみとしている。
李文烈は一九四〇年、済州島で生まれた。二十六歳のときに朴正熙政権下の韓国に見切りをつけ、親類を頼って日本に密入国。荒川区東日暮里にある親類の家に居候しつつ、金属リサイクル業に従事する。その後、同地区にあるアパートに移り、飲食店やパチンコ店の従業員、トラック運転手など職を転々とする。
飲食店時代に同じ済州島出身の朴秀美と知り合い、六八年に結婚。その年に生まれた長男の允植(ユンシク)は、三歳のときに風邪をこじらせたのが原因で病死。
その後、一念発起して、民族系の信用組合の融資をうけ、現在の住所である東京都台東区東上野××番の土地を買い取り、キムチ店を開業する。だが、当初は事業がなかなか軌道にのらず、その後、何度も倒産の瀬戸際に追い詰められる。李自身はその原因について、自分が済州島出身者で、しかも新参の密航者であったため、長らく在日社会から白眼視されたためと周囲に漏らしていた模様。もっとも、今では事業も順調で、すっかり地元の顔・古参者であり、商工会活動などにも参画している。
次男の永吉(ヨンギル)は六九年に生まれた。永吉は在日韓国人として地元の小中学校に通い、日本人の子弟と一緒に机を並べた。早くから悪童として頭角を現し、中学時代には完全に不良仲間の一員としてケンカや器物破損、窃盗などをくり返し、度々、警察の厄介にもなっている。
少年時代がちょうど店の経営が苦しかった時期と重なっていたため、永吉は割りを食った。実家の経済的貧窮だけでなく、同胞からもキムチ屋をからかわれたことがトラウマとなり、店を絶対に継がないと宣言して父親と対立。中学を卒業後、いったんは金属加工会社に工員として就職するが、しばらくして退職し、以後、建設現場やパチンコ店などで職をえるものの、いずれも長続きしていない。そのうち、店を手伝いながら不良仲間と戯れる日々を送り始め、実家を飛び出したり、戻ったりをくり返した。
李永吉の転機は、十七歳のときに訪れた。仲間から誘われたのがきっかけで、関東の広域暴力団として有名なS会の二次団体六田組に出入りするようになり、結局、そのまま組員となった。
台東区に拠点をおき、構成員・準構成員あわせて百名ほどの六田組の中で、永吉は次第に頭角を現しはじめた。とくに組の重要な資金源を担ったことで、二十代半ばにして幹部になり、フロント企業の社長にも就任した。
彼は「ヨンギル」ではなく日本風の「エイキチ」で通っていた模様。暴行傷害などの容疑で数回、警察に逮捕・起訴されているが、いずれも懲役自体は免れている。
一九九九年、ホテルの一室で、覚せい剤の打ちすぎが原因と思われるショック死を起こす。享年三十。ちなみにその数年後、大量の覚せい剤密輸の嫌疑で、六田組は警察の一斉摘発をうけ、幹部が多数逮捕された。現在は組長が病死・不在で、組員の脱退が相次ぎ、活動はほとんど休眠状態になっている…」
中村茂は、一読して、この内容をいったいどう受け取ればいいのか、しばらく考えあぐねた。要は、キムチ屋の老夫婦とその亡くなった息子についてのレポートである。
どうやら青山は、この連中が彼に「オマエノ過去ノ秘密ヲ知ッテイルゾ」という手紙を送りつけた、と思い込んでいるらしい。
つまり、「ワーカーズドア」の創業以前に、両者に何らかの接点があり、彼らが青山に関する何かいかがわしい秘密を握っている可能性のあることを意味している。
少なくとも青山はそれを恐れているということであろう。
中村は報告書の内容を何度も読み返し、推理を働かせた。そろそろ脅迫状にも何らかの具体的な文句を挿入しなければ、実際は何も知らないことを青山から見抜かれてしまう可能性がある。そのためには、報告書から何か具体的情報を読み取らなくてはならない。
おそらく、ビジネスをスタートさせた時の資金に関わることに間違いない。
また、キムチ屋の主人である李文烈よりも、その息子の永吉のほうが怪しい気が否めない。なにしろ、元暴力団の幹部である。そして彼と、彼の組は、覚せい剤と深く関わっていた。ふと、中村の脳裏に閃くものがあった。
(まさか青山勇という男は、この六田組の構成員だったのか!? 又は準構成員だったのか!? 世間にその過去を知られることを恐れているのだろうか!?)
そう思った次の瞬間には、しかし、中村自身がその閃きを否定していた。
もし本当にそうだとしたら、今頃は青山を強請ろうとする輩が引きも切らなかったであろう。なにしろ六田組はかつて百名もの大所帯だったのだ。しかも、今では没落している。当然、ジリ貧になった組員・元組員たちは甘い汁を求めて我先に青山のもとに群がっていたはずだ。だが、秘書としてそういう現象を見聞きした覚えがないということは、この仮説は否定されねばならないということである。
ただ、まったく無関係かというと、そうでもあるまい。
おそらく、両者は「何か」が絡んでいるのだ。
たとえば、組織の一員というのとは、また別の形で関わっていた可能性もある。
推理力を働かせろ、と中村は己を叱咤した。
今更のように彼らのことを調べるということは、今ではすっかり連絡が途絶えているということだ。だが、過去には何らかの形で関わっていた。又知り合いだった。そしてその関係性の中から、青山は数千万円もの起業資金を捻り出したに違いない。
しかも、彼が恐れているということは、「何らかの不正」である可能性が高い。
この報告書の行間には、たぶん、大きなスキャンダルが埋もれている。
中村はとりあえず新たに得たキーワードを考えてみた。
暴力団、覚せい剤、キムチ……といった単語が浮かんできた。
◇
中村茂が首をかしげている同じ頃、報告書に目を通した青山勇は、強い衝撃を受けていた。彼は顔を蒼白にして、「やっぱり…」と独語した。
それは彼が密かに恐れていたとおりだった。
脳裏に、辛く、孤独だったフリーター時代の思い出が蘇ってきた。
当時、青山は「将来、何かのビジネスを始めてみたい」と思っていた。
だが、そうやって己の将来像をなんとなく思い描いたところで、先立つ資金もほとんどなかった。彼の夢は「絵に描いた餅」でしかなかった。
だが、希望と失意の狭間で揺れ動いていた二十四歳のときに、思いもよらなかったチャンスがめぐってきた。上野の焼肉屋でホール係のアルバイトをしていた頃である。
あるとき、青山は、ある常連客からそのきびきびした働きぶりを見止められ、声をかけられたのである。
「いい仕事があるんだが、やってみないか?」
それがキムチ屋の店主だった李文烈との出会いだった。
仕事の内容は、月に数回、韓国の釜山から韓国産のキムチや唐辛子を手荷物として東京まで大量に運んでくるものだった。しかも一回につき報酬は五十万円だという。
信じがたい好条件だった。釜山と東京を往復するだけで、当時の月収二ヶ月分に相当するキャッシュが手に入るのだ。青山は一も二もなく李の申し出を快諾した。
実際にやってみると、仕事は体力と若干の神経を使うこと以外、何も難しくはなかった。これで五十万円も貰っていいのかと、青山のほうが気を使うほどだった。
まず、新幹線で東京から下関まで行く。そこから十九時発の日本船の関釜フェリーに乗り込み、翌朝の八時半に釜山に到着する。その日のうちに指定の場所に向かい、取引先の韓国人から大量のキムチと唐辛子の荷物を受け取る。帰りは、釜山十九時発・下関八時半到着の韓国船の釜関フェリーを利用する。荷物は無税の個人携帯貨物品という扱いで船内に持ち込む。このような日韓フェリーの運賃は、往復で一万七千円と格安だ。
むろん、絨毯の床に雑魚寝する二等船室を使うし、手荷物は別途、重量に応じて運賃に加算されるが、それでもせいぜい追加数千円ほどである。下関に到着後は宅配便を利用するものの、なぜか店舗への「直送り」が禁止されていた。宛先を自宅アパートに指定しろと言われた。荷物を自宅で受け取ってから、その手でキムチ屋の裏口に運んだ。
「うちのキムチは本場韓国産の唐辛子を使用していることが売りなんだ」
李文烈はそう得意そうに言った。
「そうやって韓国産のキムチそのものをブレンドすることによって、乳酸発酵まで韓国で漬けたのと同じになる。競争に勝つには何か他と違うことをやらないとな」
青山は月に数回、この運び屋稼業に従事した。
日韓フェリーには彼と同じような人間が多数、乗り込んでいた。彼らはどうやら、一方の国の商品を個人荷物として大量に船内に持ち込み、もう一方に引き渡すことで生計を立てているらしかった。荷物は食料品や生活雑貨が多かったが、日本から韓国へ向かうときにはそれに家電製品が加わっていた。
この運び屋たちの大半は韓国人のおばさんであるが、明らかに在日韓国人と思われる男性などもおり、在日社会の独自の物流ネットワークの存在を改めて感じさせた。
大勢の運び屋たちのせいで二等船室の一角はいつも窮屈であるが、メリットがないわけではなかった。通常、国境を越えるには出入国審査に手間取るものだが、日韓フェリーには「いつもの運び屋たち」が大量の荷物を抱えて下船のために群れをなしているという特殊事情がある。管理局側もそれを心得ていて、物理的・時間的制約から荷物チェックにもその現実が反映されていた。こうして青山も彼らの一員に埋もれることができた。
稼いだ金をほとんど使わなかったこともあり、青山の貯金は月日とともに膨らんでいった。一年と少し過ぎた頃には、二千万円にも達していた。念願だった商売を始める際の種銭ができたことを思うと、降って沸いたような幸運に喜ぶことしきりだった。
だが、貯金が膨らむのに比例して、疑問もまた次第に膨らんでいった。
あまりに話がうますぎるのである。余計な口はきかないほうがいいと分かりつつも、ある日、青山はその疑問を何気なしに李文烈に投げかけてみた。
「正規に輸入すると関税がかかるが、個人荷物だと無税なんだよ」李は笑顔で答えた。「だから、結果的に安くつく…そういうことだ」
たしかに、それが日韓フェリーの船内に行商人が跋扈している理由ではあった。
だが、それでも五十万円という報酬が、関税や通関手続きにかかる費用を下回っているとは思えなかった。つまり、李の言葉とは裏腹に、「結果的に高くついているのではないか」と思えてならなかった。もっとも、内心でそう疑問に思いつつも、この仕事を失うことを恐れて、青山はそれ以上立ち入った質問はしなかった。
だが、疑問はますます膨らんでいった。彼はやがて、「自分は何かの禁制品を運ばされているのではないか」と思うようになった。
そしてある日、思い切って尋ねてみた。
「おじさん。荷物の中身は、本当にキムチと唐辛子だけなんですか?」
外から荷物を見る限りは、たしかにそうだった。
李文烈の顔からいつもの笑みが消えた。
「余計なことは知らないほうがいい。これは韓国産のキムチと唐辛子だけだ…あくまで君はそう信じていなさい。それが君のためだ」
その言葉を聴いて、青山は「ああ、やっぱりそうだったのか」と思った。
だが、慣れとは恐ろしいもので、青山はその日以降も平然と通関することができた。
日本側の入国審査官は荷物について質問をした際に、返答する相手の目をじっと見ているようだった。おそらく、何かやましいことがあると、質問を受けた際に目の表情として表れるはずだというマニュアルでもあるのだろう、と青山は憶測した。
だが、彼は現実に自分の運んでいる袋の中にキムチと唐辛子以外の何が入っているかを知らない。だから、ごく平然としていられたし、荷物チェックでビニール袋を破かれたことも一度もなかった。もっとも、そんなことをすればキムチの臭いで周囲は惨事になるだろうが――。周りの、同じような運び屋軍団が絶好のカモフラージュになっているという安心感もあった。
青山は、彼の雇い主である李文烈のことが好きだった。親しみを込めて「おじさん」と呼んでいた。釜山で受け取った荷物を店に運び込んだとき、よく夫妻は「飯でも食っていきなさい」と自宅に招いてくれた。おいしいキムチも分けてくれた。青山はキムチが大好物になった。上野の繁華街に、何度も飲みに連れて行ってもくれた。
そんなある日、青山は裏事情の一端を知った。焼酎をたくさん開け、ひどく酔ったときに、李文烈がそれを漏らしたからだ。後の彼の様子を見るに、おそらく秘密を明かしているという自覚がその時になく、記憶にも残らなかったことは、幸いだったかもしれない。
それは思い出話から始まった。苦労人は誰かにそれを語りたがるものである。
李文烈は済州島からの密入国者で、以前は在日社会でもよく差別されていた。ひとり目の息子は幼くして急逝した。一念発起して始めたキムチ屋も、当初はうまくいかなかった。そのために貧乏で、次男の永吉に教育をつけさせてやれなかった。その次男坊は成長すると不良になり、最後にはヤクザになってしまった。
永吉は、ヤクザ社会での出世を目指した。彼には猛烈な劣等感とそれを克服しようとする上昇志向が同居していた。だから、率先して危ない橋を渡ろうとする傾向があった。
ある日、永吉は、組の資金源である密輸のカモフラージュとして、実家のキムチ屋を利用することを思いついた。それは彼にしてみれば一世一代の大博打であり、組内でのし上がるためには絶対に成功させなければならない事業だった。息子は親に土下座してまで頼み込んだ。李文烈には、子供を高校にも行かせてやれなかったという負い目があった。ひとり目の息子が亡くなったこともあり、妻の秀美も彼を溺愛していた。
結局、李文烈は協力を約束してしまった。
「こういう運び屋には、カタギの人間がぴったりなんだ。おれたちじゃすぐに目を付けられるから」
息子の永吉はそう言ったという。
青山は結局、その永吉とやらには会ったことがなかったし、顔もついぞ知ることがなかった。むろん、これは意図的であろうと思った。
なぜなら、万一、運び屋が逮捕されても、黒幕は逮捕されずにすむからだ。
実際、顔を真っ赤にして酔った李文烈も、その時にこう言っていた。
万一のときは自分たちも「知らなかった」で押し通し、あくまで息子をかばい立てするつもりなのだ、と。
次に会ったときには、李文烈は酔った勢いで青山に話したことをまったく覚えておらず、いつもの秘密主義の彼に戻っていた。
ただ、自分が何らかの密輸の片棒を担いでいるという事実だけは分かった。
やがて、二年が過ぎた。青山は三千万円もの大金を溜め込んでいた。相変わらず、自分が本当は何を運んでいるかは、知らなかった。いや、正確には知るのが怖かった。
青山は、大金を稼いでいるにも関わらず、いつまで経っても質素な身なりをしていた。あるとき、李文烈は一向に派手にならない彼を不思議に思って、そのことを尋ねた。
「お金をためて商売をやりたいんです」
青山がそう返答すると、李文烈はしばらく青年の顔を見つめて、じっと考え込んだ。
「私の若かった頃を思い出すな」李はまるで息子か何かを見るような優しげな目つきになった。そして勇気付けるように青山の肩を叩いた。
「悪いことは言わん。それなら、今の仕事を早くやめたほうがいい。もうとっくに気付いているだろうが、運んでいるものは違法な品だ。巻き込んですまなかった。息子には、私のほうからよく言っておくから…」
こうして、両者の関係は終焉をむかえた。そして、それっきりになった。
これが、青山が今まで口外することのなかった、若き日の思い出であった。
◇
Z社の報告書によると、李永吉の所属していた六田組は、覚せい剤を大量に密輸していたという。
間違いない、と青山勇は思った。
自分があの時、運んでいた荷物の中に隠されていたのは覚せい剤だったのだ!
それまでも薄々感づいてはいたが、改めて確信すると衝撃のあまり息が止まった。まるで時間と空間が凍りついたようだった。自分が今いる社長執務室が牢獄に感じられた。
青山は、自分がかつてしたことに対して、改めて罪悪感を覚えた。社会に撒き散らした害毒を思うと、戦慄せざるをえなかった。そして何よりも、自分が覚せい剤の密輸に従事していた事実が万一、世間に表ざたになれば、確実に人生が破滅すると恐怖した。
脅迫犯がその事実を握っていると想像するだけで、いても立ってもいられなかった。もしそうだとしたら、その人物は彼の生殺与奪の権限を手中に収めていることになる。
しかしながら、李文烈が本当にその脅迫犯だろうか、と疑問に思った。
青山は李文烈に対して複雑な感情を催した。彼が密輸に従事していたことを直接知っているのは李文烈だけである。報告書によると、黒幕の李永吉はすでに亡くなっている。
李文烈から、密輸の片棒を担がされたのはたしかだ。だが、そのおかげで彼は自分でビジネスを始めることができた。それに李おじさんは優しかった。最後には彼のことを気遣い、違法行為から解放してくれた。ある意味、今日の成功は彼のおかげと言ってよい。
その李は今、借金もないし、経済的に裕福で、寄付までしているという。
果たして、そんな人間に他者を強請ろうという気が起こるだろうか。
常識的に考えれば、まさか起ころうはずもない。
考えてみれば、このような脅迫状を青山に送りつければ、真っ先に疑われるのは李文烈自身である。そして犯人を突き止めようとする青山側の調査追求の手から逃れられるはずもない。それが分からないほど李文烈が頭の悪い人間でないことは、彼と間近で接していた青山が一番よく知っている。
だいたい、他ならぬ李自身も密輸の片棒を担いでいたのだ。規模こそ異なるが、世間に表ざたになることによって築き上げてきたものを失うという意味では、青山と同じ立場である。つまり、彼も強請られる立場であって、強請る立場ではありえないはずだ。
こういった理由から、脅迫状をよこしたのは李文烈ではないと思えた。同様に彼の口から青山が密輸に加担していた事実が漏れることも考えられない。なぜなら、李自身が共犯者である以上、それが外部に漏れることは自身の破滅をも意味するからだ。
報告書から察するに、六田組に対する一斉摘発の際に、李文烈のキムチ店は無事だったようだ。これは、その頃には組の密輸と完全に関係を断っていたことを意味する。
おそらくは、息子の永吉の死とともに、その関係は終わったのだろう。摘発当時、六田組は多数の幹部が逮捕されたそうだが、彼らの供述からも漏れなかったということは、李永吉が活用した密輸ルートが極めて個人的なものだったからに他ならない。
むろん、当時の永吉自身にも家族を守る意志があったのだろう。
そう考えると、永吉の口から青山のことが漏れた可能性も低いと考えざるをえない。なぜなら、自身の家族をも巻き込んでしまうからだ。
では、脅迫状を送っている者は、いったい誰なのだろうか? 脅迫者は今現実に存在し、彼に脅威を与えているのだ。青山はますます分からなくなった。
李夫妻はかくのごとしだし、息子の永吉も一九九九年に死亡している。
彼はたぶん、自分が密輸した覚せい剤に手を出してしまい、中毒か何かになってしまったのだろう。そう考えると、晩年は正常な思考が困難になっており、運び屋だった青山のことをうっかり周囲に漏らした可能性も考えられる。だが、それにしては脅迫の時期が遅すぎる感も否めない。なぜなら、ベンチャー企業家としての青山の名前と顔が喧伝され始めたのは、ネット株がバブルの様相を呈していた六、七年も前のことだからだ。
つまり、仮に李永吉周辺の暴力団関係者が、永吉が死亡する一九九九年以前に青山の情報を手に入れていたとしたら、もっと早くに「ワーカーズドア」を標的にしたはずなのである。仮に脅迫犯がそのような暴力団関係者だとすれば、その熱狂が下火になってしまった今の時期になってようやく強請りを始める可能性は低いはずだ。
もっとも、結局のところこれも推測の域を出ない。
たとえば、最近になって急に金に困り始めたのかもしれない。実際、企業家を強請ろうなどという考えは、普通はカタギの人間には思い浮かばない。
青山勇はいろいろと考えた末、やはり故李永吉の周辺がもっとも怪しいのではないかという結論に落ち着いた。まだ永吉が生きていた頃に、彼を通して何らかの形で青山が密輸に関与していた事実を知った暴力団関係者がいた。そして、最近になって、企業恐喝という犯罪へと駆り立てる窮状が、その男に生じた……。
とりあえず、そんな予想を立ててみた。
ただの推測とはいえ、犯人像に独自に目星をつけたことは、青山にとってある程度の心理的な救いにはなった。いずれにしても、焦点は今後の調査の進め方であろう。
脅迫者はいったい誰なのか? 調べねばなるまい、なんとしても。
◇
秘書の中村がその日の予定を社長に説明していた。
「…部長級会議は五時半までに終了させ、移動。六時から、ホテルニューオータニでIT企業経営者の集いがあります。ライバルのNも出席の予定です。それが終了次第、今度の上場に関して『日刊Jスポーツ』をはじめマスコミ数社の記者から取材があります。その後、赤坂のY亭で、経団連のT氏をまじえて会食…。本日の予定は以上です」
青山はあからさまなため息をついた。
「Jスポはこれで三度目じゃないのか」
「はい。デスクに尋ねたところ、読者層が読者層ですので、社長のような『若き成功者』の記事は羨望とやっかみを引き起こすらしく、反響がとても高いのだとか」
そんな男が薬物絡みで逮捕されれば反響はもっと凄まじいことだろうよ。
と青山は思わず内心で自嘲した。
成功者が破滅する様を見た読者たちは、きっと小躍りするに違いない。
「ところで中村。また、これをZ社に届けてくれないか?」
◇
青山が差し出したのは、例の銀色の珍しい封筒だった。第二の依頼書である。
ほらほらおいでなすったぞと、中村はほくそえんだ。
中村はZ社に行き、依頼書をそのまま手渡した。その帰り、彼は上野に向かった。
東上野にそのキムチ屋はあった。店内では、老眼鏡をかけた老いた男が丸椅子に座り、新聞を広げていた。李文烈だと中村は直感した。
ふと、過去に本当に青山勇と接点があったのかどうか、確かめてみようと思った。
中村はキムチ屋に入り、品定めをしながら、親しそうに店主に話しかけた。キムチに関する質問には何でも答えてくれた。
うちは韓国産の唐辛子を使っているんだ、発酵の度合いによってちゃんと食べごろの期間というのがある、材料は白菜と唐辛子だけじゃなく魚介類や果物も混ぜて複雑な味にしているんだ……李親父は得意げに語り、話は弾んだ。
「ああ、そうそう」中村は頃合をみて言った。「そういえば、バンクソフトの孫義正さんって、在日同胞なんだってね」
「ああ、らしいがね」親父の顔が少し誇らしげにほころんだ。
「あの人、資産がウン千億円なんでしょ? いいねえ、ベンチャー企業の創業経営者なんて、株式上場すれば一夜にして億万長者だからね」
「私らの頃とは時代が違うね」
「新聞か何かで読んだんだけど、そういえば今度、『ワーカーズドア』の青山勇っていうのが新興市場に会社を上場させるらしいね。なんでも、まだ三十七だとか」
突然、親父の顔つきが変わり、目があちこちに泳いだ。
「おじさん、知っている?」
「あ、ええっと…」店主はもごもごと口ごもった。「いやあ、初耳だな…」
「日本人も最近はキムチを食べるようになってきたじゃない。商売は繁盛しているんでしょう? おじさんだって、工場作って、上場を目指せば?」
「アハハ…」親父は少し引きつった笑みを浮かべた。「私ももう少し若ければ、この商売を拡張して、本格的な食品製造会社にするんだがなあ…」
「なあに、まだまだお若いじゃないですか」
中村はキムチ屋を出た。店主に背を見せつつ、「間違いない」とほくそえみながら。
このキムチ屋の主人は、明らかに青山勇のことを知っている。そして、何らかの理由で他人のふりをしたのだ。やはり「何か」を隠したいらしい。
社長の青山は、この主人が脅迫状を出したのではないかと思い込んでいるらしい。強請られていると思い込んだということは、青山がこの主人に何らかの弱みを握られている可能性があるということだろう。だから、この男のことを恐れているのだ。
では、その弱みとはなんだろうか。おそらく、創業時の起業資金の出所が絡んでいるに違いない。もしかして、何らかの非合法な活動が関わっており、その過去を暴露されることを恐れているのだろうか。だから、相手の動向を気にしているのではないか。
いずれにしても、両者は過去に接点があったのだ。
今回はそれが分かっただけでも収穫である。そしてそうと分かった以上、次の脅迫状には、具体的に過去を連想させる言葉を遠慮なく挿入することができる。
中村は報告書を盗み見た成果を反映させる形で、四通目の脅迫状をしたためた。
「手錠ヲカケラレタイカ? キムチ、暴力団、覚セイ剤」
◇
かくして、青山勇のもとに、また追い討ちのように脅迫状が届けられた。
青山は社長執務室に閉じこもって中から鍵をかけると、文面を開いた。
その瞬間、ある文字に目が吸い寄せられた。
「…キムチ、暴力団、覚セイ剤」
今度は決定的だった。あまりに具体的過ぎる。
もう間違いなかった。送り主はあのことを知っている!
青山は椅子に崩れた。恐怖の重圧で胸が圧迫された。まるで全力疾走で駆けたように、心臓がドクドクと痛みを伴って脈打ち始めた。
万一、覚せい剤の密輸でビジネスの運転資金を手に入れた事実が世間にばらされたら、確実に警察に逮捕されるだろう。
今を時めく青年実業家の一大スキャンダル……マスコミが狂喜する様が目に浮かぶようだった。当然、会社を上場し、創業者利益を手に入れてセレブな暮らしを楽しむという夢も露と化すだろう。いや、企業家生命の終焉程度ではすまないかもしれない。明らかに反社会性の強い重罪である。懲役も食らって人生そのものが終焉しかねない。
ふと、美香子の姿が脳裏に浮かんだ。結婚した青年実業家の正体が覚せい剤の元密輸人だったと知って、いったい彼女はどう思うだろうか。
家庭崩壊は免れないに違いない。彼女は夫を軽蔑し、見捨てるだろう。夫婦の間にまだ子供がいないことが幸いだったかもしれない。
要は、この件でいったん逮捕されてしまえば、以後は一生、日陰者として世間から隠れて生きるほかないということだ。それは想像するだに恐ろしい未来だった。
そして、決してあってはならないことだった。
とても警察や顧問弁護士に相談できるような事柄ではない。
青山は震える手で、棚から六法全書を取り出した。ほとんどまっさらだ。
調べてみてはじめて知ったが、覚醒剤取締法というのは数十条にも及ぶ長大な法律だった。そして自分が過去に行った行為は、ありとあらゆる条項に違反していた。
中でも青山の目を引いたのは罰則の項目だった。
第四十一条では、「覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する」とあるが、次の二項では「営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し…」とあった。また、同条の三では、「輸入及び輸出の制限及び禁止の規定に違反した者」の罰則として、「十年以下の懲役に処する」とも定めていた。
法律の文言を読んでいるだけで、まるで自分がその刑に処せられるような気がして――事実その可能性があるが――さらに心臓が痛んだ。
六法を紐解くうちに、自分が密輸人として関税法にも違反しているだけでなく、もっと重い罪に該当している可能性もあることが分かった。それは薬物の営利目的での輸入を「業」として行った場合に適用される麻薬特例法である。これによると、罰則は「無期または五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金」と定められている。
青山は分厚い書籍をパタンと閉じた。
ひとつはっきりとした。彼が今、姿を見せない脅迫者によって生殺与奪の権限を握られているということだ。生かすも殺すもその者の気分次第である。
青山の運命は今、他人の手の平にある。
悪戯ではありえない。目的はやはり金だろう。彼の肝が十分に冷えた頃を見計らって、要求を突きつけてくるに違いない。
青山には、強請りに応じるしか選択肢はないように思われた。
だが、一度、強請りに応じてしまったら、以後も強請られつづけるに違いない。犯人にとって、彼は黄金の打ち出の小槌だ。永遠にたかられる可能性が高い。
どうすればいい?
要求に応じなければ地獄に落ちる。だが、応じてもまた無間地獄である。
地獄の「度合い」を考えてみた。
仮に、過去の犯罪を世間にばらされれば、すべてを失う。相手の要求に応じれば、とりあえずは、それは避けられるだろう。それに、相手もいったん金を強請りとることに成功すれば、さらに罪を重ねたことになり、もはやばらすことはできなくなる。なぜなら、ばらせば、犯人自身にとっても身の破滅に繋がるからだ。
もっとも、そこまで持っていくには、ある程度、犯人の身元の証となる、又は犯人に繋がる何らかの手がかりを手に入れなくてはならない。
というのも、相手がまったくの正体不明を通すことに成功すれば、十分な金を強請り取った後にばらす、という鬼畜の所業に及ぶことも考えられるからだ。
探偵事務所のZ社には、第二の依頼書をしたため、臭いと睨んだ故李永吉周辺の暴力団関係者を洗わせている。こちらも、相手に対する包囲を狭めていかなくてはならない。
青山は、苦渋の末「強請りにはとりあえず応じたほうがいい」と考えた。
すべてを失うよりはマシだからだ。
だが、その先に待ち受けているのは、底なし沼かもしれなかった。
この脅迫状が届いて以降、青山は、表の自信家ぶりとは裏腹に、内心では常に不安に苛まれ、ビクビクするようになった。
過去の忌まわしい記憶がいつも彼の脳裏に纏わりついた。
しばらくして、青山勇は不眠症になってしまった。豪華なディナーパーティで出されるフォアグラや銀座の高級寿司を食べても、さっぱり味が分からなかった。
街の様子も違って見えるようになった。そこはいつもの喧騒で満たされていた。
だが、すれ違う人々の何事もないかのような表情を見ていると、まるで自分だけがこの世界から疎外され、重圧に苦しんでいるような気がしてならなかった。
◇
「あなた、どうかしたの?」
夕食時だった。
テーブルの向こうで、美香子が形のよい細い眉毛をしかめて、心配そうに尋ねた。
「いや、何でもない…」
「何もないはずがないじゃない。あなたったら、最近ため息ばっかりついているし、食だってめっきり細くなったし、本当に変よ」
青山勇は、初めて自分が茶碗を持ったまま止まっていたことに気付いた。これではおかしいと思われるはずだ。
だが、この件に関しては、相手がいくら妻でも言えなかった。覚せい剤とか密輸といった物騒な話は、平和な家庭に持ち込めるものではないのだ。
「大丈夫だ」
勇は飯を無理して飯をかき込んだ。相変わらず、味がしなかった。
美香子がそんな夫を悲しそうな目でじっと見つめていた。
寝る前だった。勇は居間のソファでクラシックのCDを聴いていた。頭から少しでも苦悩を追い払いたかったからだ。
だが、美しい調べへの集中は途切れがちで、ふと気が付くと、例の心配事に意識が行っているのだった。そして無意識のうちにこんな言葉が口をついて出た。
「おれは、どうすればいいんだ」
悩みを誰にも打ち明けられず、ひとりで抱え込むのは存外に辛かった。
ふと、何の前触れもなく、美香子が隣に腰掛け、寄りかかってきた。
「私はあなたの妻よ」頭を夫の肩に持たれかけさせた彼女が呟いた。「あなたが辛い思いをしていると、私も辛いわ」
「…………」
「どうか、隠し事はしないで。私はあなたが大富豪になることよりも、毎日を平穏無事でいてくれることのほうが、ずっと嬉しいの」
クラシックの調べが、ふいに甘いものに変わった。
「ありがとう」
美香子の優しさに触れることができて、少しばかり救いとなった。
ふと、以前、妻が何気なく漏らした「少しどこかに寄付するっていうのはどう?」という言葉が脳裏に思い浮かんだ。
その場でそれはすぐに財団の設立というアイデアへと発展した。公益法人を通して何らかの慈善事業をやれば、自分の罪を少しでも相殺できるのではないかと思ったからだ。それに、この措置は脅迫者が万一、自分の過去を暴露した時の備えともなる。
「青年実業家はたしかに社会的に許されない罪を犯したが、一方で罪悪感に苦しみ、罪滅ぼしをしていた」ともなれば、世間の理解も断然違ってくるだろうからだ。
つまり、財団の設立は予防線であり、いわば将来のセイフティネットである。
夫の表情が少し明るくなったのを見て取ったのか、美香子が少し微笑んだ。勇も微笑み返し、彼女の肩を優しく抱いた。
翌朝。青山はいつもの時間に六本木の本社に姿を現し、いつものごとく仕事を始めた。
傍目には何も変わりない。だが、心の中は相変わらず落ち着かなかった。
考えごとをしていると、手元がおぼつかない。青山が社判を書類に押しているときだった。いつの間にかスタンプ台のインクが指に付いており、大事な書類に赤い指紋を残してしまった。青山は思わず「チッ」と舌打ちした。
彼はそのくっきりとした己の赤い指紋を、しばらくじっと見つめた。
(後編へと続く)






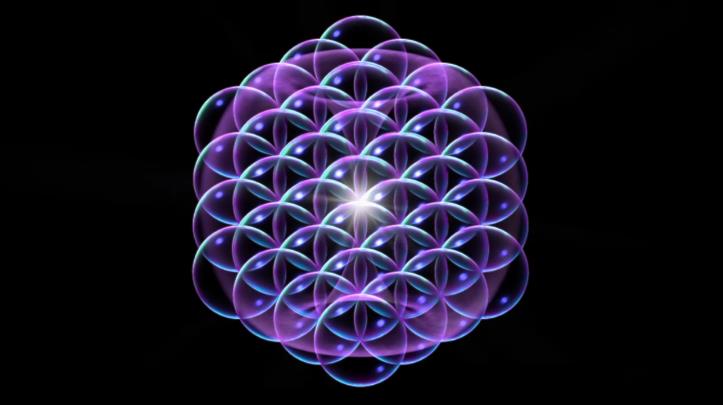





スポンサーリンク