みなさん、こんにちは。
突然ですが、私の短編ミステリー(としてはやや長めかも)を紹介いたします。
ちょっと解説しておきますと、「密室殺人」と「入れ替わり」の二つのトリックを扱っています。ミステリー好きの人には結構うってつけな作品かと思います。
シリーズものとして、「ビーナス探偵」というタイトルにでもしようかと思っているのですが、とりあえず今のストレートな題名のままになっています。
へたっぴな挿絵でもつけられたらいいのですが・・・。
結構自信作ですが、ツイッターやフェイスブックで拡散シェアしていただけると、助かります(´;ω;`)。
なおイメージキャラとして主人公にぴったりな仲間由紀恵さんを勝手に使用させていただきました(笑・抗議あれば直ちに削除します)。
始める前に、簡単に登場人物を紹介させていただきます。
主人公の小笠原裕美
探偵会社「インテリジェント・ヘッドクォーター(IHQ社)」創業者兼CEO。年齢は本人いわく秘密。元警察庁のキャリア。天才的な頭脳と推理力、そして高邁な精神の持ち主。行動派で自ら現場の先頭に立つ。ただし恋愛指数だけはゼロで、未だ彼氏なし。
鏡義雄(通称・ヨシオ)
二枚目半だが、頼りがいのある青年探偵。通常の調査はもとより、変装や潜入なども得意。万能タイプ。ひそかに裕美に思いを寄せている。
藤井源之助(通称・源さん)
元警視庁刑事。退職後の第二の人生としてIHQ社を選んだ。聞き込み・尾行など足を使った調査のプロ。江戸っ子で恐妻家。裕美のことを「お嬢」と呼ぶ。
風間雪(通称・お雪)
元スケバン。陸上自衛隊出身。スポーツ万能で各種格闘技のプロ。スポーツカーやバイクの運転もプロレーサーなみ。長身で容姿はモデル級。調査のためにホステスやキャバクラ嬢になることもしばしば。口が悪く、裕美のことを「カシラ」と呼ぶ。
大塚信孝
IHQ社の創業メンバーで専務。裕美が事務方を一任している人物。常に冷静沈着で、総務全般を取り仕切る。堅物なのが玉に傷。経営面などで裕美に諫言もする。
三上サクラ
事務・経理を担当するが、IT技術者でもある。理工学部卒のメガネっ子。
北王子英明
警察庁時代の裕美の元上司。茨城県警察本部長を経て、警察庁長官官房総括審議官。階級は警視監。今でも裕美のよき相談相手。実は警察組織の革新官僚グループに属し、裕美を警察と探偵業界の橋渡し役にすべく、前々から画策している。
不動道直
探偵業界の大御所。調査業者の業界団体である社団法人全国調査業協会の元理事長で、裕美の後見人。富豪。戦中派で今も隠然たる力を有する老人。
*とりあえず、私の中にある主人公のイメージにぴったりということで、女優の仲間由紀恵さんの顔写真を拝借させていただきますた。
探偵小笠原裕美シリーズ 「ダブルトリック」本文
「社長、ちょっと妙なことが…」
受話器を置くなり、鏡義雄がくるりと椅子を回転させた。
小笠原裕美はそれまで読んでいた日本経済新聞から目を離した。
「たった今、記者筋から聞いた情報によると…」鏡が眉をひそめた。「今朝方、太田善四郎氏が猟銃で自殺したそうです」
一瞬、裕美は心臓を鷲掴みされたような気がした。「ええーっ!?」と同時に奇声を発したのは、碁盤を睨んでいた藤井源之助と、特殊警棒を弄んでいた風間雪だ。
「太田さんが…自殺…?」
オウム返しに訊くのが精いっぱいだった。鏡が暗い顔で頷いた。
「そんな馬鹿なことがあるかよ! あのオッサンが自殺するはずねえ!」
抗議するがごとく猛然と起立したのは風間だ。
「ちげえねえ!」藤井も負けじと叫び声をあげた。「こいつはぜっていに殺しだ!」
単刀直入な彼の言葉は事務所の空気を代表していた。裕美もそう直感した。だが、社を率いる彼女としては、安易な決めつけやもの言いはできない。
「とりあえず、私たちは警察の捜査を待ちましょう。進展次第では、こちらのほうにも何かしらの事情聴取に来るかもしれないわ」
金払いのよかった依頼人の、突然の死。その日、インテリジェント・ヘッドクォーター社の誰もがショックから抜け出すことができなかった。
「妻が他の男と浮気していないかどうか、調べてほしい」
投資会社を経営しているという太田善四郎からIHQ社にそんな依頼があったのは、二ヶ月ほど前のことだった。相談のために来社した五十代後半の実業家は、腹がでっぷりと出たアンコ体型で、脂ぎったという表現が少しも陳腐に感じられないほど、丸い禿頭が見事に蛍光灯の光を反射していた。顔つきが精力的なだけでなく、声にバリトン歌手のような張りがあり、相談中も時おり大口を開けて豪快に笑った。生まれつき体内エネルギーのポテンシャルの高い人物らしく、終始、非常にアグレッシブな印象を受けた。
妻の名は明子。三十五歳。旧姓は根元。元ホステスで後妻である。写真を見せてもらう。銀座で評判の美人だったというだけあって、近影でもその美貌はほとんど衰えていない。
「前の妻子と別れた際には、酷い目に合わされましてな」
太田氏はそうぼやいた。離婚時の慰謝料が凄かったらしい。そもそも本人の浮気が原因なのだが、蓄財が第一の生きがいである彼にとって、財産を分捕られることは耐え難い苦痛だったようだ。今回はどうなのか分からないが、口ぶりから察するに、少なくとも相手から尻尾を掴まれるようなヘマは犯してないらしい。
「今度はぜひとも向こうに有責者になってもらおうと思っとります」
といって、上品でない笑みを浮かべた。
「奥さんは実際に浮気なさっているのですか?」
「幸い」と太田氏は含み笑いをした。「それは間違いないと思います。というのも、私は相場をやっとる関係で時々、海外の動向をチャックする必要があり、月に何日かは徹夜をすることがあります。情報の入手が少し遅れるだけで何千万円と儲け損なったり、損害を出したりすることがあるからですよ。当然ながら、翌日が平日の時は、帰宅することなくそのまま営業開始です。下手すりゃ一日半も事務所に詰める時があります」
「その時に浮気された、と」
「はい。こういった時は、事前に必ず妻に連絡を入れるのですが、ある日、幸運が重なって早めに手じまいできたことがありました。追加の連絡もせずに、十二時前にふいに帰宅すると、なんと妻の姿がない。ケータイに連絡しても繋がらない。その日、あいつは結局、朝方まで帰ってきませんでした」
「あとで奥さんはなんとおっしゃっていたのですか?」
「むろん、あいつは『女友達と飲んでいた』などと言い訳しておりました。ですが、妙に後ろめたい表情というか、焦っていたのは一目瞭然でしたな」
その時のことを思い出したらしく、憤慨した。赤らんだ顔は茹で蛸そっくりだ。
「なるほど…」
裕美は与えられた情報から思案し、調査時期にあわせて依頼者が連続して徹夜する作戦を提示した。そうでもしない限り、「尻尾を掴む」ことはできないと考えたからだ。
「なるほど」太田氏は感心し、満足そうに頷いた。「そうすれば、あいつも浮気の虫が騒ぎだすだろうからな」
だが、その日、結局、実業家は契約には慎重だった。
相談から二週間が過ぎた。その間にも他の探偵会社を回って、値段と調査の質とのバランスを比較したらしい。その結果、IHQ社に決めたようだ。
本契約の際に、三鷹市にある自宅まで足を運んでほしいと言われた。妻が不在の時を教えてもらい、裕美自ら印鑑をもらいに赴いた。角地に建つ洋風の豪邸だった。裏手が玉川上水に隣接しているため、野鳥のさえずりが止むことがない。今は春を予感させる新芽の装いだが、夏にはさぞかし緑が豊かなことだろう。広々とした正面の芝生の庭にはシェパードが放たれていて、玄関には監視カメラが設置されていた。
「結果さえ出してくれるなら、金はいくらでも払おう」
ワイン色の高級ガウン姿の実業家は、葉巻をくわえながら実印を押した。実際、通常の協議離婚で分捕られる財産に比べれば、調査費など微々たるものだろう。
めでたく契約が成立したところで、お茶を飲みながらの雑談となった。付き合わないわけにはいかない。これも営業の一環だ。調査結果に満足してくれれば、資産家というのは同じような仲間を客として紹介してくれるものだ。そう思うと、大事なお客である。
当人によると、貧しい出自ながらも高校卒業後、株一筋で成り上がったという。今でこそ築き上げた資産を堅実に運営しているが、かつては仕手戦の際に何度も名前が浮上するほどの大物投機家だったらしい。向こうも、警察官僚出身を看板にする女性探偵に興味があるらしく、いろいろと立ち入ったことを尋ねてきた。時おり、好色そうな目つきさえする。裕美は適当に、だが失礼のないよう、受け流した。
自慢の書斎にも通された。重々しいドアには鍵穴はなく、指紋キーが付いている。
「私以外の人間には絶対に開けられんようにしている」
成金にしばしば見られる人間不信だろうか。ドアを閉めると、背後で電子ロックが自動的にかかる音がした。内側からは握り玉を回すと普通にドアが開くが、外からは指紋登録者でなければ解錠できない仕組みだ。
書斎といっても二十畳はあり、ダブルベッドまで据えてある。寝室併用らしい。大きな金庫もあった。大型テレビ以外にも十四インチのモニターがあり、監視カメラの映像が引かれている。本棚にはお決まりの、真新しい百科事典が並んでいる。壁には様々な賞状や絵画のほかに、二丁の猟銃とサーベルもかかっていた。
部屋には大きな窓が一つだけ付いていた。重厚なアルミサッシの向こうには、庭に面したバルコニーがある。サッシに近寄ってみた。中央のクレセント錠のほかにも補助錠が二つもある。網入の板ガラスがやけに重々しい。
彼女の視線に気づいたのか、太田氏が自慢げに言った。
「防弾式だよ」
「なるほど、道理で厚いガラス戸で」
「分厚いだけじゃないんだ」と、機嫌よく葉巻を吹かす。「特殊フィルムでサンドしてあるので、大男がハンマーで叩いても絶対に割れない」
「ほう…それは凄いですね」
「ここだけの話、殺されてもおかしくはないと思っていますよ」
実業家は胸を反らせて豪快に笑った。しかし、その目はどこか本気だ。おそらく、莫大な資産を築き上げる過程では、いろいろな人から恨みを買ったに違いない。
女性に己のプライベートをさらけ出すことで親密さが増す、と信じている男がいる。裕美としては、相手の気を反らせるためにも、しゃべり続けるほかなかった。
週明け、調査が始まった。事前の申し合わせ通り、太田氏は連続してオフィスで徹夜した。その間、後妻を徹底的にマークしたのが藤井源之助と風間雪のコンビだ。
数回目の徹夜の際、彼らの読み通り、明子が動いた。妙にめかしこんで、夜の新宿方面へと出向く。待ち合わせ場所に現れたのは、三十前後とおぼしきサラリーマン風の男だった。一八〇センチ前後の長身で長髪、そしてなかなかのイケメンだった。
ふたりは高級レストラン、バー、そしてホテルと、お決まりのコースを辿った。財布を開いていたのは明子のほうだった。どちらがぞっこんかは一目瞭然だった。
朝方、浮気相手の男はホテルを出ると、そのまま職場に直行した。藤井たちは尾行を続け、身元を突き止めた。林達郎・二十七歳。都内の貿易会社に勤める会社員だ。
調査結果の報告の際には、太田氏にまた来社してもらった。報告書には、時系列で記された妻の詳細な動向のほかに、浮気相手の簡単なプロフィールも添えた。むろん、裁判で証拠として使えるビデオカメラの録画も手渡した。実業家は「やはり」と憤慨した。とくに、相手の若い男に妻が幸せそうに微笑むショットに青ざめ、激怒した。
だが、報告書を閉じた時には、もう吹っ切れた様子で、余裕すらあった。妻の浮気とその相手を見事に割り出してみせた調査に対して、一応は満足したようだった。
「いやはや」太田氏はため息をついた。「どうやら、疑ってみて正解だったようですな。今日から書斎のほうには妻も絶対に入れないようにします」
「お気の毒ですが…」としか言いようがない。
「道理で最近、小遣いをせびると思いましたよ。出来損ないの兄だけじゃなく、浮気の相手にまで貢いでいたとすれば、金がいくらあっても足らんはずだ」
そう吐き捨てると、懐からシガーケースを取り出し、一本の葉巻をつまんだ。
「明子さんはお兄さんに援助でも?」
裕美は気を利かせて、テーブルのライターの火を灯した。
「いい歳して、職に就いているのかいないのかもよく分からない男でしてな」
太田氏は嫌悪と軽蔑の入り混じった表情を浮かべつつ、身をかがめた。無事に葉巻に火がつくと、片手をしゅっと揚げ、お礼のジェスチャーをした。背をソファにあずけつつ大きく吸い込むと、天井に向かって「ふーっ」と紫煙を吐いた。
「いっつも妻のところへ金を借りに来てますわ。私にはペコペコと愛想ばかり。本当にだらしない男で、毎晩のようにフラフラと繁華街で飲み歩いているそうです」
「はあ…」
「もとを辿れば、私の金ですよ。ああいうのが、チャラチャラした軟体動物みたいなナンパ男の末路なんですな。哀れというか、情けないというか…」
といわれても、知りもしない人のことだ、分かるわけがない。
依頼者は天井の辺りを眺めながら、しばし紫煙をくぐらせた。突然、「だが」と言って灰皿に手を伸ばした。葉巻を押し付けると、不敵な笑みをこぼした。
「これさえあれば、すべてを終わりにできる」太田氏はテーブルに置かれたファイルを手にとると、揺すってみせた。「有責者は不貞を働いた明子のほうだ」
ニヤリとしたその表情と言葉の端には、もはや勝利感すら漂っていた。正直、裕美は気分が悪かった。だが、不貞の事実は事実である。
「ところで…」実業家の目が急にぬめった。「あなたもなかなかの美人ですね」
「ありがとうございます」
「どうだろう、近いうちに食事でも行きませんか? ニューオータニのトゥールダルジャンなんかどうかな。二十年もののシャトー・マルゴーくらいは空けさせるが」
「困りますわ」裕美は微量の棘を込めた営業スマイルを浮かべた。「といいますのも、私がいまお付き合いしている殿方が空手の達人でして、恐ろしく嫉妬深い方ですもの。常々、『おまえに近づく男は手刀で喉を一突きしてやる』なんて豪語しておりまして」
「ほう…」
冗談とも本気ともつかぬ口ぶりに面食らったようだが、少なくとも浮気の虫は萎えてしまったようだ。その目からは急速に興味が失われていくのが見てとれた。
ちなみに、不快な誘いを撃退したこのエピソードをあとで自慢すると、感心されるどころか、「また脳内彼氏の登場ですか」などとみなに笑われてしまった。
こうして、裕美たちの仕事は終わった。席を立った依頼者は去り際、またしてもファイルを掲げ、「これで明子を追放できる。ありがとう」と、礼を言い残した。
その後、彼がその報告書をどうしたのか、分からない。妻に証拠を突きつけたのか。それとも黙っておいて、水面下で離婚に向けて動き始めたのか。いずれにしても、太田善四郎氏の自殺は、ひと悶着あるだろうなと思っていた矢先のことである。
だが、あれほどポジティブな人物が、果たして自殺するだろうか。なにかおかしな点があれば、警察は捜査を始める。当然、こちらのほうにも訪ねてくるだろう。
だが、待てども待てども捜査当局からの連絡はなかった。
「…なるほど、たしかに、そいつは変だな」
電話の向こうにいる長官官房総括審議官の北王子英明も同意した。とうとう痺れを切らした裕美のほうから、警察庁の元上司に連絡してしまったのだ。
「でしょう?」裕美も念を押す。「とても自殺をするような様子には見えませんでした」
なにしろ、消極性や陰気とはほど遠い人物だ。実際に人となりを間近で目撃した彼女としては、自殺するはずがないと確信している。
「でも自殺が疑わしいとする根拠はそれだけかい?」
「強いていえば、それだけです」
「女の勘ねえ…」かすかに笑いをこらえている。
「あのねえ、北王子さん。真面目に聞いてますぅ?」
「経済状態は調べたのかい?」
「ですから、あの人はお金持ちで…あっ」
失念していた。最後の会合の後、もしかして太田氏は相場で大失敗をやらかしたかもしれない。多額の負債を抱えてしまったとすれば、十分に自殺の理由になりうる。
「まあいい」北王子はため息をついた。「ちょっと待っていてくれ」
それから一時間もしないうちに、彼から連絡が入った。
「一応、捜査は行われていたよ。会社の経営状態はまったく問題ない。数名の従業員はボスの自殺の理由が皆目分からず、呆然としているらしい。だが、どうやら警察(ルビ:こっち)では自殺ということで片が付きそうな気配だ」
「捜査員は太田氏がわれわれと接触していた事実を知っていましたか?」
「まったく知らないと言っていた」
「それはマズいですよ。他殺だとしたら、動機に関わることですから」
「どうする? 話を通しておくか? 根回しなら、してやるぞ」
いざそう提案されると、一瞬迷った。だが、疑問をこのまま放置しておくのも気持悪いと思い直すと、「お願いします」というセリフが自然と口をついて出ていた。
受話器を置いた。しばらくその場で考え事に集中する。
部屋の向こうから「うほん」と咳払いが聞こえた。専務の大塚信孝だ。銀縁メガネをつんと直しつつ、いつもの冷静沈着な表情で口を開いた。
「社長。分かっておられると思いますが、この件にこれ以上関わったところで、われわれにとっては一文の得にもなりませんよ」
「むろんよ。ただ、どうしても見過ごせないの」
大塚は返事の代わりに肩をすくめた。
「あなたも一度は警察官だった身。本当は血が騒ぐんじゃありませんか?」
裕美も肩をすくめて、いたずらっ子のように舌を出した。
「なるほど、太田善四郎がそんな依頼をねえ…うーん…」
九十九豊(つくもゆたか)が腕を組んで考え込んだ。
本捜査を担当している捜査一課の殺人犯捜査第六係係長である。五十代にして真っ白な頭を七三に分けている異相の持ち主だ。
その隣に腰かける右腕の相馬警部補――こっちは若禿げだ――と、テーブルを挟んで対峙している裕美が、じっと警部の様子をうかがう形になった。
「ちょっと本棚のうつった写真と虫メガネを持ってきてくれ」
九十九警部に言われ、相馬刑事が警視庁刑事部の応接室からすっ飛んでいった。数分ほどして、鑑識の写真班が撮影したらしい数枚の大判写真と虫メガネを手に持って現れた。
「いえね、机の上や引出し・金庫の中にそういったものがなかったことは記憶しているんですよ。ですから、書斎にあったとすれば、本棚しかありえないと思いまして」
警部はそういって、写真とレンズをよこした。数枚を突き合わせると、本棚の全景が収まっている。IHQ社の調査報告書は市販のファイルに綴じたものだ。背表紙にも題字をラベルしているので、すぐに分かる。裕美は拡大鏡で写真の表面をなぞった。
しばらくして、見なれた背表紙が眼に飛び込んできた。
「ほら、ここです」と、黄色いファイルの納まっている場所を指し示した。
いつの間にか老眼鏡をかけた警部とその右腕が覗き込んだ。
「この報告書を受け取った途端に善四郎氏が“自殺”してしまった…」身体を起こした相馬警部補が言葉に力を込めた。「係長、これで殺害の動機が強化されましたね」
「ああ、さっそく奇襲をかけてみようか」
「はいっ」
例の豪邸に突然おじゃまするという意味だろう。明子はさぞかし泡を食うはずだ。
「ありがたい。役に立つ状況証拠です」
白髪の警部は裕美のほうに振り返り、ペコリと頭を下げた。それを横で見た青年刑事も、「参考になりました」と言い、続いて直角にお辞儀した。
礼を言われて、悪い気はしなかった。応接室の空気が急速に和んだように感じられた。北王子の根回しのおかげか、それとも彼らの人格に拠るものなのかは分からないが、ふたりの刑事は当初から友好的な態度だった。
ただし、一方的に情報提供をするだけでは駄目だ。こちらとて独自調査をする以上、ギブ・アンド・テイクに持っていかなくては訪問の意味がない。
「ですから、私には太田氏が自殺する理由が見当たらないのです。憶測は禁物ですが、氏の自殺による最大の受益者が誰かという点は、見過ごすことができません」
「いやあ」九十九警部が頭をかいた。「実はわれわれの捜査でも、自殺の理由がないこと、その兆候もなかったことは分かっていたんです。誰に聞いても自殺するほどナイーブじゃない、とね。それに夫人にも引っかかっていました。とくに前妻や親類筋からは、あからさまに女狐とか、泥棒猫といった形容が飛び出したほどです」
「今度の死に関しても、あの泥棒猫が何か関係しているに違いないとか、あいつが殺したに決まっているといった過激な言葉も聞きました」
聞き込みに奔走したらしい相馬警部補も横から補った。
「ですが、これらはしょせん主観的な印象でしかない。しかし、太田氏がすでに離婚を決意しており、あなた方の調査を通して妻の浮気の証拠を握っていたとすれば、話は別です。それは夫人にとって破滅を意味するからです。十分に事を急ぐ動機になりえます」
事を急ぐ――離婚前に夫を殺害する、という意味だろう。
「ましてや、陰に若い男がいたとすれば…」相馬警部補がぐっと拳を握った。
「少なくとも、未亡人を任意同行して事情聴取する理由にはなりますわね」
と同意を求めると、九十九警部が急に顔を曇らせた。
「ただ…」一転して疲れ切ったようなため息を漏らした。「任同して問い詰めるにしても、あの謎を解かないことには、シラを切られておしまいになる…」
「あの謎?」
ふたりの刑事が顔を見合わせた。どこまで情報を明かしていいか一瞬迷ったようだが、警部がすぐに覚悟を決めた様子で頷いた。
「相馬から当時の状況を詳しく説明させましょう」
これこそ待ち望んでいたギブ・アンド・テイクだ。警部が目で合図すると、相馬刑事がまた部屋を出た。しばらくして、資料を持って戻ってきた。
彼は「うほん」と咳払いをすると、詳しく説明を始めた。
その内容は次のようなものだった。
事件当日の午前二時半ごろ。太田明子はいつものように寝室で就眠していた。すると、ドンという、何か妙な音がして、目が覚めた。銃声にしては妙にくぐもった感じだったと、あとで証言している。これは後の解剖による死亡推定時刻とも一致する。
胸騒ぎを覚えた明子は、寝まきのまま夫の書斎兼寝室へと駆けつけた。彼女の部屋から廊下を挟んだ斜め向かいだ。部屋の外からドアを叩いた。しかし、返事がない。明子はしばらくドンドンと叩き続けた。ケータイから書斎の電話に連絡したりもした。これは後に通信会社の記録からも事実と確かめられる。
こうして、明子は夫を起こそうと、三十分間ほど奮闘したという。しかし、反応がないので、諦めて警察に連絡した。しばらくして、派出所の警察官二名が到着。明子は「本人しか登録していない指紋錠なので合鍵がない」と説明する。今度は警察官たちがドンドンと乱暴にドアを叩いた。しかし、反応は皆無。何か事件性を感じさせるとして、彼らは署に応援を求めた。他の警察官も続々と駆け付けた。ひとりが梯子を使ってバルコニーに上るも、外から窓は開かない。ハンマーで突き破ろうかという話も出たが、明子が防弾の上に特殊フィルムを貼り付けたガラスであることを説明。「主人がライフルの弾も貫通しないし、ハンマーでも叩き割れないと自慢しておりました」と言うと、見送られた。
すったもんだの末、指紋錠のメーカーに連絡して、急きょ技術者を派遣してもらうことに決まった。一時間以上も経って、寝起きで不機嫌そうな担当者が車で駆けつけてきた。「話は聞いてます」とだけ言って、あとは終始無言で作業を始めた。彼は錠のカバーを外すと、持参のノートパソコンをコネクトし、何やら打ち込み始めた。しばらくして、カチリという音と共に電子錠が開錠した。
結局、書斎のドアが開いたのは、通報から約二時間も経った午前五時ごろだった。
警察官たちが一斉に中に踏み込むと、ベッドに横たわった太田善四郎が無残な様子で死んでいた。一見したところ、猟銃での自殺である。明子はその場で突伏して号泣したが、現場保存のため、警官がすぐに去らせた。直ちに現場鑑識が始まった。衆人注視の中、明子が怪しい動きをしたり、部屋から何かを持ち去ったりした形跡は一切なかった。
遺書は机の上にあった。「もう疲れた。あとをよろしく」という簡単な文面だった。後の筆跡鑑定の結果は本人で、遺書からは指紋も検出された。
鑑識の結果、善四郎が部屋で誰かと争った形跡はなかった。彼はベッドに仰向けに寝転んだ状態で、趣味の猟銃を手にとり、顎に銃口を当てていた。左手で銃身を掴み、右手の親指を押す形で発射していたので、引き金を「ひく」という表現は正確ではない。それぞれの手にはちゃんと硝煙反応があり、それは銃口からの距離とも整合していた。散弾は顎から頭頂へと突き抜けていた。当然、頭頂部には大穴が開き、その部分の骨片は粉々に砕け散って、ヘッドボードには散らばった脳味噌が付着していた。
ここで突然、九十九警部が横から口を挟んだ。
「仏様の遺体写真をご覧になりますか?」
「…遠慮しておきます」
相馬警部補が説明を再開した。
善四郎の死体は、現場の状況も調べた検視官による見分と、司法解剖を担当した監察医による検死を経た。いつ、どんな方法で絶命したのか、死因等が究明された。その結果、事前に薬物やアルコールを摂取した形跡はなく、首を絞められた索溝もなかった。身体には外傷・内出血の跡もなく、心臓麻痺その他の病状を起こした形跡も認められなかった。よって、死因は頭部の損傷以外にないと考えられた。
さらに、捜査の進展につれ、「何者かに射殺された」という可能性が成り立たないことが分かってきた。玄関の防犯カメラはいかなる不審者の出入りも記録していなかったし、遺書にも本人の掌紋があった。死亡推定時刻は警察官が到着する三~四〇分前、つまり明子が銃声らしき物音を聞いたと証言する時間と一致していた。指紋錠を開けた技術者は、登録者が善四郎一名だけなのは間違いないと断言した。しかも、キーは最新型で、ゼラチンなどで作った偽造指紋も見破るという。
「これは自殺だろう」捜査に関係した誰もが次々とそう口にし始めた…。
相馬刑事の説明を黙って聞いていた裕美は、内心圧倒されていた。
説明が終わっても、口を開くことができなかった。これでは誰が考えても密室内での自殺ではないか、と思った。もしかして、自分が勘違いしていたのかもしれない。
「このように、ほとんど自殺で片付けても問題ないようなケースなのです」九十九警部が大きなため息をついた。「事実、他の班だったら、そうしていたかもしれません。いや、われわれの班でも、他殺説よりは自殺説に傾いています」
(もしかして、私が考え違いしていたのかもしれませんわ…)
そんな言葉が咽のところで引っかかっていた。すると、白髪の警部が真剣な顔で「しかしっ!」と、いきなり声を張り上げた。続くセリフでは、普通の口調に戻っていた。
「私どもにはどうしても引っかかる点があったのですよ…」
部下に目で合図した。相馬警部補は頷くと、手元に置いた資料の束から、ふいに市販の便箋集を取り出し、裕美によこした。
手書きの手紙を書くときにおなじみのものだ。
「これが太田氏の部屋にあった便箋集と同じものです。試しに、ここから一枚を取り出してもらえませんか」
縦書きの便箋集は、紙の上の方が糊付けしてあるタイプだ。裕美は言われるまま、そこから一枚の紙を指で摘まんで、端からスライドさせるようにして切り離した。
「誰でもそうやって紙を引き抜きますよね」と、九十九警部。「すると、少なくとも人差し指と親指の指紋が紙に付きませんか?」
「ええ、たしかに…」
「ところが、無いんですよ、太田善四郎の遺書には」
紙をつまんだ痕跡がない? いったい、どういうことだろうか。
「つまり、手袋をはめた手で紙を切り離した、ということでしょうか?」
「あるいは箸でつまんで器用に切り離した、とかね。もっとも、そんなことをする人がいるとは思えませんが」
「でも、遺書には当人の指紋が付着していたのでしょう?」
「こんなふうに付いていたんですよ」九十九警部補は左手で紙を押さえ、ポールペンを握った右手で文字を書いてみせた。
右端の一行目に、遺書の文字が再現されていく。左の手の平は紙の上に乗っかっているが、右手は常に欄外に位置している。つまり、左手の指紋が転写されるわけだ。
「変ですねえ…」裕美も異様さに気づいた。「つまり、太田氏は手袋をはめた手で便箋集から一枚を切り離し、次に手袋を脱いで、短い遺書をしたためた、ということですか?」
「そうとしか考えられないんですよ」
「とても不可解な行動ですよね」
「でしょう。しかし…」九十九警部の目が鋭く光った。「死人の手を操ったと考えると、ちゃんと説明がつくんですよ。こんなふうにね」
警部は横にいる相馬刑事の左手首を掴むと、それをスタンプのように紙に押しつけた。
言わんとすることが分かった。裕美は再度、便箋集を手にとり、一枚の紙を外してみた。やはり、紙の下を摘まんで、やや力を入れてスライドする必要がある。そうやってはじめて、のり付け部分を剥がすことが可能だ。
「たしかに、紙を抜き取る作業は、死人の手じゃできないですね。ですが、筆跡鑑定の結果については、どう説明なさるおつもりですか?」
「わずか十数個の文字ですよ。善四郎のノートやメモ帳が一冊でもあれば、いくらでも拾えます。私は書斎を少し調べてみて、彼が相当なメモ魔・手書き魔である事実を知りました。あとは半透明紙やライトボックス(*蛍光灯を内蔵したケース)があればいい。どちらも画材屋でそろえることができる。つまり、遺書に関しては偽造可能なんです」
「なるほど…」裕美は感嘆した。
筆跡鑑定の結果はたしかに本人だ。紙には本人の手の平の指紋も付いている。しかし、本人が紙を摘んだ跡がない。ベテラン捜査官はそこに疑惑を嗅ぎ取ったのだ。
だが、裕美は自信を失いかけていた。正直、ここまで自殺の体裁が整っているとは思いもよらなかったからだ。死の状況を詳しく知ることができたのは収穫だったが、科学捜査レベルで自殺の可能性が高いと見なされていることは、大きな壁だった。
己の甘さを思い知らされた気がした。もしかして、自分が軽率だったのだろうか。
原点に立ち戻ってみる。元はとえいば、自分たちの報告書が、明子に殺人を決意させたかもしれないのだ。むろん、他殺を裏付ける直接証拠はない。しかし、状況証拠のレベルでは十分に怪しいといえる。自分たちとしては、依頼主の仕事をしただけだが、それでも気分が悪いのはたしかだ。今回の件には犯罪が隠れているかもしれない。そう考えると、自分のやろうとしていることが決して無駄ではないと思い直すことができた。
だが、仮に自殺が偽装だとしたら、まさに「密室殺人」である。これで少なくとも、捜査当局がなぜ好意的かという理由ははっきりした。裕美と同じように、九十九警部も本能では他殺だと直感している。だが、彼らにも解けないのだ、この謎が。
おそらく今まで散々、苦労したに違いない。七転八倒している最中に、運よく自ら協力を申し出てくれる探偵が現れた、というところではないか。要するに、利用できるならば、探偵であろうが何であろうが利用したいというのが本音だろう。
なるほど、好意的なわけだ。だが、乗りかかった船である。裕美としても、これからはそれを納得づくで彼らと付き合っていかなければならない。
「ところで…」口を開いた時には、裕美の腹はすっかり座っていた。「警部は浮気相手の林達郎についてどう思われますか?」
「ぜひとも調べてみる必要がありますね。あれ(ルビ)が偽装だとしたら、女ひとりで何もかもやるのは無理でしょう。協力者がいたと考えるべきだ。もしかして、こちらのほうが突破口になるかもしれない」
暗黙の協力関係が築かれるのに、一瞬のアイコンタクトがあれば十分だった。
裕美はハンドバッグから報告書の一部コピーを取り出した。
「彼の簡単なプロフィールです。住所と勤務先程度は把握しています」
「ありがたい。私どもは、まず事件当日、彼が何をしていたのかを調べてみますよ」
「では私どもは」ニコリとした。「彼の過去を調べてみようと思いますわ」
九十九警部が身内・仲間に向けられる種類の笑みを浮かべた。裕美は立ち上がった。自然と両者の手が伸び、テーブルの上でかたいブリッジが築かれた。
警視庁を出るなり、裕美はケータイを取り出した。藤井源之助を呼び出す。
「あっ、源さん。ちょっとお願い。例の林達郎のことを、もっと突っ込んで調査してほしいの…」
女探偵が去ったあとも、ふたりの刑事はしばしその場にたたずんでいた。九十九はそれまで我慢していたタバコに火を灯した。
「おかげさんで、今回の事件は、少なくとも動機面では苦労しなくなったな」
「ええ、非常に分かり易い構図(ルビ:え)ですね。明子にしてみれば、不利な条件で離婚を強いられることが確定していたわけですから、先手を打つ以外に道はありません」
「夫さえ『自殺』してしまえば、財産はまるまる彼女のものだ。ほとぼりが冷めたころに浮気相手と再婚すればいい…」
「やはり他殺の線で、調べ直さなくてはなりませんね」
この件に関しては、未だに捜査本部の設置には至っていない。自殺か他殺かはっきりしないからだ。殺人犯はよく遺体を自殺に見せかけようとするので、このような境界型の事件は少なくない。ただ、ほとんどの場合、ベテラン捜査員がすぐに偽装を見破る。時間のかかるケースでも、科学捜査が決着をつける。今回のように遅延する例は珍しい。
係の中では自殺説と他殺説とに見方が割れていた。昨今は自殺説に傾きつつあったが、それを今回の情報提供がひっくり返したといえよう。
「それにしても、少し狐につままれたような気がせんかね?」
「なにがです?」
「今の奇特な女性のことだよ」
今回、直接連絡が来たのは刑事部の一課長からだが、バックにはサッ庁の高官がいるという。その時点で無下に扱うことはできないわけだが、相手が元警察官僚ということで十分に信用が置けると判断した。そのような経歴をもつ女探偵に個人的に興味もあった。
なにしろ、事件に関する情報提供をしてくれるというのだから、利用しない手はない。捜査が行き詰っていることは明らかだった。探偵であろうが何であろうが、行き詰まりを打破してくれるなら、猫の手も借りたいくらいだ。
だが、プロの面子がある。「協力を」とか、「手を貸してほしい」などとは口が裂けても言えないし、実際、言わなかった。
しかし、彼女は察してくれたようだ、こちらの苦しい立場を。
もっとも、それ以上に、実際に会ってみて、彼女のパーソナリティに引かれる部分が大きかった。あの強い意志を秘めた瞳を見た瞬間に、不信感は雲散霧消した。長年、様々な人物を射抜いてきたこの眼が、この女性は絶対的に信用できる人間だと判断した。
「なにしろ、彼女は自分に何の得にもならないことをやろうとしている。調査の成果がすべてわれわれに持っていかれることも承知しているんだ」
「世の中には変わった女性もいるもんですねえ…」
「まったくだ」
太田明子は自分の寝室に掃除機をかけていた。あの事件以来、いったい何度目だろうか。そうせざるをえない衝動のようなものが未だに収まらないでいる。今では寝室はおろか二階で眠ることすらできないため、一階の和室に布団を敷いて就眠している。
当初、犯罪性が疑われたのか、夫の死体は死因究明のため司法解剖に回され、その後にこちらに引き渡された。葬儀では、ほとんど針のむしろ状態だった。周囲は敵だらけ。親戚たちはあからさまに彼女を疑っていた。誰もが冷たい、射るような視線をこちらに向けてきた。しかし、資産が自分のものになると思えば、なんでもなかった。しょせん負け犬の嫉視だと思えば、むしろ勝利感から含み笑いすらこみ上げてくるのだった。
(しばらくは、おとなしくしていよう…)
改めてそう自分に言い聞かせた時だった。突然、玄関のインターホンが鳴った。掃除機のスイッチを切り、応対に出る。テレビホンの液晶画面に映っているのはコートを着たふたり組の男だった。頭の禿げたほうには見覚えがある。たしか…。
「恐れ入ります、警視庁の相馬と申します」男はニコニコとして挨拶した。「ちょっと気になったことがありまして、おじゃまさせてもらってよろしいでしょうか」
「はあ…」
気が進まないが、断るとかえって疑われる可能性がある。とりあえず、愛想はよくしてふたりの刑事を招き入れた。相馬はペコペコと何度も頭を下げながら、突然の訪問を詫びた。どうやら、この分ではたいした用事ではなさそうだと安堵した。
刑事が調べたいと言ったのは夫の書斎だった。指紋錠は業者によって解除されたままなので、事件以来、自由に出入りできる。明子はドアを開け、「どうぞ」と言った。
一応、一緒にいて監視することにした。ふたりの刑事の動向を背後から見守る。刑事たちはなぜか本棚に直行した。その手には写真が握られている。
突然、心臓がバクバクと高鳴り始めた。
刑事たちは写真と見比べながら、本の背表紙を順にチェックし始めた。
「あのう」相馬が振り返った。「この辺りに黄色いファイルがあったと思いますが」
「はあ? 存知ませんが」
じっと顔を覗き込まれた。
「本当ですか?」
「もちろんです」自然と語気が強まった。「ここは夫の趣味のスペースでしたし、私は全然タッチしていなかったもので」
「変ですねえ…」
といって、またこちらの顔を見つめる。今度ははっきりと疑わしそうにしていた。見透かされているようで、視線が苦痛だった。
「この写真は」相馬がそれを掲げてみせた。「旦那さんが自殺なさった直後に撮ったものなんですよ。写真にははっきりと黄色いファイルが写っているんですがねえ」
「ああ、もしかして!」パンと手を合わせた。「そうそうっ、事件の後にここを毎日のようにお掃除していまして、その際に本棚も少し整理したような覚えが…」
「整理したというのは、本やなんかを捨てたという意味ですか? それにしては、その他の本なんかは、写真と位置が変わっていないように思えるのですが」
「…そのう、それはちょっと…よく覚えていないものですから…」
ふたりの刑事が顔を見合わせた。相馬がまた笑みを浮かべた。
「まあ、旦那様が突然亡くなられて、奥さんも相当なショックを受けておられた時期だと思います。記憶が曖昧になのは仕方がないでしょう」
どうも失礼しましたといって、刑事たちは帰っていった。玄関の鍵をかけた後、そのままくるりと背を向け、ドアにもたれかかった。気づけば、ガクガクと膝が震え、全身に冷や汗をかいていた。手で額の汗をぬぐった。
しくじった、と後悔が襲ってきた。刑事があの浮気調査の報告書を見つければ、当然こちらに疑いを向けてくる。だから、一刻も早く証拠となるものを隠滅しなければならないという強迫観念から処分してしまった。だが、今にして思えば何も慌てて処分する必要はなかったのだ。極論すれば、刑事の目に留まっても堂々と開き直ればよかったのだ。
(もしかして、刑事は他殺を疑っているのだろうか…)
ぞっとした。大きくため息をついて、胸のつかえを吐き出す。ポケットからケータイを取り出し、メールの着信履歴を開いた。
〈念のため、しばらく姿をくらます。連絡も絶つ。よろしく〉
その事件直後のメールを、履歴から消去した。
邸宅を出た相馬警部補はニンマリとしていた。
(われ奇襲に成功せり)
覆面パトカーに乗り込むなり、ケータイを取り出して九十九警部に連絡を入れた。
「係長、例のファイルはありませんでした」
「そうか。じゃあ、明子が処分しちまったんだな」
「としか考えられません。シラを切っていましたが、もの凄く焦っていましたよ。あれはやっぱり何か隠していますね」
「よくやった」
「で、そっちはどうですか?」
「こっちも奇襲は成功だ。林達郎はかなり慌てている。最初にわれわれの姿を見た時、顔面蒼白になった。この焦り方はちょっと普通じゃないぞ」
今回、第六係は、明子が自宅に、林が勤務先にいることを確認してから、同時奇襲をかけた。事前に対応を考えることのできる暇と、一方から一方へと連絡を入れる暇を与えさせないためだ。九十九たちは内神田にあるアーク中山ビルを「急襲」した。そこには明子の浮気相手である林達郎の勤務先「芙蓉貿易」があったのだ。
リーダーの九十九豊が刑事には珍しく決して怒鳴ったり、怒ったりしない性格のため、第六係は捜査一課内で「泣く子もなつく九十九一家」などと呼ばれている。
九十九たちは事件当日の林の動きを調べ始めた。九十九一家は今、大きな山を掘り当てたかもしれないという予感に沸いていた。
すでに夜十一時を回っていた。事務所で残業しているのは裕美一人だ。
ここに依頼に来た時の太田善四郎の様子を思い出していた。あれほど豪快に笑う精力の塊のような人物が「疲れた」などと言い残して自殺するだろうか。検視官も、監察医も、彼の死を自殺と判断している。彼らはプロ中のプロだ。しかし、裕美の直感は違うと訴えていた。たしかに彼は人格者ではなかったが、だからといって殺されねばならない理由はない。人を殺してのうのうと生きている者がいるとすれば、必ずや見つけ出して法の裁きを与えねばならない。それが、あの元気だった依頼者への、彼女のなりの弔いだ。
とはいうものの、先ほどから思考は堂々巡りを繰り返していた。
そもそも、なぜ「散弾で頭を吹き飛ばす」という派手な“自殺方法”でなければならなかったのだろうか。偽装を画策した側にとって、単にあれがベターな方法だったからだろうか。それとも、何らかの必然性があったからだろうか。つまり、どうしてもあの方法でなければならない何らかの理由や意味があったのだろうか。
裕美の脳裏に一つのイメージが浮かんできた。書斎に置かれていたのは、たしかダブルベッドだった。当日、妻が一緒にいたのだ。深夜の二時を過ぎてから、明子だけがそっと布団を抜け出した。夫が熟睡しているのを確認する。それから夫にうまく猟銃を持たせて、さも自殺しましたというふうに引き金を引いた。それから部屋を出て、いかにも私は入れませんという演技を、警官たちの前でしてみせて…。
と突然、太田氏の言葉が脳裏に蘇ってきた。
「今日から書斎のほうには妻も絶対に入れないようにします」
考えてみれば、浮気の証拠を押さえ、離婚に動き出してからは、身の危険を感じるのは夫のほうだ。当然、警戒していたはずである。
(ああ、今日は駄目ね…)
裕美は諦めると、店じまいをした。事務所を施錠し、近くに停めてある愛車のプリウスに乗り込む。自宅は下北沢にある賃貸マンションだ。
だが、運転中も、気がつけばこの件に関して考えごとをしている自分がいた。裕美は急に方向を変え、三鷹のほうへと向かった。
太田邸は静まり返っていた。少し離れたところに車を停めた。夜に見ると、また風景が違って見える。中には入れないので、周囲をうろついた。ほとんど不審者である。
豪邸は角地にあった。表の道路に面している側が庭と玄関だ。二階部分には、例の書斎とバルコニーがある。一階の部屋には明かりが点っていたが、二階は真っ暗だった。東隣の家との間に小さな道があり、家の裏手にある玉川上水沿いの歩道と直角に交わっていた。間に挟まれたその小道には電柱が一本建ち、ランプが頼りない光を発していた。裕美はそこを通って、家の裏手に回ってみることにした。刑事の話からすると、ちょうど邸宅の角にあたるところが明子の部屋らしく、例の書斎とは廊下を挟んで斜め向かいに位置している。その角部屋には、小道側と川側にそれぞれ窓があり、ぴたりとカーテンが閉じられていた。裏手に面した彼女の部屋からは、さぞかし眺めがよいことだろう。
舗装されていない玉川上水の歩道に出た。木々が黒々としていた。気持ちのよい川のせせらぎをBGMとしながら、裕美はしばし豪邸の暮らしに想いを馳せた。
刑事たちと会ってから、一週間がすぎた。相馬警部補から連絡があった。近くによるついでに、事務所を訪ねたいという。
訪れた相馬刑事の口調や表情は興奮を隠しきれないでいた。太田氏の書斎の本棚からは、見事にIHQ社の報告書だけが消えていたという。
「それについて尋ねた途端、明子は目を泳がせ、かなり動揺した様子でした。当初はこわばった表情で否定しましたが、しまいには顔が紙のように白くなっていましたよ」
「やはり、彼女が本棚から抜き取ったとしか考えられませんわね」
「あれほどまでに動揺するということは」相馬刑事がお茶をすすった。「あの報告書がなにかよほど後ろめたいことと関連しているからではないでしょうか」
今の段階では憶測は禁物だが、そうだろうなと裕美も思った。お茶に口をつけた。
「ところで、林のほうはいかがでしたか」
今度は一転して刑事の表情がくもった。結果がかんばしくなったことが一瞬にして見てとれた。
「実は、林達郎には完璧に近いアリバイがありました」
「アリバイが?」
「ええ。太田氏の死亡推定時刻は朝二時半ごろですが、その日、林は朝の三時までオフィスにいたのです」
「えっ? それはたしかですか?」
「はい…」失望を隠しきれない様子だ。
「林が朝の三時まで仕事をしていたということは、どうやって証明されたのですか?」
「それが…」
相馬警部補ががっかりした表情で説明を始めた。
明子の浮気相手である林達郎・二十七歳の勤務先は、海外代理店業務を手広く行う「芙蓉貿易」だ。オフィスは千代田区内神田一丁目にある「アーク中山ビル」の五階に位置している。この十階建ての中規模ビルは、都営新宿線の小川町駅を降りて徒歩数分、本郷通沿いにあり、周辺はいわゆるオフィス街だ。
林が事件当日、その時間まで仕事していたことは、このテナントが独自に付けているセキュリティ機器と、ビルが備えている同機器の両方から裏付けられた。
まずは前者だ。芙蓉貿易では社員の入退室がすべてチェックされている。オフィスのドアはすべて電子錠でロックされ、パネルにIDカードをかざさなければ解除できない。実は一般の社員は知らないが、この時の操作は総務部のパソコンに刻々と記録されており、役員か又は総務部長でなければ閲覧できない。IDカードは固有のものなので、「誰が何時何分に入退室したか」がたちどころに分かる仕組みになっている。同社では、社員の「動態管理」や「情報漏えいの防止」などの名目で、その他にもネットの閲覧履歴やメールの内容まで監視されている。
「その日は林が残業組の最後の一人でした。終電直前に退室した二番目の残業者は『残る居残りは林だけでした』と断言しています」
「それが総務部のパソコンで証明されたというわけですね」
「はい。当初、われわれは、その二番目の残業者が退室して以降、林が誰かを身代わりにオフィスに招き入れたのではないかと疑いました。彼にIDカードを手渡し、最終退室の際の警備セットの方法を教えておけば、『自分がそこにいた』というアリバイが作れるわけですからね。ところが、ドアの開錠操作記録を調べてみると、その二番目の残業者が解錠して以降、林が最終退室する午前三時ごろまで、ドアが開いたという記録がない…」
「なるほど…」裕美も思わずうなった。しかし、すぐに突破口が思い浮かんだ。「こういうのはどうでしょう? 二番目の残業者が帰宅のためにドアを開けたのを見計らって、それが閉まりきる前にドアストッパーか何かをかましたのです。その時に、あらかじめ共用部のトイレなどに潜ませておいた替え玉と素早く入れ替わった…こうすれば…」
「否定です。そこがまさしく、ビルのセキュリティと関係してくるのですよ」
相馬がそれについて解説を始めた。
アーク中山ビルでは、正面玄関、エントランスホール、通用口、四台のエレベータ内に監視カメラが設置され、二十四時間録画している。
正面玄関は夜の九時に閉まるので、それ以降から朝の七時までは通用口がもっぱらの出入り口になる。そこのカメラが、朝の三時に林が退館する様子を記録していた。
また、ビルには警備員が常駐しており、二時間おきに巡回が行われている。彼らは屋上から順に下に降りていき、共用部を念入りにチェックして回る。最後にビルの外周・外観をチェックして管理室に戻る。
当日、夜十時、十二時、朝二時…と巡回した警備員は、トイレ・給湯室・廊下・階段・一階ホールなどの共用部には「誰ひとりとしていなかった」と証言している。
「うーん…なるほど…」裕美も腕を組んで考え込んでしまった。
だが、またしてもあること(ルビ)を思いついた。調査のためには、時としてセキュリティを欺くことを要求される探偵ならではのしつこさかもしれない。
「通用口のカメラは一台だけですよね」
「はい」
「どっち(ルビ)を向いていますか?」
「あっ」相馬刑事の顔がほころんだ。「さすがに、いいところに気づかれますね。ご想像の通り、入館者を監視しています」
「つまり、録画には、退館する林達郎の後姿(ルビ)が映っていた、ということですね」
「そうです」またニコリとする。「探偵さんのおっしゃりたい意味はよく分ります。ただ、その日の朝九時前には、正面玄関のカメラが、出勤してくる林の姿を、正面からもろに記録していました。このことから、その後姿は、やはり本人であると考えられるのです」
「林はタクシーで帰宅したのでしょう? その記録はあるのですか?」
「彼はバイクか、マイカー通勤なんですよ。ビルの近くに勝手に停めているそうです。当日、朝三時に残業を終えると、そのまままっすぐ練馬にある自宅アパートに帰ったと言っています」
裕美はため息をついた。
どうやら、誰かと入れ替わるという芸当は、不可能なようだ。つまり、林達郎は、太田氏が死んだ時間帯、本当にオフィスにいたらしい。そもそも、すべては、太田氏の自殺を他殺だったと仮定した場合、林が何らかの形で犯行に関わった可能性がある、という推理ないしは思い込みに基づく。その前提が崩れてしまったということだ。
「ただ…」と刑事は言った。
その表情が急に微妙というか、複雑なものへと変化した。林のアリバイの話にはまだ続きがあると、裕美は直感した。
「どうしても、疑問というか、引っかかる点があるのも、たしかなのですよ…」
「それはどういった点ですが?」無意識に身を乗り出した。
「一つには、われわれの訪問を突然受けた際の、林の焦り方が尋常ではなかったということです。九十九警部などは『隠していた犯行がバレてしまったと泡を食った際の犯罪者特有の引きつった表情』とまで形容していました」
「実に分かり易い例えですね」
「そして、もう一つが」刑事はそこでふいに言葉を止め、腕を組むと、まるで自らの禿頭を見るかのように目を上にやった。「まあ、実に些細なことと言えば言えるのですが…」
「些細な?」どうやら相馬氏自身はあまり賛同している内容ではないらしい。
「はい…。いえね、またしても、引っかかっているのは、例によってうちの係長なんですがね。林が帰宅する際に『なんでエレベータを使わなかったのか?』と、しきりに言うのですよ、フフフ…」
「エレベータを?」裕美の思考が突然、急発進する車のタイヤのように回り始めた。「ビルの監視カメラは、エレベータの籠内にも設置されているのでしたよね」
「ええ」といって、刑事はさして興味なさそうにお茶に手を伸ばした。
裕美は帰宅者の立場になってイメージしてみた。
「朝三時ごろ、五階にあるオフィスを退室し、警備セットをかける…。普通なら、次にエレベータの前に立ち、ボタンを押して呼び出しますよね…。そして、すぐに籠が上ってきて、そのドアが左右に開いて…」
裕美の頭の中ではチンという音が鳴ってドアがスライドする様子までが再現されていた。そして、籠内に足を踏み入れると、天井には…。
「きっと顔を映されたくなかったから、エレベータに乗らなかったのではないでしょうか。つまり、通用口側のカメラに後姿が映っていた男は…」
「林達郎本人ではなかった、ということですかっ」刑事がお茶をせき込みつつ勝手にあとを続けた。裕美が頷くのを見てとると、「いやあ、驚きましたねえ。うちの係長とまったく同じ推理をおっしゃるとは!」と頭をかいた。
「五階のオフィスを出た者が通用口のカメラにいきなり現れたということは、階段を使って下りたということですね。二、三階の勤務者がそうするなら不思議ではありませんが、五階の者がエレベータを省くことは不自然ですよ。ましてや深夜。エレベータの使用頻度は極端に少ないはずです。呼び出しボタンを押して待たされるということはないはずです。よって、エレベータに乗れない、乗りたくない理由があったとしか考えられません」
「うむ。林本人は『急いでいたので、一階に止まっているエレベータを呼び出すよりも先に、階段を使って下りることにした』などと話していましたが…」
変と思えば変だし、正常と思えば、そう思えなくもない。微妙である。
「ちなみに、これが通用口のカメラに映っていた林の姿です」
相馬刑事が持参のノートパソコンを開いた。数回、クリックすると、動画が現れた。カメラは天井から斜め下方に位置するスチール製のドアを捕えている。画面の左には管理室の受付窓口があるが、カーテンで閉ざされていた。午前3時を少し過ぎたころ、画面の手前から、ふいに後姿の退館者が現れた。男の髪は長めで、部分的にふわふわとパーマがかかっている。身長は一八〇センチくらいで、やや細長い体格だ。ラクダ色のコートと黒いズボン、革靴を身に付けている。右手には茶色い鞄をぶら下げている。
「で、これが同じ日の九時前に入館してくる林の姿です」
刑事がクリックする。今度の動画は玄関に取り付けられたカメラの録画だ。サラリーマンやOLが次から次へと出勤してくる。「ほら、これです」と、刑事がそのうちの一人を指差した。それは裕美も浮気調査で知っている林達郎の顔だった。服装は帰宅時と同じ。パッと見では、ふたつの動画は、同一人物の裏と表を映したものにしか見えない。
「うーん…」裕美は思わずうなってしまった。
だが、うなりつつも素早く自己分析をしていた。自分が今、この二つを同一人物と判断した根拠は何か。まず髪型。次に体格。あとはコート、ズボン、靴、カバンなどだ。
「同一人物とは必ずしも断言できないと思いますね」我ながら自信なさげな口調だ。「要は、体格が似ていればよいのです。髪型はカツラを被れば真似れます。あとは服装と持ち物ですから、同じものをそろえればいいわけですし…」
「ですが、仮にこの二つが別人だったとしても、では林はどうやって入れ替わったのでしょうか? うちの係長も、その点でうんうんと考え込んでいるのですよ…」
「まったくです。その謎を解かないことには…」
相馬警部補とのミーティングのあとも、裕美はずっと社長席で考え込んでいた。
何のことはない。謎が二つに増えてしまった。密室の謎に、アリバイの謎である。
「一難去らないうちに、また一難か…」と、思わず独語してしまう。
ふと、何か言いたそうな専務の大塚と目が合う。「ほらほら言わんこっちゃない」という表情。だが、彼は何も言わずに、つんと眼鏡を直すと、また経理作業に戻った。
(そういう態度のほうが辛いのよねえ…)
他のメンバーは仕事が山積みで、今もフル稼働だ。むろん、自分だってそうだし、決済や雑事が山のようにある。だが、実際、推理に時間を費やせるのは裕美しかいない。
まるで咽に刺さった小骨だった。
仮に太田善四郎の死が「他殺」だとすれば、いわゆる密室殺人である。やり手の経営者で、精力が皮を被ったような人物相手だ。女一人で自殺を偽装するのは難しいだろう。必ず協力者がいたと考えるべきだ。しかし、林以外の人間に協力を頼めば、それは即、一生分の弱みを握られることを意味する。そんなリスクを犯すとは思えない。共犯者がいるとすれば、やはり愛人の林だと考えるべきだ。しかし、太田善四郎が猟銃で頭を打ちぬいたまさにその時、林は神田のオフィスで残業していた、とされる。
考えれば考えるほど、九十九警部と同じ点に引っかかりを覚えた。なぜ遺書には指紋が残っているのに、その紙を便箋集から切り離した時の指紋がないのか。なぜ五階のテナントで働く者が、深夜の帰宅時にエレベータに乗らなかったのか。前者に関しては、警部は「誰かが死人の手を操ったからではないか」との推理を披露した。後者に関しては裕美と同様、籠内のカメラに顔を映したくなかったからではないかと推理した。
その時にアリバイを作ったとすれば、協力者がいるはずだ。むろん、カメラに後姿をさらすのだから、体格的に男のはずだ。協力者を先に見つけ出すことが有力な突破口になりそうな気もするが、どうやったら洗い出すことができるだろうか。
裕美も九十九警部も、本能のレベルでは犯罪だと直感している。だが、それを証明するには、隠されているであろうトリックを暴かねばならない。
(座って考えるばかりじゃラチが開かないわ…)
裕美は受話器をとり、先ほど去ったばかりの人物に連絡を入れた。
「無理を言って本当にすみません」
裕美が頭を下げると、相馬警部補は慌てて被りを振った。
「と、とんでもありません。捜査を手伝ってもらっているのだから、迷惑どころか、逆に私のほうからお願いしたいくらいですよ。アハハハ…」
後頭部に手をやってなにやら照れている警部補に対して、裕美も笑みを返した。
「まあ、助かりますわ」
親密そうなふたりの様子を見て、一瞬、むっとした表情を見せた鏡義雄に気づいたのは風間雪だけだった。彼女は口を手で押さえ、ぷっと吹き出した。
四人は内神田にあるアーク中山ビルの真ん前に立っていた。十階建の同ビルは角地にあり、ガラス張りの外観だ。本郷通には似たような高さのビルが並んでいる。
とりあえず現場に足を運び、自分の目で確かめてみる…それが調査の鉄則である。鏡と風間の視点も借りることにした。
「事前にアポは入れてあります」相馬刑事が言った。「それじゃ、行きますか」
まず一階にある管理室を訪ねた。通用口の通路に面している。相馬警部補と、七十近い人のよさそうなメガネの管理人とは、すでに顔なじみのようだ。
裕美たちは、相馬刑事から「捜査の手伝いをしてもらっている調査会社の人たちです」というふうに紹介された。三人でお辞儀をした。管理人は愛想がよかった。
裕美はその間にもすばやく管理室の中に目を走らせた。机の上に二台の液晶モニターが並んでいた。画面は四分割されている。左側がエレベータ内、右側がそれ以外の映像の映像を映していた。左はやはり籠に乗り込んでくる人の顔を映し出していた。
管理人からお茶を振舞われた。彼によると、昼間は設備員と警備員が一人ずつ、夜は警備員が一人のみという体制だそうだ。しばらく雑談をしていると、警備員が巡回から戻ってきた。管理人は「ちょっと留守を頼む」と言い、席を立ってキーボックスからマスターキーを取り出した。「じゃあ行きましょうか」と刑事に言った。
全員で七階に向かった。管理人がそこのドアを開けると、がらんとした空間があった。七階のワンフロアがまるまる空き部屋になっている。
「このところ不景気でしてね。ほら、供給過剰でオフィスの空室率が高いというでしょう」
「五階と同じつくりですか?」刑事が訊く。
「まったく同じです。ちょうどこの二つ真下が、芙蓉貿易にあたります。輸入代理業をやっているそうで、いつもダンボールやなんかを出し入れしていますよ」
相馬が裕美のほうを見た。「どうですか」と訊きたげだ。裕美は部屋の中をぐるりと見回して、それから窓のほうに歩み寄った。部屋の三面がガラス張りだ。東側が車の渋滞している表通りに、西側が裏通りに位置している。南側が一方通行の通りだ。
「中から窓を開けることはできないのですか?」
裕美が訊くと、管理人は軽く頷き、東側の一枚の窓に向かって歩き始めた。
「ほとんどは『はめ殺し』と呼ばれる、閉め切りタイプの窓ですが…」
その時、なぜか風間が口を押さえて卑猥な笑みをかみ殺した。
「…中には換気用の回転窓もあります」
管理人は目的の一枚に到達すると、そこのレバーハンドルを掴んで引いた。横幅一メートルはある窓の真ん中を縦軸として、ほぼ六十度の角度で開いた。
「回転窓にはちゃんとマグネットセンサーが付いていまして」管理人は窓枠の端っこを指差した。「この窓をピタリと閉じない限り、退室時の警備セットがかからない仕組みです。ですから、セキュリティのほうは万全ですよ」
人のよい管理人は、自分が質問者の趣旨に応えていると疑わなかった。みんなでその場所の周りに集まった。鏡が「ふーん」などと感心している。
「回転窓はこの一箇所だけですか?」と裕美。
「いえ、三箇所付いています。ここの他に」管理人が南側と西側のガラス窓を順番に指差した。「あそこと、あそこです」
風間が回転窓からやや身を乗り出して、しきりと上下を覗きはじめた。
「なんだあ、簡単じゃん」頭を引っ込めて、裕美のほうを振り返った。「カシラ、いい方法があるよ。ロープでここまで降りてくりゃいいんだ」
「え?」と、その場の全員が固まった。
「簡単さあ。あたしは昔、高層ビルのガラス拭きのバイトをやってたことがあるから、この程度のビルならお茶の子サイサイだよ」
「あのねえ、風間さん、簡単に言いますけど…」と、少し呆れ顔の鏡。
突然、裕美の身体を電流が駆け抜けた。
「ちょっと待って!」裕美はジェスチャーで鏡を制した。「そうよ、可能性としては、十分に考えられるわ。警備員の巡回の隙をついて、林が代理の人物を外から招き入れればいいのよ。入れ替わりに、林のほうはそのロープを伝って地面に下りればいい…」
尋常ならざる表情を浮かべている裕美の顔を、全員が見つめた。
「しかし、入れ替わるタイミングをどうやってうまく図ったのでしょう?」相馬刑事が口を開いた。「相手とケータイで連絡を取り合えば通信記録として残るが、事件当日の林のケータイには怪しい記録がない。あらかじめ時計を合わせたとも考えにくい。というのも、われわれの調べた限り、林は社員全員の残業者の有無を把握できる立場にないからです。つまり、いつ誰が残業をするか、彼には分からない…」
「それは全然、問題ないですね」と鏡。「彼ひとりになったところで、窓際に立ち、何かのジェスチャーをすればいい。外で待機している共犯者は、それを確認してから行動を起こせばいいんですよ」
「おそらく、外から目撃される可能性を考えると、裏通り側の回転窓を出入りに使ったと考えられるわね」
裕美が西側のガラス窓を見やると、みなの視線が続いた。
相馬刑事が管理人のほうを振り返った。
「ここの窓ガラスは、どうやって拭いているんですか?」
「こちらのお嬢さんのおっしゃる通り」と、手の平を上にして風間を指した。「清掃員がロープを伝って下りながら、一枚一枚拭いていますよ。月一でね」
「今度、道具を持参して、あたしがやってみせるよ」風間が張り切った。
「ですが…」管理人が困惑の色を浮かべた。「屋上へ通じる扉は常時、閉鎖されていますよ。警備員の巡回や、屋上の設備点検など、用事のある時以外は開錠しません」
「とりあえず、屋上を見せてもらえませんか?」相馬刑事が頼んだ。
今度は急きょ屋上を案内してもらうことになり、一同はその足で最上階へ向かった。
屋上では、電気設備や室外機、熱交換機などの設備がうなり声を上げていた。その他にも、高架水槽やエレベータ機械室の塔屋などがあり、ごちゃごちゃとしている。
「通常、ここに出入りするのは、どなたですか?」と裕美。
「われわれ設備員や警備員などの内部関係者。あと外部の人では、ガラス清掃員と電気設備点検員、エレベータ点検員が月に一度ずつですね」
屋上の端っこには、低い塀が外周部沿いに張り巡らしてあった。高さが五〇センチ、厚さがやはり五〇センチほどある。みんなで渋滞する表通り側に寄った。
「これはパラペットと呼ばれる、落下防止のための柵というか、堀でしてね」管理人がしゃがんだ。「で、こっちが丸環といいまして」そこに内側向き埋め込んである金属製の輪を手にとった。「ガラス清掃の人たちはここにロープのフックをかけて降りていくんです。もっと高いビルだとゴンドラがありますが、うちくらいだとロープ作業が普通ですね」
裕美が「そうなの?」というふうに風間の顔を見やると、彼女が「うん」と頷いた。金属の輪は二メートル弱の間隔で埋め込まれていた。
パラペットはブリキ板のような金属製のカバーで覆われていた。灰色の塗装がしてあるのだが、劣化して少し粉がふいている。風間がなんとなしに踏みつけて、すぐに足をどけると、うっすらとブーツの踵模様が残ってしまった。
「この仕上げ材を、われわれは業界用語で笠木と呼んでおります」管理人はしゃがんだまま、パラペットの上をパンパンと叩いた。「ほら、触ると粉がついて、指が白くなってしまうでしょう?」実際に触って指の腹を白くして見せた。「これはチョーキングと呼ばれる劣化現象ですよ。もっとも、管理上は何ら問題ありません」
「ほう…」みんなが感心して聞き入っていた。
裕美は何気なしに周囲を見回した。十階だけあって、眺めがいい。大手町や丸の内あたりの高層ビルがすぐ間近に迫って見える。ふと、気づくことがあった。
外から見た時には気にも留めなかったことだが、隣のビルの屋上がまったく水平に並んでいた。いや、それどころか、そのまた隣もそうだった。
裕美がビルの北側に歩み寄ってみると、みんなもぞろぞろと付いてきた。
「向こう二棟のビルも、ほとんど同じ高さなんですね」
裕美がそう言うと、みんなも並んで端っこに寄った。ビルの間隔は数メートルしかない。
「そのようですねえ」管理人はさして関心なそうに応えた。「ちなみに、うちはお隣さんとも仲良しでして、時々、道具なんかも融通しあう間柄ですよ」
「風間さんなら、向こうのビルに飛び移れるんじゃないですか?」
鏡がニヤリとして煽ると、風間は平然としてパラペットに足をかけた。
「やってみせようか?」いきなり身体にバネを利かせた。
「ちょっと、ちょっと…」
相馬刑事と管理人が慌てて彼女の肩を掴んで止めに入った。
「カシラ」刑事から肩を掴まれたまま、風間が振りかえる。「もし容疑者がラペリングしたなら、窓ガラスから靴型がとれるかもしんねえよ」
「なに、それ?」
「懸垂降下だよ。ブランコを使わないやり方さ。ガラスを足で踏んづけなきゃならねえから。ほら、山登りとかでよくやるだろ。いや、ブランコを使ったところで、使い慣れていなきゃ、ガラスを足で蹴ってしまうことも多々ある。経験的に分かるんだ」
「あのう、ブランコって?」専門的すぎて裕美にはさっぱり分からない。
「ガラス清掃の人たちは板の上に座りながら窓を拭くんですよ」横から管理人が助け舟を出してくれた。「それをブランコと呼ぶんです」
「それはグッドアイデアだ」相馬刑事が手をポンと叩いた。「有力な物証になるっ」
靴というのは、たとえ量産品であっても、使いこむにつれ溝に小石を挟んだり、踵が欠けたりして、指紋のように独自の模様と化していく。犯行の特定に大いに役立つ。
「いや、それがですね…」管理人が申し訳なそうにした。「刑事さんが調べられた例の日から数日後には、ガラス清掃が入っています。きれいに拭き取られているでしょう」
その場を沈黙が覆った。
「ちょっと待ってくださいっ。ガラスは拭いたにしても、もしかして…」
裕美がビルの西側に勝手にずんずんと歩いていくと、みんなも慌てて追っかけてきた。ここは裏通りに面している。裕美は管理人が横に並ぶのを待って、尋ねた。
「西側面の回転窓の位置は、どの辺りですか?」
「ええっと、そうですね…」管理人は数メートルほど移動し、ピタリと止まった。「だいたい、この辺りでしょうね」
裕美は管理人が指差した辺りでしゃがんだ。ハンドバックから拡大鏡を取り出し、覗いた。何事かと、みんなが周りを取り囲んだ。
(思ったとおりだ!)
調査の過程で何かを発見した時の、特有の興奮が蘇ってきた。「笠木」と呼ぶらしい金属製のカバーを拡大鏡で見ると、分かりづらいが、微妙に靴の跡が散らばっていた。
「相馬さんっ」
裕美が見上げると、そこには意を汲んで顔を輝かせた刑事の姿があった。
「すぐに鑑識を要請します。ガラス清掃で出入りしている関係者の靴型をすべて調べ上げて、ここに部外者のものが混じっていないかどうか照会してみます」
とりあえず、実地調査の成果はあった。屋上の見学を終え、一同は一階に下りた。裕美の頼みで、隣のビルの管理人を紹介してもらうことになった。
隣の住菱ビルはタイル貼りの概観で、築年数が新しい。高さこそ十階だが、少し幅があるため、床面積はアーク中山ビルの一・五倍あるという。管理人同士が知り合いのおかげで、お隣さんも協力的だった。相馬刑事と裕美が質問を浴びせた。
厚いメガネの管理人は、「うちのセキュリティはとても厳しいですよ」と自慢した。警備員は常時二人体制で巡回は一時間おき。監視カメラの数もアーク中山ビルの倍。むろん、部外者が屋上に上がることは絶対に不可能。
たしかに話で聞く限りでは、警備は万全のようだった。
「あのう」裕美が尋ねた。「この隣はどうですの?」
途端、厚いメガネの奥にある小さな目が軽蔑の色を宿した。
「隣のツノダビルは古くてねえ」見下したような表情で冷笑した。「もう築四十年は経っているんじゃないですか。いわゆるインテリジェントビルじゃないし、セキュリティもスキだらけですよ。取り潰しが決まっていることもあって、オーナーもできるだけ経費をかけたくないらしいんです。消防法などの関係から、とりあえず年寄りを昼間だけ時給制の管理人として置いておいて、あとは問題が起こった時のみ管理センターが対応するという体制ですよ。夏には冷房が故障ばかりしていると、テナントさんがボヤいていました。夜中も扉を自動施錠してますが、暗証番号の管理がルーズで、新聞屋ですら知っている。危なくて、テナントさんもみんな自分で大手警備会社と契約していますよ…」
侵入者の思考や視点を知るためにはどうしたらよいか。
答えは自らが侵入者になりきることである。すると、おもしろいもので、それまで見えなかったものまでが見えてくる。
「だから、今回は刑事さんの協力は仰がないほうがいいのよ」
助手席の裕美は、ワンボックスカーの運転席にいる鏡義雄に言った。
「ほらほら、言ってる間に八時ですよ」
ふたりはそろってボンゴ車を降りた。この時間帯、車は表通りには駐車できないので、一方通行の通りにある公の駐車区画に小銭を払って停めていた。ちょうど本郷通を挟んだ道の反対側にアーク中山ビルがあり、ほぼ全景が見える位置だ。
ふたりともスーツを着込んでいた。事務所ビルの中に失礼する際に、怪しまれないためである。もっとも、普段から、ふたりはこの格好がメインではある。
ふたりはツノダビルのそばに立った。たしかにずいぶんと痛んだビルだが、それでも背広を着た人たちが勤務しているらしい。玄関からは彼らが頻繁に吐き出される。
夜八時。事前の情報通り、警報音と共にビルの玄関シャッターが自動で閉まり始めた。完全に閉まると、音も止んだ。退館者たちが今度は建物の右端にある灰色の通用口から出始めた。時々、入館するサラリーマンやOLもいる。通用口は表からは閉まっているらしいが、彼らは扉の脇にあるパネルで暗証番号をピッピッと押すと、難なく入っていく。
鏡が近寄って、まさに入館しようとしている会社員の背後に立った。コンビニの袋を手に持っている若いサラリーマンだ。鏡は彼の背後に立ち、何気ない様子でボタン操作を観察した。鏡がこっちを見て、OKサインを作った。
「分かりました。7728♯です」
「ご苦労さん。これでトイレに苦労しなくてすむわね」
ふたりはボンゴ車に戻った。次は夜の十時だ。張り込みとはいえ、今回のように事前に情報があると、精神的にも肉体的にも、とても楽だった。交代で食事もとった。
「義雄君、あれじゃない?」
裕美は双眼鏡に目を当て、アーク中山ビルを指差した。屋上でライトの光が動いている。人物は真っ黒で判別不可能だが、巡回の警備員であることは間違いないだろう。
「ちょうど十時過ぎですね」鏡が腕時計を確認した。
そのほぼ三十分後、警備員が今度は通用口から姿を現した。ビルの外周を歩き始める。時々、ビルの上を見上げたり、周囲の植栽の中を覗き込んだりしている。彼はビルをぐるりと一周すると、また通用口の中へと戻っていった。
「さて」裕美は運転席を振り返った。「人通りも減ってきたし、そろそろ行こうか」
「そうですね。ルパンタイムといきますか」
ふたりはまた車を降りた。鏡が後ろのドアをスライドし、中から脚立を取り出した。ツノダビルに向かう。鏡が暗証番号を押した。入り口はあっさりと突破できた。
暗いエントランスで各階テナントの案内板を確認する。時々、エレベータから降りてくる退館者とすれ違う。鏡が脚立を肩に担いでいても、ふたりを疑う者はいない。エレベータで最上階へ上がった。そこから非常階段で屋上の出入り口まで行ってみる。すると、錆びの浮いたドアは、握り玉にサムターンが埋め込まれたタイプで、鍵自体がない。ドアに「部外者立ち入り禁止」と張り紙がしてあるだけ。
「これは必要なかったですね」と言って鏡がポケットから取り出してみせたのは、ピッキングの道具だった。
サムターンを捻って、ドアを開けた。塔屋から外に出る形になった。屋上の設備や配管はどれも塗装が剥げ、赤錆だらけだ。あちこちでキイキイと妙な異音を発している。床のコンクリートの一部はボロボロとして剥がれている。
「地震がきたら大丈夫かしら、このビル…」
「しっ」と、鏡が裕美の袖を引っ張った。
塔屋に寄り添って隠れた。隣の住菱ビルの塔屋のドアから、いきなり制服姿の人影が現れたからだ。時刻は十一時を少し過ぎたころだ。
制帽が妙に後ろにズレた警備員は、屋上に出るなり、思いっきり伸びをした。肩から吊り下げた懐中電灯は消灯のまま。タバコを取り出し、ふかし始めた。腕時計できっかり五分過ぎたことを確認すると、警備員は携帯用の灰皿でタバコをもみ消し、また塔屋の中へ消えていった。ガチャガチャと鍵をかける音を確認して、裕美たちはまた身を起こした。
「なるほど、たいしたセキュリティだ」鏡が皮肉った。
南の方角を見ると、三棟の屋上がほぼ水平に並んでいた。鏡が二一〇センチの脚立を床に置き、広げた。裕美も手伝う。フックをかけると梯子になった。鏡はそれを担ぐと、ビルの端に置いた。次にその場で上着を脱いだ。ワイシャツに装着した安全帯があらわになる。その間、裕美はハンドバックからロープを取り出し、一方のフックをビルの丸環に、もう一方のフックを鏡の安全帯の金具に取り付けた。万一の落下防止策を講じたところで、鏡がビルの端に寄りかかった。そして梯子を力いっぱい持ち上げて、そろりそろりと隣のビルへとスライドさせた。正直、このビルの丸環の固定具合が信用できなかったので、裕美は両手でロープを握り締めた。無事にビルとビルの間に橋は渡された。
「ほとんど泥棒ね、あたしたち…」実際、不法侵入である。
「行きますよ」
と言うが早いか、鏡がその上をひょいひょいと歩き、難なく住菱ビル側へと渡った。
裕美は丸環からフックを外すと、対岸の鏡に向かって投げた。それをキャッチした鏡は、今度は住菱ビル側の丸環にフックをかけ、同ビル側に梯子を回収した。
ここから先は、裕美も手伝うことができない。少し心配になる。
「義雄君、気をつけて…」
鏡は無言で片手を挙げた。彼は梯子を担いで、ビルの反対側の端へと移動した。今度は同じ方法で、住菱ビルとアーク中山ビルの間を橋渡しする。
その間、裕美は時計を気にした。だが、作業に馴れが生じたのか、鏡は最初よりも短い時間で両ビルの橋を渡した。鏡は無事にアーク中山ビルへと渡った。梯子はそのままで、安全帯から外したフックを床に置き、歩き出す。裕美のケータイに連絡が入った。「ポイント到達」とだけ鏡が言った。そこはビルの西側にある回転窓の真上部分だ。
鏡はそのポイントで五分潰すと、今度は一転して逆の手順を始めた。住菱ビルへと渡り、梯子を回収。次に同ビルからツノダビルへと梯子を渡す。裕美は鏡が投げたフックを受け取り、丸環に繋いだ。ふたりして再びツノダビルの塔屋へと戻る。
裕美は左の手首を見た。時間は十一時四十分。
「上出来ね」
裕美の言葉に鏡が少しはにかんでみせたが、すぐにキリリと顔を引き締めた。
「不二子ちゃん(ルビ)のためなら」
「調子に乗らないように」
ふたりはボンゴ車に戻った。自販機で買ったジュースを飲んで、少し休憩する。やがて終電の時間が過ぎた。ふたたび車を出て、アーク中山ビルに向かう。
表通りは依然として車の往来があったが、裏通りは暗く、人影が皆無だった。ふたりしてビルの屋上を見上げ、次に照明の消えた五階を見やった。
「僕らは事前に情報を得ていたから一日の調査ですみましたが、これなら何も知らなくても、数日ほど張り込むだけで侵入に必要な情報を得ることができますね」
「そうね。ここの警備の巡回はしょせんルーチンワークだから、その意志さえあれば盲点を突くことは難しくないわ」
「あとは雪さんがうまくやってくれるのを祈るだけですね」
数日後、アーク中山ビルの屋上で検証会が開かれた。立ち会ったのは先日のメンバーのほかに、九十九警部以下、数名の刑事たちだ。
裕美は刑事たちに向かって、夜間に二棟隣のツノダビルから今の己の立ち位置まで侵入する方法について説明した。
「…というわけで、警備の隙を突いて、ここまでたどり着くことは可能だと思われます」
本当は実際に検証したのだが、それについては触れなかった。九十九警部たちもなんとなく察しているふうだが、とくに言及しなかった。
「それではこれから、うちの風間がロープ降下をご覧に入れます」
風間は頷くと、登山用の大きなリックから、ブランコと呼ばれる板切れやロープ、金具類などを取り出し始め、ドサリと床に置いた。みんながその様子を注視する。
西側は捜査の対象なので、南側のガラス壁面が実験の対象となった。裕美はつい先ほど、内輪で交わしていた会話を思い出した。
「こんな道具をどっから持ってきたんですか?」と鏡が訊いた。
「金物屋にあるけど、これはバイトを辞める時に記念にもらったやつさ」
「本当はくすねてきたんじゃないですか?」
「まあまあ、硬いこと言うなよ」と、風間は豪快に笑った。
裕美の回想の合間にも風間は革ジャンを脱ぎ、セーターの上に安全帯を装着した。
「カシラ。なんなら、ファストロープでやってみせようか? グローブも持ってきたし」
「なに、それ?」
「軍事式の降り方さ。ほら、よくヘリコプターから特殊部隊の兵士がすばやく…」
「普通でいいのよっ、普通でっ」
「オーケー。じゃあ、窓拭き方式でいくね」
パラペットの丸環にフックをかけ、手際よくメインロープと補助ロープを整える。風間の腹の位置には「エイト環」と呼ばれる、文字通り八の字形の金具があり、そこにメインロープが通された。ここで下降を調節するらしい。一方、エイト環の下部穴のほうにブランコの吊りロープのフックをかけ、板を尻に当てがった。命綱だという補助ロープとも身体を連結すると、彼女はいよいよパラペットに足をかけ、後ろ向きに降下体勢に入った。
「一分したら降りるから」
「頼みます」九十九警部が頷いた。
警部を先頭にして、全員が足早にその場を離れた。エレベータを使わずに、非常階段でどやどやと降りていく。みんなで七階の空き部屋に入った。南側の回転窓のところで待つ。すると、窓拭き職人よろしく、風間がするすると滑るように降りてきた。彼女は窓枠に足をかけると、体重を部屋内へ移動させてから床にストンと降り立った。
「本当にこの方法だとしたら」二本のロープのフックを自らの安全帯から外しつつ風間が口を開いた。「当日は時間短縮のためにメインロープ一本でやっただろうね」
「ありがとう」
裕美はねぎらうと、刑事たちを振り返り、オホンと咳払いをした。
「当日はたぶん、目立たないように真っ黒な服装をしていたことでしょう。こうして、外から侵入した替え玉が、中の人間と入れ替わればよいのです。ふたりは直ちに互いの服装を交換します。要は体格が似ていればよいのです。林の髪型は長髪でふわふわとしているので、頭の形を隠すのに便利ですし、カツラに適しています。林が侵入者の使った装備を使って地面に降りれば、入れ替わり完了です。それを見届けて、屋上にいる協力者がロープなどを回収し、元来た方法で撤収する。一方、変装を終えた替え玉は、午前三時までオフィスの中にいます。あとはIDカードを使い、通用口から出るだけ。よって、協力者は最低でも二人。もし外に見張り役を置いたとすれば三人といったところでしょう」
一寸置いて、「見事だ」とか、「おおーっ」といった感嘆の言葉が刑事たちの口から漏れた。尊敬に満ちた眼差しが自分に注がれるのが、何となく照れくさかった。
「警部っ」相馬警部補が興奮した様子で叫んだ。「これでアリバイの謎が解けましたね」
「ああ」九十九警部が力強く頷いた。「完璧といっていい。協力者は林と親しい者に違いない。さっそく、周辺を洗ってみるんだ」
林達郎のアリバイを突き崩す推理を組み立てたとはいえ、実のところ、裕美は刑事たちほど喜んでいなかった。なぜなら謎はもう一つある。そして、こっちのほうが強敵だ。
裕美は仕事を終え、下北沢のマンションに帰った。その途中、パスタ屋で食事もすませた。父は早くに、母は昨年に亡くなり、今は独りぼっちである。一風呂浴びて寝巻き姿になると、缶カクテルを開けてソファにもたれかかった。習慣的にテレビをつける。
若手漫才師のトーナメント番組をやっていたが、思考はあくまで事件にあった。時々、漫才のほうにも気が行ったが、おもしろいコンビは多くない。そのうち、少し眠気が襲ってきたので、クッションを枕にして、ゴロリと横になった。
テレビはただ点けているだけだった。そろそろ消そうかと思った時、登場したコンビが冒頭から3D映画の話題を始めた。そういえば裕美も見たいと思っていたのがあった。
「最近は3Dブームでして、映画が次々と立体映像になってますねん」
「そういや、お客さんの中には、宙を手で掴もうとする人がいたりしますな」
相方がまるでハエを追っているようにスカスカと宙を掴んでみせた。その様子が滑稽なためか、会場に笑いが木霊した。
「映画だけやないで。3Dテレビいうのもあるんや」
「家庭のテレビから立体映像が飛び出すんか。料理番組なんかうかつに見れへんな。おれが夕食のカップ麺すすっている時に目の前にドーンと豪華料理が出来てきたら悲惨やで」
「食いたくても食われへんってか」
「しかも、昔と違って今のテレビはほんまに薄いもんなあ。爺ちゃん婆ちゃんからしたら、あれはほとんど屏風やで。動く立体映像が出る屏風みたいなもんや」
「屏風いうたら、一休さんのエピソードを思い出さへんか。ほら、足利義満が一休さんに無理難題ふっかけるやつ」
「ああ、あれか」ポンと手を打つ。「意地悪な将軍様が『虎が屏風絵から抜け出して暴れるんで困っとる。なんとか退治してくれ』いうて頼む話やな」
「そやそや。一休さんは縄をもって、『分かりました。今から虎を捕まえてご覧に入れますさかい、将軍様が屏風絵から虎を追い出してくださいな』ってやり返すやつや」
「もしあの時に今みたいな3Dテレビがあったら悲惨やなあ。将軍様は『よっしゃ』って、リモコンのボタンを押すだけで、ほんまに虎を追い出してしまいよるで」
「そうしたら、一休さんは打ち首やがな。安国寺も取り潰しやで」
ハハハ…と聴衆の笑い声がホールに木霊する。
裕美はまた事件に思考を集中した。太田善四郎の死が自殺でないとしたら、いったいどうやって殺されたのか。しかも、第三者が入れない密室で。
だが、いくら考えても分からなかった。「ハハハ」と人々の笑い声が響き、思考が中断された。目の焦点が再びテレビ画面に合う。漫才コンビはまだ一休ネタをやっていた。
「…でな、その時、一休さんは橋の真ん中を堂々と歩きよったやろ」
「ああ、『橋』と『端っこ』をうまい具合に掛けよったんやな」
「そやけどな、『このはしわたるべからず』という立て看板を『このブリッジわたるべからず』という文言に変えたら、一休さんはどないしたらええねん?」
「おまえ、室町時代に英語があるかい!」
ハリセンでパンッと相方の頭を叩く。聴衆がどっとうける。
「仮にやがな」
「そんな意地悪したんなや」
「そしたら、一休さんも坊主頭から湯気出して頓知に苦労しよんで」
「周りがニヤニヤしながら、『おい、一休、お得意の頓知はどうした?』とか、冷やかしながらか?」
「そや。例の『ぽくぽくぽく…チーン!』の『チーン!』がいつまで経っても鳴らへんパターンや。ずうーっと、『ぽくぽく…』と木魚が鳴ったままや」
といって、目を瞑って木魚を叩く真似をした。それを見て、裕美はふと木魚をイメージした。すると、なぜかそれが、太田氏の、あの爛々とした禿頭へと変化した。
「そしたら、『はーい、あわてない、あわてない』とか余裕かまして寝転んでる場合やあらへんな。もう周りからボコボコやで」
「えげつない話やな。教育に悪いわ。絶対に子供に見せられへんで…」
若手の漫才コンビは、その後も、一休さんが仏の道を踏み外したとか、結局は悪の道に走ったとか、言いたい放題を続けた。時々、突っ込み役がハリセンでボケ役の相方の頭をパンと叩く。その度に観客から笑い声が上がった。
突然、ハリセンを勢いよく振り下ろす様と、脳裏に浮かんだ木魚のイメージが重なった。彼女はソファに寝転がったまま、己の寝巻き姿をしげしげと見やった。
次の瞬間、眠気が吹っ飛び、ソファから立ち上がっていた。
どうやら、人間、ツイている時はとことんツイているらしい。それまでいくら考えても分からなかった密室殺人の謎が一瞬にして解けてしまった。
「たとえば、こういう方法はどうでしょうか」
裕美は寝巻き姿のまま、まだ残業していた九十九警部に連絡を入れ、突然閃いたトリックの種明かしをした。
要は書斎から善四郎をおびき出せばいいのである。そして、何かに注意を向けさせ、死角から不意打ちする。場所は明子の寝室などが妥当だ。彼はもともと己の部屋の窓に防弾ガラスをはめるほど周囲を警戒していた人物だ。その警戒心を逆に利用すればいい。
深夜、寝巻き姿の明子が怯えた様子で善四郎の書斎のドアを叩く。
「あなた、何か外の様子が変。電柱の陰に誰かいて、時々こっちをじっと見てるの。怖くて仕方がないわ…」
そんなふうに言われれば、善四郎としても確かめるほかない。妻に釣られて、彼は寝室におびき寄せられる。そして、窓から電柱のある小道のほうをそっと覗く。
だが、消灯された妻の寝室には、林が潜んでいた。部屋は玉川上水側の歩道と面しているので、縄梯子でも垂らせば容易に第三者を招き入れることが可能だ。侵入者は玄関の犬に吠えられることもなければ、防犯カメラに録画されることもない。
善四郎が外の景色に注意を向けた瞬間、背後から林が金槌で頭を一撃する。その時に死んだかもしれないし、意識を失っただけかもしれない。いずれにしても、殺害だけでなく、太った男を抱えて書斎まで運ぶためにも、二人の協力が不可欠だ。おそらく、林が背後から彼の上半身を抱え、妻が足側を持ったのだろう。書斎のドアは、善四郎の指を使って解錠すればいい。そして身体をベッドに横たえる。
まずは遺書の偽造だ。林は侵入の時点から終始、手袋をはめていたに違いない。便箋集から一枚を切り離し、机の上に置いて文字を書く。文面だけは、あらかじめ明子が拾っていたのかもしれない。ライトボックスを使って下から透かせば、簡単に筆跡を真似ることができる。あとは画板か下敷きの上に載せたその紙に、印鑑を押すように善四郎の左手を押さえつければいい。いかにも彼がしたためましたよ、というふうに。
次は自殺の偽装だ。これは書斎にある猟銃を使う。銃口を顎に当てると、善四郎の左手を銃身に握らせ、右手の親指をトリガーに当てる。だが、実際に引くのは林だ。
このように、散々悩んだが、気付いてしまえば、なんてことはない。単純なトリックである。背後から金槌で襲うという方法なら、不意打ちが可能で、出血も少なくてすむ。
だが、相手を気絶や死に至らしめるほどの勢いで頭頂をぶん殴れば、当然、頭蓋骨にはその型がつく。検視の段階で、凶器の種類と背後から振り下ろした角度が分かる。誰が見ても殺人だ。
だが、間髪をおかず、その部分を散弾で吹き飛ばしたらどうか? 見事な証拠隠滅となるではないか。そもそも自分で頭の上から銃を押し当てることは不可能だ。長銃の場合なら、どうしても顎に銃口を当てるほかない。その場合、散弾が頭頂へと抜ける形になる。実際、善四郎の死体は、頭の皿が粉々に砕け散っていた。
つまり、この度の“自殺”は、このような猟銃を使ったスタイルでなければならなかったのだ。それが証拠隠滅にもなる唯一の方法だからである。
裕美は九十九警部に対して、この必然的ともいえる殺害方法を説明してみせた。
九十九は容疑者の逮捕が近いことを確信していた。
捜査はここへきて急速に進展した。部下が次々と成果を挙げ始めた。
アーク中山ビルの屋上パラペットの金属カバーから、怪しい靴型が採取された。犯行日から何度か雨が降っていたが、チョーキングという独特の現象のおかげで、夜中に捜査用ライトを照射すると、たくさんの足跡が浮かび上がった。そこから、出入りの清掃員のものでない靴型が一つだけ特定された。しかも、足跡痕の状況から、清掃員でもないのにその踵がビル外に向かっているなどの不可解な点も見つかった。
一方、林達郎の交友関係から、背丈や格好がよく似ている学生時代の友人が捜査線上に浮かんだ。独り住まいをしているこの男のところへ赴いた捜査員が、まさに玄関で同型の靴底をしたスポーツシューズを発見した。証拠として押収したその靴を調べたところ、小石の挟み具合や溝の欠け具合などが、ビルで採取したものとピタリと一致した。しかも、微物分析装置にかけたところ、溝からチョーキングの成分までが検出された。
犯行に関わった決定的な証拠が得られた。男を呼びつけて事情聴取した。相馬警部補たちが「このままだと殺人の共犯者だぞ」と脅かすだけで、男は真っ青になってすべてを自供した。その結果は女探偵の予想した通りだった。共犯者はもう一人いて、それは男と林との共通の知人だった。犯行当日、二人はレンタカーで現場近くに乗りつけると、深夜、二棟隣のツノダビルから侵入した。一人が降下して林と入れ替わり、屋上に居残った一人がロープと脚立を回収して、また同ビルから退出した。
アリバイ作りに協力した当人たちは、重大な犯罪に関わっているとは露知らず、あくまでゲーム感覚で協力したと説明した。彼らが道具をそろえたと話したホームセンターからは、レジの記録のほかに、防犯カメラの録画も得られた。そこには三人の男がロープや安全帯などを買う様子がばっちりと映されていた。そのうちの一人は林達郎だった。
女探偵の推理は、アリバイの謎だけでなく、密室殺人の謎も見事に解いてみせた。
仮に太田善四郎が別の部屋におびき出されて金槌で殴り倒されたとしたら、それに関係する物証があるに違いない。改めて太田善四郎の死亡時の着衣が調べられた。すると、寝巻きの背面に、ある特徴的な繊維が付着していた。捜査員が邸宅内を捜査したところ、その繊維は書斎ではなく、明子の寝室に敷かれていた絨毯と一致した。これは“自殺”の直前に、善四郎が明子の寝室の床で仰向けに横たえられた事実を意味した。捜査員はさらにその寝室を徹底的に調べた。そこは事件以来、念入りに掃除されていた。
だが、繊維に染みついた血痕は、洗剤で拭いたくらいでは完全に消えない。見た目では綺麗になっていても、肉眼では見えないほどの染みが残る。そして、ほとんどの有機物は特殊な光源によって発光させることが可能だ。それが人体由来のものならばDNA鑑定によって個人を特定することもできる。案の定、捜査用紫外線ライトによって、寝室の絨毯に点々と付着した血痕が浮かび上がった。そこから微量の血液成分も検出され、善四郎のDNAとも一致した。彼の頭が横たえられた位置も判明した。
決定的な物証がついに得られた。警察は容疑を殺人に切り替え、三鷹警察署に捜査本部を設置した。そして、太田善四郎殺害の容疑で林達郎と太田明子の逮捕に踏み切った。
直接的に物証を見つけ出したのは科学捜査だが、元はといえば捜査の突破口を開いたのは裕美の推理である。しかも、彼女の幸運というか、活躍はまだまだ続いた。
林達郎の過去を調べていた藤井源之助が、重要な情報を掴んで帰ってきた。
「お嬢。遅くなりやしたが、とんでもないことが分かりやしたぜ」
彼によると、かなり過去の人脈に当たらなければ到達することができない情報なので、捜査当局もまだ掴んでいないはずだという。
「実は、林の母親は郁子といいまして、彼女はかつて善四郎の愛人の一人だったんです」
「まあ」驚いた。「ということは、林達郎は…まさか太田氏の実の息子なの?」
「林郁子は妊娠したあとに捨てられた女なんで、その可能性は十分にあるでしょう」
「でも、そのことを太田氏は知っていたのかしら? 後妻の浮気相手がよりにもよって自分の息子であることに」
裕美は依頼者の様子を思い出してみた。浮気相手の写真や録画を見て、かつての愛人の面影を見出していただろうか? そんな様子は皆無だったように記憶している。
「その可能性は低いですね。というのも、当時は善四郎も若く、仕手戦で大儲けしていた時期でして、兜町では怖いもの知らずのイケイケで通っていました。あちこちで女を孕ませていたそうで、十指じゃ足りないとかなんとか…」
「それじゃ、覚えてさえいなかったのかしら?」
「なにしろ二十七、八年も昔のことですから、おそらく…。当時、数百万くらいの手切れ金を支払ったそうで、その後は両者とも一切関わりあいをもってません」
「まああ、呆れたっ。男って本当に勝手なものねっ」
「あ、あの、急に一般論に結び付けられても…」藤井が困惑していた。「現にあっしなんかはワイフ一筋ですし…」
「そうね、少し飛躍しすぎたから。これはあくまで、あのトドみたいな男に限ってのことね。実際にトドそのものだったし」
「あ、あの、あんまり仏様をそんなふうに悪し様に言わないほうが…」
「郁子は今どうしているの?」
「数年前に癌で亡くなりました」
「そうなの…」人差し指を無意識に顎につける。「それにしても、偶然かしら? 林がたまたま明子の愛人に収まったにしては、ずいぶん話ができすぎているわね」
「おっしゃる通りで。実は、ふたりの出会いはダンスクラブでした。当初から明子が通っていて、林があとから入会したそうです。しばらくして、ふたりは付き合い始めました」
「ということは、最初から善四郎の妻に狙いを定めて、計画的に近づいた…」
「たぶん…。林が動き始めたのは、母親を癌で亡くした後です。ずっと母子家庭でして、決して裕福ではなかったそうで」
「なるほどぉ。仮に達郎が、実の父親が善四郎であることを、母親から聞かされて育ったとすれば…。今回の事件の動機がはっきりするわね」
「復讐…という線が一番しっくりきやすね」
「それはすごい…」九十九豊は思わず唸った。「いやはや、貴重な情報です。この度は本当に助けられてばかりで…。どうも、ありがとうございました」
女探偵からの電話を丁重に切るなり、九十九は一同にその情報を伝えた。それは部下たちを驚かせ、計画的犯行を確信させるに十分だった。
林達郎が太田善四郎のかつての愛人の子であり、林から明子に近づいたと仮定すると、成り行きではなく当初から計画的だったとも考えられる。
「父親を殺して財産を奪うことは正当な権利である…とでも思っていたのでしょうか?」相馬警部補が訊いた。
「まだ分からん」と、九十九は率直に言った。
「この情報を突きつければ、やつの完落ちも時間の問題でしょう」
「ゲロしなくても、これだけの状況証拠なら検察も納得しますよ。十分に公判も維持できるでしょう」
部下たちが次々と楽観論を口にした。
取り調べは、少なくとも明子に関しては進展していた。当初こそ頑として犯行を否定していた明子だったが、数日で根を上げた。きっかけは捜査員から共犯者として林が逮捕されたと聞かされたことだった。驚いた様子を見せ、自供を始めた。
「どうやら逃げ切れないと観念したらしい」と捜査員たちは考えた。
とくに、林が計画的に彼女に近づいたという話を聞いて、明らかにショックを受け、「騙された」と嘆いた。明子は林こそが主犯だと断言した。自分は林に命令された、計画に協力しないと殺すと脅された、そこで仕方なく夫殺しを手伝うことに…などと供述した。
そして、夫の殺害方法は、まさに女探偵が推理した通りだった。
一方の林達郎は、「やっていない」とか「私ではない」などと繰り返すばかりだった。捜査員たちから、「なぜ退社時間をごまかす必要があった、何のためにアリバイを作った?」と代わる代わる詰問されても、黙秘を通した。屋上の足跡という物証を突きつけられようが、一日中怒鳴られ胸ぐらを掴まれて揺すられようが、断固として口を割らなかった。
ただ、「共犯の明子が『おまえが主犯だ』と自供したぞ」と告げられた時には一瞬、憎悪に満ちた表情を浮かべたが、それでも「違う」と言ったきり、あとは黙秘を敢行した。
「まあ、解決は時間の問題でしょう」
そういって、お茶をすする相馬警部補は、実に機嫌がよかった。
菓子折をもって事務所を訪れた刑事は、明子の自供内容など、捜査の進捗状況を教えてくれた。といっても、彼はすでに肩の荷が下りたと思っているのか、ほとんど談笑と称しても差し支えなかった。正直、裕美は、容疑者二人の供述内容や態度のギャップに引っかかりを覚えた。しかし、彼女自身にもその違和感の正体は皆目掴めなかったし、話題がすぐに雑談に向かったので、とくにこだわることもなかった。
やはり、刑事たちも裕美の過去や背景に、それなりの興味があるらしい。警察官僚時代の想い出話や、彼女を後押しする警察庁の人物などについて、いろいろと尋ねられた。退職した時には警部でしたというと、「それなら私の上司ですね」と感心された。
「この度は、本当に小笠原さんにお世話になりました。うちの係長からも、くれぐれもお礼をと、念を押されております。捜査員一同、本当に感謝感激でして…」
おいとまのために相馬刑事が改まった、その時だった。彼のケータイが鳴った。「失礼」といって、それをとる。捜査本部からだった。
「はい、はい…」と返事をしていたが、すぐに眉をしかめた。その表情が次第に困惑の色を帯び、ついには「なにぃ?」と叫んだ。
「いったい、どういうことなんだ……?」呆然として訊いた。
どうやら、電話の相手側にも理解できない不可解な内容らしい。刑事は電話を切るなり、訳が分からないという顔でこちらを見た。
「小笠原さん、今捜査本部に入った情報によると…」
相馬刑事が説明を始めた。たしかに、それは予想だにしない意外な話だった。
つい先ほど、林の住まいを管轄する所轄署から一報があったという。それによると、事件の前、林は相談のために地元の警察署を訪れていた。その内容は「資産家の太田善四郎氏が殺されるかもしれない」というものだったらしい。
対応に当たった刑事が「誰が殺そうとしているのか?」と訊くと、「たぶん夫人の明子だ」と答えた。ところが、「あなたは何者ですか?」とか、「どういったお知り合いですか」といった質問を投げかけると、相談者は途端にしり込みを始めた。結局、「そういう話を小耳に挟んだので気をつけてほしい」と頭を下げて帰っていった。
内容があまりに漠然としていたため、相談は受け付けた刑事のところで止まっていた。だが、捜査本部から所轄に対して林についての照会があった際、その刑事は急にこの時の経験を思い出して、連絡をよこしてきた…という内容である。
「いったい全体、どういうことなんでしょうか?」相馬刑事は困惑を隠しきれないでいた。
裕美のほうが訊きたいくらいだった。途端、疑念の渦に放り込まれた。
自分は何かとてつもない勘違いをしていたのではないか。何か重大な要素を見落としていたのではないか。何かを忘れていないだろうか。
その場で目を閉じた。「よく考えてみるんだ」と己を叱咤した。前頭葉に意識を集中し、善四郎に対するデータを総動員する。
その様子が尋常でないためか、刑事も息を殺して彼女の様子をうかがっていた。
(林が主犯ではなかったのか。己の復讐のために明子を利用したのではなかったのか。ところが、実際には善四郎の殺害を阻止するふるまいをしていた。しかし、ならば、なぜわざわざアリバイを作った? 他に見落としている要素や人物はないか…?)
と突然、脳裏にフラッシュが焚かれた。ある推理に基づけば、すべてのピースがぴったりと組み合わされ、矛盾のない絵が完成する。
そうか! まったく逆だったのだ!
「刑事さん、明子の兄ですっ。今すぐ彼女の兄を調べてくださいっ。なぜなら…」
林達郎は父を殺そうとしたのではなく、守ろうとしたのだ。
彼女は自分の推理を一気に語った。相馬が驚愕して固まった。
調べてみると、事件後、明子の兄の根元良一が行方をくらましていることが分かった。
しかも、その直前、彼の自宅マンションの駐車場で、深夜、激しく争う声がしたという通報騒ぎがあった。しかし、警察官が駆けつけたときには何もなく、周囲は静まり返っていた。喧嘩した当事者たちがどこかへ行ってしまったということで、その場はいったん収まった。時刻は太田善四郎が殺されてから、約一時間後のことだった。
駐車場には根元の愛車が停められたままだった。しかも、奇妙なことに、部屋の中はエアコンが付けっぱなしで、冷蔵庫の中にも買って間もない酒や惣菜があった。とても計画的に準備して失踪したようには見えなかった。
捜査当局が調べたところ、根元は失踪後、ATMで一円たりとも金を引き出した形跡がなく、ケータイも未使用だった。電源を切ったままなので、発信源も特定できなかった。九十九たちは、根元が事件に巻き込まれた可能性が高いと判断した。
相馬は小笠原裕美の言葉を思い出していた。
「そう、たしかに林は善四郎氏を殺してはいないのです。彼がその日、わざわざ手の込んだアリバイを作ったのは、別の人間を襲うためだったからです」
捜査員から容疑が切り替わったことを告げられると、林達郎はついに観念した。一転して己の犯行(ルビ)を認め、洗いざらい自供した。
「…ずっと太田善四郎を憎んでいた。殺してやりたいとすら思っていた。だが、本当に殺されようとしていると分かったとき、どういうわけか、助けなきゃっと思って…」
内容は次のようなものであった。
そもそも林が明子に近づいた理由は復讐のためであった。それは「善四郎から奪う」というものであった。かつて母親があの男から捨てられ、母子は惨めな暮らしを余儀なくされた。そこで妻から捨てられ、慰謝料をふんだくられる目にあわせてやろうと決心した。それが彼なりの復讐だったのである。そのために明子を誘惑し、自分に惚れさせ、通常の離婚にもっていくことを企んだ。すべては、それで終わるはずだった。
しかし、事態は彼自身も思わぬ方向へと転がってしまう。明子の浮気が発覚し、探偵によって証拠を押さえられてしまったのだ。明子にしてみれば、もともと財産目当ての結婚である。己の不貞が原因で離婚が成立したら、すべてが元の木阿弥になってしまう。それまでの苦労と我慢が水の泡だ。ピンチを打開する方法は一つしかない。
明子は林に殺害の相談を持ちかけた。「離婚になる前に、あの男を殺したい。ほとぼりが冷めたら、あなたと再婚したい」と。だが、林は拒絶反応を起こした。この時点で、ふたりの関係は破綻した。林は、明子が次に相談を持ちかけるのが実兄ではないかと危惧した。
明子の兄・根元良一は生業にも就かず、かといってヤクザでもない、中途半端なチンピラ風情だった。酒に酔って大言壮語したり、妹から金を無心したりしているうちに、いつの間にか三十半ばを過ぎてしまったらしく、善四郎からも嫌われていた。林も幾度かこの男に会ったことがあり、危険さを嗅ぎ取っていた。いつも無頼を気取り、努力もしないくせに、「チャンスさえあれば」などと一攫千金を夢見ていたからである。
案の定、明子が次に相談を持ちかけたのは、この甲斐性なしの兄だった。なにしろ明子は兄にたんまりと小遣いを渡してきた。多大な貸しがある。良一にしても、金持ちと結婚した妹は貴重な財布だ。単に兄妹というだけでなく、利害関係も一致している。
林は危惧した。このままでは善四郎は殺されるかもしれない。しかも、自分はその犯人を知っている。だから犯行後には、今度は真相を知る自分が口封じされる可能性すらある。悩んだ末、林が最初に打った手が、警察署に出向いて事情を話すことだった。
しかし、ほとんど相手にされなかった。対応にあたった刑事からも真剣さが感じられなかった。なにしろ、自分は人妻の浮気相手でしかない。どだい、信用しろというほうが無理なのだ。
警察は事件が起こってからでしか動かない。当てにならないことがはっきりした。だが、このままでは善四郎は殺され、自分にまで口封じの矛先が向かってく可能性がある。
もはや、林には先手を打つ以外の選択肢はなかった。自分でなんとかするしかない。強盗に見せかけて明子の兄を襲撃し、重傷を負わせようと決意した。手足の骨でも折ってしまえば、数ヶ月は動けなくなる。そのうちに離婚が成立するだろう。幸い、根元良一は、毎晩のように遅くまで飲み歩いている。いつも深夜から朝方にかけて帰宅し、昼過ぎまで寝るという自堕落な生活だ。待ち伏せすれば、容易に襲撃できるだろうと踏んだ。
できる限り善四郎の財産を剥ぎとってやるという当初の計画とは異なるが、もはやこれ以外に方法はなかった。そのために、わざわざアリバイまで作った。
まさか、同じ日に明子とその兄が犯行を企てていたとは露とも知らずに。
当日、根元良一が自宅にいないことは、公衆電話から確認していた。夜の十二時過ぎ、友人と入れ替わりにロープを伝って外に出ると、周辺に駐車しておいた自家用車に乗り込み、良一のマンションへと向かった。近くに車を停めると、マンションの駐車場で待ち伏せした。服装は真っ黒で、おまけに目だし帽まで被った。どうせ今日も酔って、千鳥足で帰ってくるだろう…そうタカをくくって、野球のバットを構えた。
ところがである。その日に限って、良一は普段のように酔っていなかった。それどころか殺気立っていたので、奇襲とはいかず、もみ合いになった。重傷を負わせるつもりだったのに、勢いあまって殺してしまったらしいことに、事を終えてから気づき、戦慄した。とにかく、遺体は車のトランクに隠した。近所に騒動を聞かれたかもしれないと思い、すぐにその場を走り去った。
善四郎自殺のニュースは、その日のうちに知った。つまり、良一は、まさに善四郎殺害からの帰りだったのだ。林は良一のケータイを使い、兄を装って明子にメールした。しばし連絡を絶つ、という趣旨だ。そうすれば、姿を消しても、しばらくは怪しまれないだろうと考えたからだ。それからスイッチを切り、河に投げ捨てた。
当初、捜査当局が自分の元にやって来た時は、てっきり自分が犯した殺人の件だと思い込み、ひどく慌てた。これで警察に不信感を持たれてしまった。しかし、疑われているのは善四郎殺害の件だと分り、黙秘に転じることにした…。
林達郎の語った真相は、以上のようなものであった。根元良一の遺体は、彼の供述通りの場所に埋められていた。遺体の上着のポケットには、血の付いた金槌を入れたビニールが入っていた。血痕のDNAは太田善四郎のものと一致した。
林達郎の自供は、明子のそれの矛盾点をも暴きだした。彼女は、捜査当局が林を共犯者として逮捕したと知り、兄の役柄をそっくり林に入れ替える嘘を思いついたのだ。それだけではなく、己の罪をできるだけ軽くするために、林を首謀者に仕立て上げ、自分は唆されただけと言い張ることにした。だが、嘘がばれ、兄が殺されたことを知った彼女は、ひどいショックを受け、今度こそ観念した様子で正直に供述を始めた。
「結果的に二件の殺人事件を解決に導いたということで、君たちには感謝状が贈られる予定だ。九十九君も己の手柄にはせずに、周りには君の功績だと吹聴しているよ」
電話の向こうの北王子英明は、わが事のように嬉しそうだった。
「まあ、そう言っていただけると、嬉しいですわ」
「じゃあな、名探偵(ルビ)さん…」
電話を切った。社長席の周りに集まっているみんなの顔を見る。
「というわけで、私たちに感謝状をくれるって」
誰もが満足そうに微笑んでいた。しかし、人の良さで終わらないのがここの連中だ。
「今回は、苦労はわれわれ、手柄は警察様というパターンですね」
鏡義雄がそう皮肉ると、専務の大塚がしきりと頷いた。
「本当は書状よりも調査経費をくれたほうが助かるのですがねえ」
「いやあ…」藤井源之助が思わず頭をかく。「あっしなんか、調査のためにずいぶんと交通費と宿泊費を使っちまって、お嬢に面目ねえ」
「いいのよ。だって、こうして私たちが警察の捜査に役立つことを実証していけば、今後、何かと調査の役に立つ時がくるわ。ほら、タダほど怖いものはないって言うでしょう」
みんなが「なるほど」と頷いた。
「お金といえば…」鏡がため息をついた。「今回はとりわけ金に汚い事件でしたね」
「資産家のオヤジが金の力で美女を妻にし、一方の女は金目当ての結婚をする…」裕美もうんざりしたような表情を浮かべた。「たまたま双方の利益が一致したというだけの間柄よ。その利己的な関係の行き着いた先が殺人だものね。嫌になるわ、ホント」
「人に与えるのが愛なんですけどね」と、事務員の三上サクラ。
みんなが「うんうん」と頷く。
「まったく、どこにも真実の愛なんてありゃしねえ」
と風間雪が腹立たしげに吠えると、そのすぐ横で藤井がプププと吹き出した。
「何がおかしいんだよ、爺さん?」
「お金よりもバイオレンスとかエキサイティングをとる風間さんなんかは、女性としてむしろ例外なんですよ、例外」
そう横から口出しした鏡に、風間がぐいと顔を近づけて詰めよった。
「どういう意味だよ?」
「そういう意味ですよ」
鏡も平然と顔を近づけ返し、涼しい目を向けた。ふたりはしばし睨みあった。
「ああっ」と、裕美はいきなり慨嘆した。目をパチクリして首をふり、天に祈りを捧げる芝居がかったポーズをつくる。「あたしも真実の愛が欲しいわ」
ちょっと、夢見る女子高校生っぽく、ぶりっ子してみた。
事務所の空気が瞬時にして凍りついた。三十秒ほどの沈黙が続いた。
「さあ、仕事仕事」大塚が事務的な口調で言った。
みんながその場を去っていった。
(「ダブルトリック」了)
*この他、2編の短編を併せて、計3本立てで、
『女神のチェスゲーム 探偵小笠原裕美の超推理』をkindleから出版しています。今ではkindle本を読むのに専用端末は不要であり、PCでもスマホでも好きな端末で読むことができます。








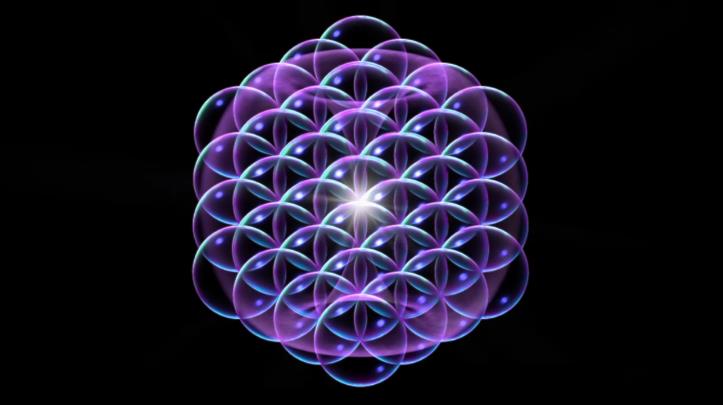




スポンサーリンク