国共内戦、朝鮮戦争、中ソ紛争、中越戦争、そして天安門事件。
これらを見ると、中国共産党とは、軍隊であり暴力そのものである事実が分かる。
毛沢東は「革命は銃口から生まれる」と言った。
軍略家である毛は、日本軍と国民党軍を戦わせ、漁夫の利をさらった。
しかし、軍略家としては天才だが、経済社会政策においては無能。
人民公社制・大躍進政策を推進し、2千万の餓死者とも言われる大失敗をした。
このままでは国が崩壊すると危惧した劉少奇・鄧小平らが修正路線を推し始めると、毛沢東は権力を奪い返すために青少年を扇動。
文化大革命である。無知な青少年は徒党を組んで「走資派」を粛清して回った。
せっかく北京を占領していた日本軍も文化財を保護していたのに、毛沢東は世界でもっとも壮大な北京や南京の城壁と楼閣をぶっ潰した。これには日本の明治初期の廃仏毀釈にも見られた、“遅れた自己”に対する嫌悪の噴出もあったのかもしれないが。
毛沢東は挙句、国務を周恩来に放り投げて、自分は引きこもってしまった。
中国が辛くも倒れずにすんだのは、周恩来が必死で支えたからである。
狂った文革の時代が十年ほど続いた。毛沢東は晩年に鄧小平をまた引き上げたが、専横をふるった毛の妻・江青ら「四人組」と対立し、鄧小平はまた失脚する。
そのうち、周恩来が亡くなり、毛沢東も1976年に亡くなった。
江青ら「四人組」は人望・統治能力ともになく、共産党幹部たちが「中国の将来を託せるのはこの人物しかいない」として選んだのが鄧小平だった。
かくして鄧小平が再度復活し、反撃を受けた四人組のほうが粛清される。
なぜ朝日新聞は日中離間工作に尽力したのか? 真犯人は誰だったのか?
こうして「鄧小平の時代」が始まった。
当時の中国社会はボロボロになっていた。
鄧小平は来日して日本の発展ぶりに衝撃を受け、改革解放経済路線を決断する。
それが1978年の終わり頃。
この頃の中国は「親日」路線だった。日本の映画も輸入され、公開された。
実は、これを見た中国人はものすごい衝撃を受けたのである。で、ますます日本ファンになった。親日のピークは1980年代前半の「中曽根・胡耀邦」時代。
日本もまたこの頃は「親中」だった。日本人の大半は、人民服を着て自転車に乗っていた中国人が大好きだったのである(笑)。
しかし、下の記事でも少し触れたが、日本と中国があまりに接近しすぎるので、日中離間工作が始まった。策源地は欧米支配層というより、KGBくさい。

日本との中立条約を破って、満州を侵略し、多数の婦女子を強姦殺害し、60万将兵を拉致した極悪ソ連は、自身の戦争犯罪を帳消しにするため、「日本はナチスの同類」と宣伝する必要に迫られた。だから、ハバロフスク裁判で731部隊の犯罪を誇張した。その後にソ連のエージェントの島村喬、そして作家の森村誠一を使って宣伝した。森村のネタ元が赤旗の記者。また、朝日新聞も匿名の「証言者」を記事にし始めた。
731部隊だけでなく、南京大虐殺もそう。抗日の指導者の毛沢東からして「南京大虐殺」という言葉を発したことすらない。当時南京の日本軍は、かなりの捕虜を処刑し、又ゲリラ狩りの際に間違えて多数の兵齢民間人男子も処刑しており、決して無実ではない。
ここでのポイントは「毛沢東が気にも留めていなかったレベルだった」という事実であり、また70年代に「数十万の市民を大量虐殺した」という話にすり替わったこと。
このストーリーもまた朝日新聞がまず日本で広めて、それが中国に伝達した格好。
私は年配の中国人から「私の時代は南京大虐殺なんて学校で一度も習わなかった、ソ連が祖国の一番の敵だと教えられた」と言われたことがある。
「靖国参拝ガー」も同じ。朝日新聞と社会党の田邊誠委員長が中国の長老部を焚きつけて、靖国神社の首相参拝を批判させた。これが1985年8月15日から。
実は、それまで中国は日本の靖国参拝に何の関心もなかった。
状況証拠からして「731部隊」「南京大虐殺」「靖国参拝問題」の三つは、KGBの指令で日本国内のエージェントが広めた可能性が高いと、私は睨んでいる。
中国は「反日」に路線転換してから、それを自ら政治利用するようになったわけだ。
日本には瀬島龍三以下、ある者は取引で、ある者は自身の信条からソ連の対日工作を担っており、しかも社会的影響力の強い人物が少なくなかった。
結局、それは「犯罪」ではないために、今なお暴かれず、罰せられてもいないのだ。







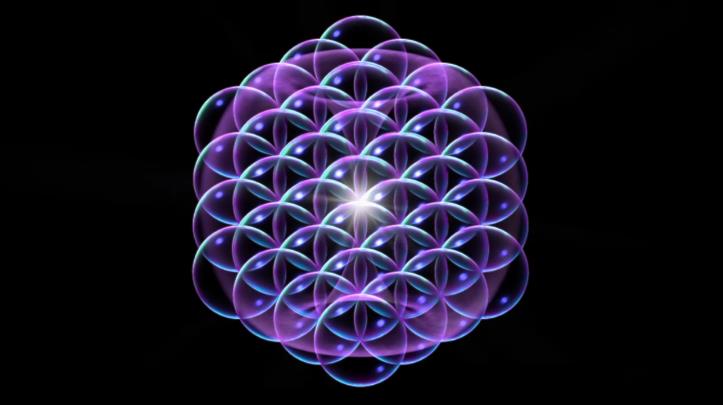




スポンサーリンク