昨年、トランプ政権は中国に対して2500億ドル規模の関税をかけ、10月にはペンス副大統領が「対中宣戦布告」とも取れる激烈な中国批判演説を行った。

要は、中国は、知的財産の窃盗やスパイや為替操作やら、ありとあらゆる汚い手を使って、政治的にも経済的にもアメリカの覇権を奪おうとしているという批判だ。
ペンスの中国観に大きな影響を与えたのがピルズベリー博士と言われる。博士は中国語がペラペラで、もともと親中派の一人だったが、中国がどんどん経済発展しても、いつまで経っても民主化する気配がないとして、「裏切られた」と気づいた人物だ。
私は何度か触れているが、世界支配層は東アジア人について独特の偏見があって、「日本人や韓国人や台湾人がそうだったから、中国人も同じだろう」とタカをくくっていたフシがある。つまり、目の吊った連中なんてみんな同じようなものという思い込み。
私は20年前から共産中国の最終目標を知っていた。むろん、それは「アメリカから覇権を奪って中国が世界の盟主になる」というもの。
というのも、1997年に台湾海峡問題があった。李登輝氏がまだ総統だった頃だ。この時、中国の海軍は、悠然と海峡を横断する米空母に手も足も出ず、指をくわえて眺めているしかなかった。「今は耐えろ」と訓示して鄧小平が国内を抑えた。
「臥薪嘗胆」である。アメリカの中国専門家は、たしかに中国語が分かるかもしれないが、まず司馬遷の『史記』を知らない。だから中国のことが本当には分からない。
中国の「一帯一路」政策も根本的には覇権獲得のための「政治」であって、その「経済的手段」にすぎない。中国では相手よりもいかに優位に立つかという政治闘争がまずあり、軍事、経済、宗教までが並列ではなくその下位の概念である。
ピルズベリー博士には申し訳ないが、中国専門家だの、博士だのと称する人物の見識を盲目的にありがたがる必要はないといういい例だ。
ちなみに、ピ博士は、中国は今後も民主化しないという認識でいるみたいだが、これも間違いだと思う。中国共産党はいずれ、自ら倒れるか、又は倒される。中国の長い歴史から言えば、共産党独裁なんて一時のものでしかない。中国は必ず民主化するだろう。それがハードランディングか、ソフトランディングか、という違いはあるにせよ。
人民元国際化の後ろ盾となるイギリスとかつてのアヘン貿易
さて、前置きが長くなったが、南シナ海での航行の自由作戦や、ファーウェイ締め出しを見ても、ファイブアイズなどの西側諸国が米の対中姿勢に同調しているのは明らか。
しかしながら、他方で、イギリスは金融面で中国と連携している。
たとえば、中国経済の図体とは裏腹に国際決済における人民元の存在感が薄い。それだけ安心できる金融資産とは見なされていないということ。言うならば中国の国際的な信用度がそのまま通貨の実力として現れている。ところが、この人民元の国際化を後押ししているのがシティ。イギリスといえばAIIB(アジアインフラ投資銀行)に参加したことでも話題になった。証券取引でもロンドンと上海間の連携が進んでいる。
また、閉鎖的な中国にあって国際社会への窓口の役割を果たすのが香港のため、中国は形の上では香港を取り戻したが、今でもイギリスの支配を追い出しきれないでいる。香港ドルは米ドルとペッグ(固定相場)であり、今もHSBC(香港上海銀行)やスタンダードチャータード銀行――どちらも英系――が発行している。
この矛盾しているとも取れる動きをどう読むか?
私は共産中国解体と再植民地化が一体となっているのではないかと考えている。
なぜそう直感するのかというと、この連中が100年前にも同じことを企んでいたフシがあるからだ。アヘン貿易に始まって、清朝を半植民地にして、解体後は「孫文→蒋介石」に中国を再統一させて、裏から経済を牛耳ろうとした・・そういう前科がある。
その中核にいたのがかつての東インド会社であり、サッスーン財閥である。サッスーンは元オスマン帝国の宮廷ユダヤで、ロスチャイルドの東アジア代理人である。
かつて大英帝国とその傘下の貿易会社は中国へのアヘン輸出で空前の儲けを手にした。その収益から生まれたのが世界最大級のHSBCである。現在、世界本社はロンドンの「新シティ」たるカナリーワーフにあり、5代目サッスーン卿が頂点に立つ。
浙江財閥≒世界支配層が「孫文→蒋介石」を選んだ

1912年の辛亥革命によって清帝国が崩壊した。南京政府による最初の中華民国は、中国同盟会(後に国民党)の孫文を指導者に選ぶが、最終的に権力闘争に勝利したのは北洋軍閥の袁世凱だった。袁世凱は帝政を復活させるが、支持はなく、以後、中国は軍閥が群雄割拠する時代へと突入する。再び日本に逃れた孫文は宋慶齢と結婚する。
欧米資本とのパートナーシップで勃興した上海を拠点とする「浙江財閥」が、いつから「孫文→蒋介石」による中国再統一事業の後ろ盾となったのか、判然としないし、歴史家も記さない。しかし、宋嘉樹ことチャーリー宋の「宋家の三姉妹」と、イェール大卒でシェル石油の中国代理人・孔祥熙というキーマンを通して見ると、何となく時期が分かってくる。ちなみに、シェル石油のサムエル家を支援したのはロスチャイルドである。

チャーリー宋は、キリスト教をうまく利用して中国への宣教的使命感を持つ米国のジュリアン・カーの後ろ盾を得ることに成功した。カーはタバコ会社や銀行などを所有する大富豪だ。カーは宋の義理の息子となる孫文の革命も支援するようになる。
宋の長女・宋靄齢が孔祥熙と日本で結婚したのが1914年。一方、二番目の宋慶齢が同じく日本で孫文と結婚したのが、ほぼ同時期と言われている。三番目の宋美齢は1920年に蔣介石と付き合い始め、1927年の上海クーデタ成功後に結婚した。
浙江財閥が本格的に国民党と癒着し始めた時期がだいたい見えてこないだろうか。
さて、1914年に第一次世界大戦が勃発すると、1917年にはアメリカ参戦、ロシア革命と続き、世界支配層はこの問題に掛かりきりになった。
1915年、それをいいことに、連合国だった日本はかの悪名高い「二十一か条の要求」を袁世凱政府に突きつける。欧米が本格的に対策に乗り出したのが大戦後で、それがベルサイユ体制と双璧を成すワシントン体制である。悪名高い海軍軍縮条約と並んで「九カ国条約」が締結された。内容は中国の領土保全・主権尊重などである。また、この時に日英同盟が破棄されたことでも有名だ。この1921から22年がターニングポイントだったと思われる。要は、英米は日本の軍事力と中国進出を抑える方針へと転じた。
そして、歴史の表舞台にはないが、世界支配層はそうやって日本をブロックしつつ「孫文→蒋介石」の国民党に天下を取らせ、自らは経済を支配する方針を決めたようだ。
その表れが1924年の第一次国共合作である。本来は水と油であるはずの孫文の中国国民党と、コミンテルンが支援する中国共産党が一時期、急接近した。
孫文はコミンテルンの顧問をむかえ、後継者の蒋介石をソ連留学させた。
この奇々怪々については、従来の教科書的説明ではどこか足りないものがある。
当時、中国国民党のバックにいたのが「浙江財閥→世界支配層」であり、中国共産党のバックにいたのが「革命直後のソ連→世界支配層」である。私は何度も書いているが、ソ連は世界支配層の産物であり、スターリンが裏切るまではその統制下にあった。
つまり、どちらのバックにいたのも「影の政府」だったのだ。彼らが両者を無理やりくっつけてまで中国統一を急いだというのが事の真相ではないだろうか。
ただ、これは結果的にうまくいかなかった。孫文の死後、蒋介石が北伐軍の総司令に就任すると、左右両派の対立が激化した。結局、蒋介石は浙江財閥を後ろ盾として、共産党員の大量粛清に踏み切った(上海クーデタ)。どうやら浙江財閥≒世界支配層は、蒋介石一択となり、あくまで彼に全国統一を成し遂げさせることにしたようだ。
一転して中国共産党は駆逐される立場になった。
私は、あの時期の中国共産党の信じがたい惨めさは、世界支配層の方針によって、まだ彼らの支配下にあったコミンテルンから見放されたからだと考える。逆にいえば、だからこそ、コミンテルンの支持のない毛沢東の発言権がどんどん党内で強まり、最終的に長征中において「ソ連派」を制して主導権を確立することができたのでないか。

一方、蒋介石は北伐を行い、満州を除いて中国の再統一を進めていく。孔祥熙は蒋介石の右腕として中国の産業政策を担う。当時の国民政府は政官財が一体となった利権共同体と言える。そして、欧米の支援を得て急速に近代化を進めていく。
中国という獲物をめぐって日本帝国と世界支配層がぶつかった
さて、第一次世界大戦が終了した直後の1920年代、欧米支配層が日本を排除しつつ本格的に中国の再統一事業を影で支援し始めたわけだが、興味深いことに1920年代といえばアメリカ経済の黄金期だった。そして、1929年の世界恐慌により、突如としてその繁栄に幕が下りた。私は何度も言っているが、これは世界支配層による米経済の「刈り取り」である。経済成長は19世紀の南北戦争後に始まり、1920年代に絶頂を迎えた。その後、人為的に引き起こされたNY株式市場の暴落によってアメリカを代表する企業の株は軒並み暴落し、7割がモルガンなどの世界支配層系列の財閥の手に落ちた。
つまり・・・彼らは「アメリカ経済が成熟し切ってそろそろ刈り取りの時期かな?」などと相談し合っていた頃、他方で、次の「種まき地」にも思いを巡らしていたわけだ。
その候補こそ、封建時代の呪縛を脱しつつあった中国だったのである。
彼らは中国の巨大なポテンシャルを見抜いていた。彼らが散々食い物にした清が滅んで混乱状態にあったが、今度は近代国家として統一させてやれば、必ずや経済成長を遂げて、投資の何十倍ものリターンがあるに違いないと、そう算段していたのだ。
蒋介石とその取り巻きは腐敗し国を私物化していたが、他方で愛国者でもあり、首都南京を中心として行政やインフラ、通貨・銀行制度、軍隊、医療・公教育などの近代化を強力に推し進めていった。その巨額の資金を支えたのが浙江財閥≒世界支配層だった。
ただ、北伐後の中国の本格的な近代化は、実ることなく潰えてしまった。
その理由が日本の侵略である。当時の日本のやり方で非常にまずかったのが、満州国建国よりもむしろその後の華北分離工作である。実は、孫文・蒋介石は日本の支援を得る代わりに日本の満州利権をかなり認めていた。だいたい、当時の中国人は漢民族意識が強く、満州は満州人の土地としか思っていなかった。しかし、華北分離工作で日本が関内(万里の長城の内側)に侵入してきた時、蒋介石は明確に日本の侵略と見なした。
そして、それは日本帝国と、英米を中心とする世界支配層との本格的衝突の始まりであった。それは他方で中国という「獲物」を巡る争いでもあったのである。
いわゆるシナ事変は1937年に始まり、1949年の人民中国の建国まで、中国は戦乱を強いられた。しかも、毛沢東の経済政策はめちゃくちゃで国を疲弊させた。
結局、中国が再び近代化を始めたが、1978年の鄧小平による改革解放路線からだ。見方によっては、日本の愚かな侵略のせいで、中国の近代化は50年後回しになった。そういう事情も承知した上で、ゆえに私は「毛沢東の鶴の一声で決まった日中条約はまずい、賠償金又個人補償分を支払う形に改訂したほうがよい」と書いてきた。
また、世界支配層がいかに日本を恨んでいるか、ということである。
ただし、長い目で見れば、中国共産党による支配は「毒をもって毒(欧米支配層)を制する」形になったわけで、日本の侵略がなければ中国は彼らに寄生されていただろう。
その欧米支配層はというと、かつての「成功体験」が忘れられないらしく、近年の中国株投資による儲けくらいでは、まったく満足していないようだ。
結論を言えば、近年の彼らの動きは、それが顕れたものではないか。
つまり、新中国の金融を牛耳ろうというシティの深慮遠謀である。人民元の国際的信用の保証人になることで、共産党に代わる中国の「次の政府」が誰であろうとも、イギリスの信任を受けなければならない仕組みを構築しているのかもしれない。
日本は今、欧米と一緒になって中国封じ込めをやっているが(それは全然構わないのだが)、一方で、中国が自由な国に生まれ変わったら、結局は獲物を独り占めしようとする世界支配層がまた敵に回る可能性があるということも、承知しておくべきである。
・玉蔵&山田高明 直前!未来スペシャルin 新宿 2月16日(土)
・玉蔵&山田高明 直前!未来スペシャルin 横浜中華街 2月23日(土)
当日飛び入り参加でもOK!









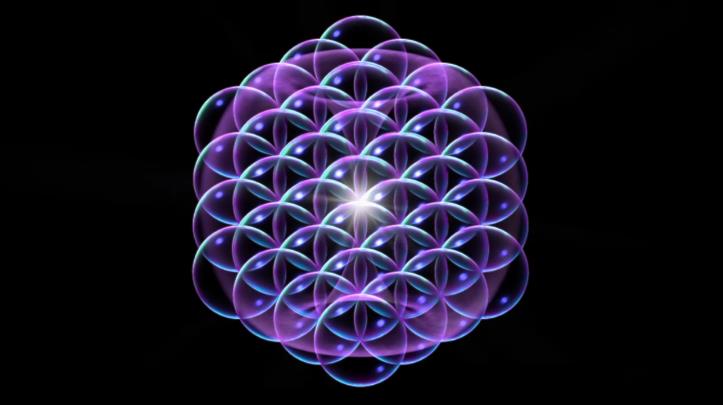


スポンサーリンク