ジャーナリスト高沢皓司氏の「『オウムと北朝鮮』の闇を解いた」第11弾です。
第一、これは大事な情報なので、もっと世間に広まるべき。
第二、様々なサイトに転載されてから、すでに15年以上も放置されている。
以上のことから、その公益性を鑑み、「著作権者の高沢氏からの抗議が来たらすぐにやめる」ことを条件にして、勝手ながら当サイトでも転載させてもらうことにしました。
(以下引用 *赤字強調は筆者)
「週刊現代 1999年11月6日号」高沢皓司(ノンフィクション作家)
村井秀夫は「北朝鮮の核」機密保持のために殺害された
村井秀夫の指示でオウム信者たちが原発に労働者として潜り込み、内部資料を持ち出していたことは、先週号で報じた。
では村井はなぜ、原発資料を集めていたのか。
それは彼が、北朝鮮が密かに進めていた「核開発」と接点をもっていたからなのだ。そして村井が口封じされた原因も、まさにそこにあった!
物理学の専門家だった村井
材井秀夫は“知りすぎた男”だった。オウム真理教をめぐる一連の事件のなかでも、もっとも深い謎に包まれている「科学技術省長官」刺殺事件――複雑に絡み合った謎の周辺をほぐしていくと、これまでマスコミで報道されてきたオウム真理教の顔だけではなく、もうひとつ別の顔をもった教団の姿が、浮かび上がってくる。
教団武装化を唱えはじめたオウム真理教の突然の転換の背後には、北朝鮮の影が濃厚に見え隠れしはじめる。さらに、偽ドル、サリン事件の謎と毒ガスの入手ルート、北朝鮮工作組織の介在、流出した原発の極秘データとその行方という、新たな疑惑が露出してきた。そして、それら教団内部の最高機密に属していたであろう事がらを、彼=村井秀夫はことごとく知り得る立場にあったのである。
その村井が不用意に口を開きかけたとき、陰の工作者たちは戦慄した。村井の発言がもたらす波及力は、教団という組織内部にとどまるものではなかったからである。
しかし、たぶん村井秀夫がそのことを完全に自覚していたとは言いがたい。村井は自分が知っている事実が白日のもとに曝されたとき、国内外にどのような波及カ、破壊力をおよぼすかについて、無自覚であっただろう。
村井秀夫刺殺事件は、オウム真理教および村井個人の思惑などを越えたところで、大きな闇の世界の力学によって引き起こされた事件であったように思える。この事件の背後には、国際的な陰謀と謀略、政治が渦を巻いて存在していた。
村井は、各地の原子カ発電所にオウム信者を送り込むにあたって、
「今度、行くときにはどんな資料でもいいから持ってこい、これはいいデータとして使える」と、語っていた。
また、どこが参考になるのかわからない、と言う信者に対して、「オレは専門だから、たいていのことは見ればわかる」と語っていたという元信者の証言もある。
ここで村井の経歴と専門分野、プロフィールを、少しだけ辿っておく必要がありそうである。
村井は1958年12月、京都市で生まれた。1977年4月、大阪の府立高校を経て大阪大学理学部物理学科に入学、大学卒業とともに大学院修士課程に進み、宇宙物理学を専攻。このときの研究テーマは、惑星から出るX線の研究だった。
修士課程を修了後、1983年4月、神戸製鋼に就職。機械研究所の研究員として、航空機関係の研究に従事。熱心な学究肌の研究者だった。
その村井にわずかな変化の兆しがあらわれるのは、1985年頃、彼は次第にヨガに夢中になるようになり、神秘主義にあこがれるようになる。この年、職場の同僚だった女性とネパールにおもむき結婚式を挙げる。
オウム真理教との出会いはそれからほぼ2年後、彼がたまたま麻原彰晃の著作を読んだことからはじまる。村井は麻原の著書に非常な感銘を受け、研究所を退職し、妻とともに出家を決意。その後の村井は1995年4月23日、東京・南青山のオウム真理教総本部前で、徐裕行によって刺殺される運命の日まで、オウム真理教という教団と運命をともに、一気に短い人生を駆け下りていった。
この経歴からわかるように、村井は物理学徒として、きわめて専門的な知識を身につけ、実際に民間企業での研究の最先端の場に身を置いていた人間であったのである。
「オレは専門だから……」という村井の発言には、誇張も衒いもなかった。
究極の教団武装化は「核」開発
先週号で指摘したような、国内各地の原発の機密データも、村井の目には研究所で日常的に目にしていた多数の書類と同じものに見えていただろう。彼は、そこに現在稼働中の原発の状態、点検工程、不備などを手に取るように見ていたはずである。
村井についての印象的な写真が残されている。教祖・麻原の横にいる村井が、麻原と一緒にいることで喜びを隠し切れないという表情を浮かべ、天真爛漫な笑顔で写っている写真である。その村井が、信者たちに原発の機密データの持ち出しを指示し、
「持ってくればカルマが落ちる」と、言っていたことは、村井自身もまた、そのことを信じていただろうことを、容易に窺わせる。
一方では自分自身も宗教的な存在として「ハルマゲドン」におののき、一方では冷静な科学者の目で、村井は手元に集められてくるデータの集積を見続けていたに違いない。彼に、そのことに対する罪の意識は、たぶん、なかった。だから、彼=村井にとって、それらの資料が国外に流出することについても、危険の感覚は存在していなかったに違いない。
村井の人生を私なりに辿る作業をしてみて、なぜかそんなふうに思えてくるのである。
村井がオウム真理教の活動のなかで、これら原発の機密資料を収集するだけではなく、さらにそれを越える途方もないことを考えていたらしいことを、私はいま、リアルに感じ取っている。
村井は、オウム真理教「科学技術省長官」として、サリンをはじめとする毒ガスの生産研究、生物化学兵器の研究とほぼ同時に、教団自らが独自に「核」開発に手をそめることを、真剣に考えていた痕跡があるのである。
村井が核開発のことを、たびたび周辺の信者たちに語っていた、という証言がいくつかある。周辺の信者たちにとって「核」開発の話は、原発の機密データと同じく、ある種のブラックホールであり、理解不可能なただの話にすぎなかったかもしれない。
しかし、村井秀夫についてのみ考えてみれば、あながちそれが単なる空想、夢想にすぎなかったとは思えないのである。オウム真理教のもつ豊富な資金と北朝鮮コネクション、そしてそれらを背景にして教団武装化を至上命令として考えたときに、村井「科学技術省長官」の脳裏をよぎったものは、究極の教団武装化としての「核」開発であった。
一致したオウムと北の利益
オウム真理教「科学技術省」が究極の獲得目標として「核」武装を射程に入れていたのだとすれば、ここに不気味な国際政治の裏面が浮かび上がってくる。その構図は次のようなものである。
1982年5月6日、金正日による「よど号」のハイジャッカーに宛てた「親筆指令」から始まった日本国内の破壊・攪乱工作指令は、「よど号」グループのいくつかの試みを経ながらも成功することはなかった。この工作をいかに実現するかで、「よど号」グループは組織内部に路線対立を生じ、メンバーのひとり岡本武の粛清問題にまで発展していく。
彼らは日本国内に潜入し、さらにヨーロッパ各地で人員獲得のために「拉致」事件を引き起こす。しかし、’80年代末にいたって逮捕者が相次ぐなか、この企ては挫折する。
そこに代わって登場してきたのがオウム真理教だった。オウム真理教は、それまでの「オウム神仙の会」のころのヨガ道場的な存在から、一挙に教団武装化を唱えはじめ、世界各地で宗教を隠れみのにした活動を開始する。この段階で、相当大量の資金導入が外部から行われたことは、元幹部の証言にも詳しい。
そして、どうやらこのときの導入資金の大半が、いわゆる偽ドルだったらしいことも指摘した。ちょうど、この時期は、北朝鮮による偽ドル疑惑がさかんに取り沙汰されはじめた時期の直前にあたっている。
当時、教団が北朝鮮の工作組織とヨーロッパを中心とする各地で接触を図っていたらしい痕跡がいくつか残されている。教団はこれらをきっかけとして徐々に、北朝鮮との関係を深めていった。村井秀夫「科学技術省長官」と、同じ教団幹部、早川紀代秀「建設省長官」がともに頻繁にロシアに渡航し、さらにウクライナにも入国していたことがわかっている。さらにウクライナの首都キエフやハリコフから、ハバロフスク経由で北朝鮮に入国していた痕跡が多数残されている。
この段階で、オウム真理教の北朝鮮コネクションは、ふたつの軸を中心に動いていた。ひとつは、かねてからの宿題である日本国内の攪乱工作。もうひとつは、北朝鮮側が必要としていた日本のハイテク技術、ソフト、製品の需要である。同時にロシア、ウクライナ・ルートによるプルトニウム輸入などの「核」開発関連である。
ところが、ここに北朝鮮とオウム真理教を結ぶ第三の軸が、先のふたつの軸を発展させた形で浮上してきた。オウム真理教自身の武装化としての「核」開発が、村井秀夫「科学技術省長官」の教団武装化構想のなかで、課題にのぼりはじめたことである。
偶然というか、奇妙なことに両者の利益がこのとき一致した。オウム真理教の「核」武装化は、北朝鮮が狙う日本撹乱・破壊工作の上では、原発のデータ流出とともにきわめて重要な位置を占める。さらにオウム真理教側にとって、北朝鮮という新興の「核」開発をめざす国家の存在は、有形無形の大きな意味を持っていた。
オウム真理教側は、この構想にもとづいて北朝鮮に食い込もうとし、北朝鮮側は、オウム真理教を可能な限り利用しようとした。これが、1990年代中頃、地下鉄「サリン」事件が引き起こされる直前までの構図である。
「よど号」犯の妻に接近した狙い
しかし、実際にはどうであったのだろうか。これらのお互いの思惑と構想は、どこまで有効に結びついたのだろうか。
結果は、どうやらその大半が実現されることなく終わったとしな言いようがないのである。いくつかの傍証がある。
日本の「核」技術開発の中心のひとつである、筑波研究学園都市、ここの関連研究施設に、オウム真理教の幹部たちが幾度か接触を試みたことがあった。しかし、この試みはどうやらあまりうまい結果を生んでいない。
さらにちょうどこの時期、ピョンヤンにいた「よど号」グループのリーダー・田宮高麿は、日本から合法的に多くの人材を北朝鮮に招請する計画を立てていた。それは民族派の人間であったり貿易関係考であったりしたが、その中に科学技術関係者も含まれていたのである。このことは、オウム「科学技術省」の村井秀夫が意図し構想していたであろうようには、北朝鮮側の核開発関連技術導入の「筋」が、まだ確定したものではなかったことを示している。
これと関運して、1991年10月20日、東京・練馬区の練馬文化センターで開かれたオウム真理教主催の「真の自由と平等を求める市民の集い」という集会に、「よど号」グループの「妻」のひとり、八尾恵がパネリストとして出席したことで、オウムと北朝鮮の関係が、「赤旗」紙上や週刊誌などで取り上げられたことがあった。
この集会については、オウム側から青山吉伸弁護士、鹿島とも子などが出席し、人権派として千代丸健二、救援連絡センターの事務局長・山中幸男などが参加した。八尾恵はこの当時、報道被害などを訴えてマスコミ訴訟をつづけており、救援連絡センターの事務局員として働いていたことから、この集会に参加している。
この集会に「よど号」の「妻」のひとりが参加していたということをもって、「赤旗」は疑惑に満ちた記事を書いたが、実際にはなんの根拠もないうがった記事だった。
しかし、問題は彼女がこの集会に参加したことにあったのではなく、じつはこれ以前から八尾の裁判支援にも、オウム側から青山弁護士を含む複数のアプローチが行われていたことである。当初はオウム側が、一種の「広告塔」として八尾を利用しようとしているのではないか、とも考えられたが、グループのリーダー田宮は、私が訪朝したおりに直接、その理由を尋ねたとき、じつに明快な答え方をした。
「オウムは八尾さんを介してわれわれとコンタクトを取ろうとしているのではないか」と。さらに、「オウムはわれわれを通して共和国とコンタクトを取りたがっているのではないか」と。
これらのことを考えあわせると、オウム真理教にとってもこの時期にはまだ、明確に北朝鮮側の窓口が一定していなかった、ということがわかってくる。
そして、オウム真理教と北朝鮮側の窓口がまだ不安定であったが故に、オウムの「核」による究極の教団武装化計画は実現するにはいたらなかった。幸運なことに、オウム真理教が自作自演しようとした「ハルマゲドン」計画は、回避されたのである。
核査察問題で野望は挫折した
ではなぜ、北朝鮮の「核」開発にとって、ロシアではなく日本の一宗教団体がそこに食い込む余地があったのだろうか。この答えは簡単である。
北朝鮮は自国の「核」開発のために、ロシアから多数の学者、研究者をピョンヤンに招請していた。その担当部署が朝鮮労働党第二経済委員会であったことも、今では周知の事実となっている。しかし、北朝鮮の工業技術、ハイテク技術の技術体系には、明らかにもうひとつの「筋」が存在していた。それが、日本の工業技術でありハイテク技術であったのである。
朝鮮総連をはじめ、その傘下の在日朝鮮人科学技術協会(科協)などの団体が、これまでに極めて大量の技術、研究成果、および資材を日本から「祖国」北朝鮮に輸出していることは紛れもない事実であり、これが合法的・非合法的な領域を問わずに、これまでつみ重ねられてきたことは多くの指摘がある。
いわば北朝鮮には、ロシア型の技術体系と日本型の技術体系が混在していると言ってよい。その上、現在のハイテク技術の分野では、圧倒的に日本型の方が部品等の製品事情を含めて優位にたっている。北朝鮮のミサイルや潜水艇の部品に、多くの日本製品が使われていることがマスコミで問題視されることの理由もそこにある。
この日本型の技術体系下で行なわれる研究や開発にとっては、小さな部品やIC機器のひとつにいたるまで日本製品の方が便利であることは言うまでもないだろう。そこに、日本からの研究とデータが北朝鮮に求められる意昧が存在している。
北朝鮮側がオウム真理教を利用して、日本の原発の資料をはじめとする研究レポートを入手しようとした理由の大半も、そこにこそあった。
また、オウム真理教側にとっては、国内では所有不可能な研究施設や研究体制が、北朝鮮側から提供されれば、それに越したことはなかったのである。
しかし、このオウム真理教「科学技術省」の構想は挫折した。
1993年3月、北朝鮮のNPT(核不拡散条約)脱退宣言から、核査察の受け入れと拒否をめぐる1994年6月のIAEA(国際原子カ機関)脱退という、一連の北朝鮮核開発疑惑をめぐる国際政治の荒波のなかで、この構想は着手されなかった。
むしろ、あの朝鮮有事に向けた一触即発の状況のなかで、このオウム真理教の構想に、北朝鮮がどんな些細な部分においても関与していることは、どうしても闇に葬らねばならない「事実」だったのである。
村井秀夫「科学技術省長官」刺殺事件の背後には、そうした国際政治の闇の部分が、ブラックホールのようにうず巻いていた。オウム真理教が引き起こした一連の事件への北朝鮮の関与、工作組織の存在は、村井の命を奪ってもなお、死守しなければならない機密に属していた。
サリン事件をはじめとした多くのオウム真理教によるテロ事件、これらの事件の犠牲者の数は多い。さらに親兄弟を失った家族の悲しみもいまだにいやされることがない。一連のオウム真理教の事件の背景になにがあったのか、その真相を明らかにすることが、犠牲となった人々への何よりの鎮魂、手向けであるのではないだろうか。日本政府は、これらの事件の真相と背景について、そろそろ明らかにするべき時期が来ていると思うのだが。
最後に一言。この連載は今回でひとまず終わらせて頂くことにしたい。短期の集中連載という形で始まったこの記事も今回で11回目を数えた。鈴木哲編集長の「ライブでやれ!」との一言で始めさせていただいた記事だったが、いくつかは新しい事実、真相を提示することができただろうと考えている。あらためて取材の態勢をとりなおした上で、再開できる日を待ちたい。このテーマはオウム真理教と北朝鮮という国家が存在するかぎり、私にとってのネバー・エンディング・ストーリーである。
(文中敬称略) ■取材協力 時任兼作、今若孝夫、加藤康夫(ジャーナリスト)
(以上引用終わり)







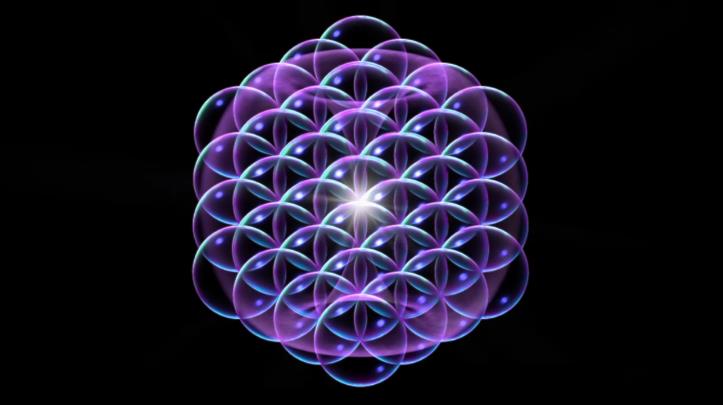




スポンサーリンク