ジャーナリスト高沢皓司氏の「『オウムと北朝鮮』の闇を解いた」第5弾です。
第一、これは大事な情報なので、もっと世間に広まるべき。
第二、様々なサイトに転載されてから、すでに15年以上も放置されている。
以上のことから、その公益性を鑑み、「著作権者の高沢氏からの抗議が来たらすぐにやめる」ことを条件にして、勝手ながら当サイトでも転載させてもらうことにしました。
(以下引用 *赤字強調は筆者)
「週刊現代 1999年9月18日号」高沢皓司(ノンフィクション作家)
まさに「対決」という言葉がふさわしいインタビューだった。講談社ノンフィクション賞を受賞した高沢氏の鋭い質問に、最初は努めて冷静だったA(46歳)が、徐々に追いつめられ、渋々、事実関係を認めていく。そして取材の最後には、こうつぶやいたのである。
「僕の身は危険でしょうかね—」と。
深夜電話を卸けてき走謎の男
時計の針は、午前一時を少し回っていた。突然、電話が鳴った。マドリッドでのことである。夜の底から伝わってくる男の声が、「そちらが探しているAという男のことを、よく知っている人間が見つかった」と言っている。昼間の男だった。
私たち取材班は、オウム真理教に潜入していたとみられる北朝鮮「工作」組織の実態を追いかけて、スペインの首都・マドリッドに来ていた。Aは、そうした疑惑の濃い一連の人物のなかでも、とりわけ不可思議な経歴を持つ男だった。北朝鮮への度々の渡航歴、チュチェ(主体)思想研究会会員、チュチェ思想国際研究所の局員という経歴。
そして、ヨーロッパにおける北朝鮮の重要な工作拠点である、スペインでの長期滞在とその後の頻繁なマドリッドヘの渡航。
そのAは、滞在中のここスペインからオウム真理教に入信し、目本への帰国とともに出家して、教団施設内で武器製造に携わっていた。1995年の一連のオウム真理教テロ事件のあとは突然に教団を脱会し、ふたたび頻繁な海外渡航をくり返している。
前々日の昼間、私たちはこの電話をかけてきた日本人の男と、はじめて接触していた。ごく一般的な取材のあと、Aのマドリッドでの生活ぶりを質問したのである。
本来ならば、私たちの取材は、この男に対するかぎり、そこで終わるはずだった。ところがここにきて、その男からの深夜の電話である。
「いまからホテルに行ってもいいか? 証人を連れていく」
男は電話口でくり返していた。
「……わかった。OKだ。それではロビーで」
ロビーに降りると、まだ人の姿があちこちに見えた。夜会の終わりだろうか、着飾ったドレス姿の女たちも見える。フラメンコの旋律が耳に届いた。
夏のマドリッドの夜は、たしかに遅い。しかし、それにしても深夜の1時半だ。どこかで疑念が首をもたげるのを感じていた。
しばらくして男の姿が見えた。最初に聞いてきたのは、私たちのその日の動きと、どこまで取材の成果が上がったのか、ということだった。
言葉を選んで、慎重に対応する。業を煮やしたのか、いきなり男が言った。
「Aはオウムですよ。自分では隠しているようだが、彼はオウムにまちがいない。スペインに来てまで、何をしようとしていたんですかね。Aのことは、ここにいる彼がよく知っていますよ」
男に促されるようにして、連れられてきた証人と称する第二の男が口を開いた。日本語。朴訥(ぼくとつ)な話し方だ。ふと、暗記した台詞をそのまま話しているのではないか、という印象すら受ける。
「ええ、あれはAが日本に帰国する1ヵ月ほど前のことですが、オウムの本を持ってきて、内容が自分の考えとよく合っている、自分も会員になりたいと思っている。だから日本に帰る、と。そう、本以外にも尊師の書いた文章だというもののコピーも持っていました」
「それから『スペインには支部がないから、そのうちこっちにもつくりたい』というようなことも言っていました。それ以前は、そんなことを言ったことはありませんでしたが。Aはあまり人付き合いがよくなくて、ひっそりと行動していたようなので、ほかにも勧誘された人間がいたかどうかはわかりません」
――その話を聞いたのは、いつ頃のことですか。
「ええっと、Aが帰国する頃でしたから’92年です……」
――オウムと言われたときにすぐに分かりましたか。
「ええ、すぐに分かりました。いろいろと問題のある宗教でしたから」
Aと北朝鮮の関係を隠す意図が
私たちは彼の証言を興味深く聞いていたが、この答えを聞いて、あらためて疑念が湧き出してくるのを感じた。どこかが少しだけ、ずれている。そんな不協和音を感じたのである。
1992年、Aがスペインでの長期滞在を切り上げて日本に帰国する当時、オウム真理教の名前がそれほど有名だったとはとても考えられない。
教団の犯罪はまだなにひとつ露見しておらず、世界を震撼させた一連のテロ事件もまだ実行されていない。なによりAが、これから日本に帰国して出家しようとする時期のことである。オウム真理教は、世間的にはまだローカルな新興宗教のひとつに過ぎなかった。しかもこれは、日本ではなくスペインでの話である。
話の最後に、私たちはマドリッドを舞台にした「よど号」のハイジャッカーたちによる「拉致」事件のことを話題にした。話のなりゆきというものだったろう。
「どうやら、いまでもマドリッドには北朝鮮の工作拠点があるようだし……」
その一瞬、電話の男の視線がきつく鋭さを増し、こちらを刺しつらぬくのを私たちは、はっきりと見ていた。
この話には後日談がある。くだんの男が、私たちが取材を終えて帰国したのちにも、私たちのことを誰彼なく聞き出していたという話が噂となって伝わってきた。さらに、あの日の深夜の顛末話すと、普段の男を知るほとんどの関係者が首を傾げた。
そして、私たちはこの男が、やはり「マドリッド在住の他の日本人とはどこか違う人物」(男の知人)であるという証言や、日本国内で北朝鮮と密接なつながりのある人間であることに、ようやく辿りついたのである。
では、これはいったいどういうことか。北朝鮮と関係の深い真夜中の電話の男が、同じく北朝鮮と関係の深いAのことをあしざまに非難している。Aは、オウムの信徒で、いかにも悪いやつだ、と。
私たちは、そこで恐ろしい疑念に突きあたった。男の深夜の来訪の意図は、Aの背景から「北朝鮮」という絡みを極力取り除き、隠し通すことにあったのではないのか。そのためにこその電話であり、不自然な「証人」だったのではなかっただろうか、と。
「Aは単純にオウム真理教信者であり、あいつは北朝鮮とはなんのつながりも持ったことがない」
と私たちにアピールすることが目的だったのではあるまいか? 私たちは、問題の男A本人に、どうしても一度、詳しく話を聞く必要を感じていた。
精惇で猛禽類の鋭さをもった目
Aと連絡がとれたのは、それからしばらくのちのことだった。Aは最初、話をするべきことはなにもない、と頑なに取材を拒否していた。何度かの電話でのやりとりのあと、しかし、ようやく私たちはAに直接の疑惑をぶつけることができた。
Aは精停な顔つきで、がっしりと鍛えられた体つきをしていた。目の表情に時折、猛禽類の鋭さが宿る。ただ、なにがしか陰りが感じられたのは、気のせいだったのだろうか。
Aは自分がチュチェ思想研究会の活動をしていたことも、オウム真理教にいたことも、すぐにすべてを認めた。
「いまは、どちらもやめていますが……」
話はチュチェ思想とのかかわりから始まった。
――チュチェ研にかかわった経緯は?
「高校時代は全共闘の運動が盛んで、(生まれた)地元の広島大学には中核派が多かったのですが、僕自身はまだノンポリでした。1969年に京都の大学に入り、自治会の活動をやっていました。卒業は’74年です。部落解放運動や朝鮮問題などをおもにやっていました。でも、セクトの運動にはそれほど熱心になれませんでした。
大学の3~4年の頃、チュチェ研の人間と知り合い、人間が中心であるというその思想と響きのよさに引かれて、活動にのめり込んでいきました。でも、最初から組織生活を強いられ、窮屈だなあ、という印象が強かったです。そう思いながらも、ずるずるとつづけて、組織のなかでの役割もだんだん大きくなっていったんです。
その後、支部長として、ほかのメンバーとふたりで和歌山にオルグに行ったんですが、結局、うまくいかなかったですね。多くて4~5人しか集まらなかった。そのころ、東京からチュチェ思想国際研究所に来ないか、という声がかかって上京しました。
当時の事務局長は尾上健一さんでした。そこで4~5年間、研究員をしていましたが、’85年には辞めています。私にとっては、研究所内部のあり方に不満がつのるばかりで、なにより尾上さんに対する反発が大きかった。そのころ同じチュチェ研の仲間だった妻も、別の理由ですでにやめていました」
取材班は、チュチェ研、さらには国際研究所時代のAを知る尾上健一事務局長に何度も連絡を取っているが、彼からの応答はこれまでのところいっさいない。
Aの話をつづけて聞くことにする。
――尾上氏への反発とはどんなものだったのか。
「口ではチュチェ、チュチェと言ってるわりには、その思想に反して人間的には堕落しているような印象を受けました。強権的で厳しく、ちょっとしたミスに対する処分の厳しさにもうんざりさせられましたね。私が研究所を離れたのは、チュチェ思想そのものに反発したわけではなく、所属した組織そのものへの反発でした。何度か、戻ってこい、と言われたこともありましたが、もう、気持ちが駄目でした」
Aは、チュチェ思想そのものに幻滅したのではなく、組織への反発だった、という。研究所はやめたがチュチェ思想を捨てたわけではない、という他の人物がいることも私は知っている。
「チュチェ思想はすばらしい」
――いまでもチュチェ思想は間違っていない、と思っていますか。
「チュチェ思想自体は、人間中心という意味で、すばらしい思想だと思っています」
――では、どうして才ウムに入信したんですか。
「純粋に自分の宗教心からでした。どこかの組織の指示で潜入したということではありません」
――しかし、チュチェ思想とオウム真理教では、あまりにも隔たりがあるように見受けられますが。
「潜入したということではありません。オウムのことを当時はゴキブリも殺さない暖かい宗教だと思っていましたから」
――でも、オウムは無差別なテロ事件を引き起こしています。
「オウムには、ヴァジラヤーナという教えがありましたから……」
ヴァジラヤーナの戒律には、殺人を正当化する教えが含まれていることは知られている通りである。オウム真理の教はこの教えに法って人をポアしてきた、といわれている。
――スペインにはなぜ?
「チュチェ思想国際研究所にいたとき『南米からもいろいろな人や資料がくるから、お前、翻訳をやれ』と言われたのがきっかけです。大学の第二外国語がスペイン語だったこともあって、研究所から金を出してもらって、語学校に2年半ほど通っていました。チュチェ研をやめてから、何ができるかを考えたときに、スペイン語を生かすことができれば、と考えてスペインに行こうと考えたんです。.語学留学です」
――質問を急に変えることになりますが、柴田という男を知っていますか。
「いえ、知らない。どういう男ですか?」
「よど号」ハィジャックのメンバーですが。そ.の柴田が何度か泊まっていたマドリッド市内のホテルに、あなたも何度か泊まってますよね? Oというオスタルですが。
「知らないなあ……」
――あのオスタルは、北朝鮮の工作拠点にされているとの疑いもありますが。
「えっ、そうなんですか? 僕はぜんぜん知らないですよ。あっ、2~3日、泊まったことがあったかもしれません。おばちゃんがいますね、たしか……」
――あなたは、当時、北朝鮮の「工作員」だったのではないですか。すべての相関図の中心にあなたの存在があるのですが。
「とんでもない。僕は100パーセント、潔白ですよ。正直言って、そんなことを北から頼まれたことも、やったこともいっさいありません」
――いまは、どうですか。
「もちろん、潔白です」
ここで質問者は、Aのマドリッド滞在時に周辺にいた、北朝鮮と関係が深いと思われる人間の名前を何人かあげた。いずれも当時、親しく付き合っていたとされる人たちである。
――○○さんを知っていますか?
「知らないなあ」
――○○氏のことは?
「知らない」
――○○氏はどうですか。
「記憶にないなあ」
しかし、これまで冷静に対応していたAが、わずかに動揺を見せたのはこのときである。そして、このときと、あと一度だけだった。これだけの直接的な質問をぶつけられながら、Aは終始、その冷静さを崩さなかった。ときおり、眼光がするどくこちらを射抜いた。私は、そこに金日成主義者の強固な意志をみたように思った。
――じつはマドリッドでは、あなたについて悪い噂が流れています。
「えっ、なぜですかね。半年くらい部屋にこもって、ヨガの修行をしていたことがあったので、そのせいかな」
――○○氏(先述した深夜の電話の男)のことは知っていますか? 彼も京都にいたはずですが?
「えっ、それは知らなかっ.た。彼もチュチェに?」
――なぜ、あなたについて悪い噂が広がっていると思いますか。
「チュチェ時代に『あいつは日和見主義的な立場をとっている』と思われていたからでしょう」
――北朝鮮には何回くらい行きましたか。
「3回。そのたびに比較的長い期間を向こうにいました。一度は3ヵ月くらいいたこともあります」
――そのとき「よど号」のメンバーとは会いましたか。
「いえ、僕は会っていません。代表団としていった時など、ほかのメンバーは会った人もいたようですが」
ここでAは意外なことを言った。
北朝鮮に何度か滞在していた時、黄長ヨプ元朝鮮労働党中央委員会書記とは何度も会ったことがある、というのである。黄は金日成、金正日父子の側近中の側近である、超大物だ。彼のチュチェ思想研究はこの黄長ヨプ書記から直接、指導を受けたものだったらしい。
黄書記は、その後、1997年2月、韓国に亡命し、世界中に衝撃を与えることになったのだが、Aからそのことについての感想を聞くことはできなかった。ただ、この話のなかで、Aが日本のチュチェ思想研究気のレベルよりははるかに深く、金日成主義とチュチェ思想にのめり込んでいたのだということだけは、わかった。
もう一人の潜入工作員は医師
――いまの北朝鮮についてどう思っていますか? あるいは金正日についてなど。
「チュチェ思想については、いまでも間違っているとは思わないけど、北朝鮮という国のことになると、僕なんかが何かを言うというものではないと思うんです」
――オウム真理教に入ったのも北の指示ではなかったのですか。
「ありえない話ですよ。チュチェのメンバーで、工作員になっている人間なんていないはず。上からそんな指示を受けることもないし、北の御用機関になることもありえない」
――金日成主義には「領導芸術」という言葉があるように、知らず知らずのうちに相手を誘導していく技術というものがある。優秀なチュチェ思想の活動家であるあなたにとって、それは容易いものではなかったのか。心理的な誘導というか、相手が自分の意志であるかのようにひとつの方向を選んでいく、という……。
Aの顔色が、一瞬、さっと変わった。そしてこのときが、冷静沈着なAに、わずかに内面の動揺がかいま見えた2度目だった。
「あなたは、領導芸術という言葉を、そんなふうにしか理解していないのか!!」
言葉は激しく、そう言い放ったAだったが、次の瞬間には、即座に冷静なAに戻っていた。
印象的な一幕だった。
――しかし、いろいろなデータは、あなたがそうであってもおかしくないことを指し示している。悪い噂もささやかれはじめている。もし、あなたがスケープ・ゴートにされているなら、その疑惑を晴らす意味でも、もっと本当のことを語るべきではないか。
「たしかに自分の目標を持って入り、その目標を達成できずに組織から出てきたわけだから、自分なりに総括はすべきだとは思う」
時間はあっという間に過ぎていた。これだけの話を終わって時計を見ると、すでに話しはじめてから2時間以上が過ぎていた。このインタビューの内容は、できるかぎりAの発言を正確に再現するようにつとめた。取材班の立場だけでなく、Aの言い分もはっきりと伝えておきたいがためである。結局、Aは私たちの疑惑をすべて否定した。
別れ際、Aはふっと、「僕は危ないですかね……」と言った。
「ひとりで歩かない方がいいかもしれませんね」と、私は言った。
「告発するなら、味方になります」と私は付け加えた。
さて、ここで私は、このAに連なるBという疑惑の「潜入工作員」について、そろそろ語りはじめなければならなくなった。
Bは’62年生まれ。長野の大学の医学部を卒業し、共産党系の病院に入局。その後、日本国内における北朝鮮の工作活動拠点の一つとの疑惑がある、東京都内の病院に、なぜか突然、転職し、さらにオウム真理教附属病院で医師として働きはじめる。
「Bは特別な信徒だったので、よくおぼえています。’94年に入信後、すぐに幹部待遇(師補)となってホーリーネームをもらい、麻原とも直接にいろいろとやりとりをしていました。彼の冷然とした態度、違法行為をも平然と行う姿が教団内部でも印象的でした」(元信老の証言)
私たちは、このBについて、音信の途絶えていたAに連絡をとった。すぐさま、代理人から、今後いっさいの取材に応じる気持ちはない旨の通告があった。
しかし、その翌日のことである。Aから、ふたたび代理人を通じてメッセージが届き、「Bという人については知りません。私は、医師と接触することはほとんどなかった」とあった。
(文中敬称略、以下次号)
■取材協力 今若孝夫、時任兼作(ジャーナリスト)
(以上引用終わり)







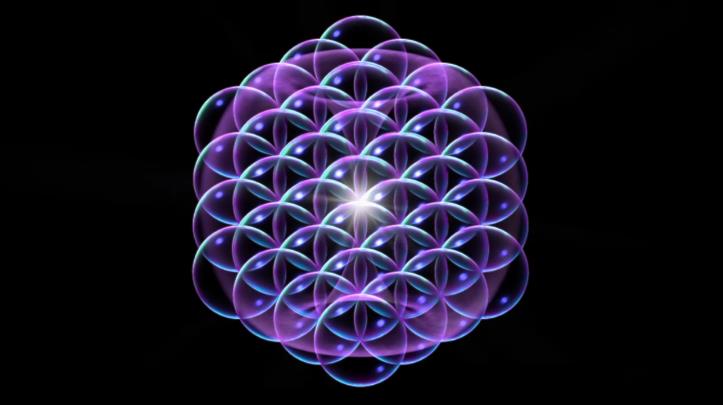




スポンサーリンク