中国は国民主権というレベルにはほど遠いが、「大衆が力を持ち始めた」という事実、またそれによって中国が動かされることもあるという可能性は、頭に入れておくべきだと思う。本来ならばそれは民主化の進展を意味するので喜ばしいことなのだが、大衆の受けてきた政治的な教育の質などを考えると、「大衆の台頭」は率直に喜べない部分も大きい。
江沢民の上海閥の誕生
順を追って説明したい。
1983年11月、政治改革を進めていた胡耀邦総書記が訪日し、日本の国会で始めて演説した。当時、胡耀邦氏と中曽根康弘氏は「平和友好 平等互恵 長期安定 相互信頼」という“四原則”に合意した。
おそらく、この時が“日中友好”の絶頂だったのかもしれない。
中曽根氏が回顧するところによると、彼が靖国参拝を取りやめた理由は、胡耀邦の立場をおもんばかってのことだという。当時、保守派は、表面では日本を非難しながら、本心では自由化路線の胡耀邦を攻撃していた。
つまり、中国で突如始まった「靖国参拝非難」も、元は国内の権力闘争から始まった「指桑罵槐」なのだ。その胡耀邦は結局、学生デモを理由に失脚し、89年の天安門事件が起こるきっかけとなる。

当時、戦車の前で踏み止まったある男性
当時、中国の政局はひどく混乱していた。そこで鄧小平ら長老たちから「よし、とりあえず、おまえがやれ」という感じで総書記に指名されたのが元上海市長で一政治局員だった江沢民だった。軍歴もなく、当初は誰が見ても暫定的なパペットだった。事実、直後に起こった(第二次)天安門事件では、江沢民の出る幕はなく、鄧小平が直接、軍部に命じて鎮圧させた。つまり、鄧小平こそ虐殺の張本人である。
ところが、その後の江沢民は意外にもしたたかだった。無難な政局運営の一方、軍部に対しては昇級人事を乱発して支持を獲得する。そして事件後に高まっていた人民の怒りや不満の矛先を反らせ、共産党に対する信頼と求心力を今一度高める手段として「憎日キャンペーン」を始めた。一方で、日本を利用することで、西側の経済制裁を解除することに成功する。彼はこれで党難を救った。さらに目の上のタンコブだった北京市長の陳希同を追放し、次第に存在感を増していく。急激な経済成長も彼を後押しした。
江沢民は、このように軍指導部を刷新し、かつての部下を次々と登用する巧みな廃立人事によって着実に自らの基盤を固め、一大「上海閥」を創り上げた。その過程で、鄧小平をはじめとするかつての長老たちは、ほとんど死に絶えてしまった。かくして、02年に胡錦濤政権が誕生して以降も、最高権力者としての地位を保持したのである。

江沢民が作った憎日紅衛兵と反日教育
ところで、この「憎日キャンペーン」は、単なる一時的な反日ではなかった。本当は公教育とマスメディアを総動員して国家が推進した「日本悪魔化政策」だったのである。党中央の対日姿勢転換を敏感に嗅ぎ取った知識層も大挙してそれに加担したこともあり、以後、対日偏見が異常なほど拡大生産されていく。結果として中国人は、「日本人は過去の戦争をまったく反省しておらず、未だに軍国主義的な野望を捨て切れず、両岸統一を妨害している根っからの悪人だ」といった憎悪と偏見を今日まで妄信するようになる。
恐るべきはその政策下で育った青少年である。大雑把にいえば、今の40歳未満の中国人に当たる。彼らは悪しき教育により、「われわれは日本から酷いに合わされた、しかも相手は謝罪も反省も一切してない、だからやり返す権利がある」と信じ込まされ、復讐心を植えつけられている。また、「中華民族の利益を実現するためなら他の民族をいくら犠牲にしても正当化される」と、本当に悪びれることもなく信じきっている。彼らは毛沢東が純粋培養した紅衛兵に似ている。かつて毛は青少年を扇動し、政敵に「走資派」のレッテルを貼って葬った。今ではそのレッテルが「親日的=売国」なのだ。
05年3月、日本の国連安保理常任理事国入りに反対するデモが中国各都市で燎原の火のごとく広まり、日本の大使館や領事館、商店などが襲撃を受けたことは記憶に新しい。「第一次反日暴動」とでも呼ぼうか。胡錦濤政権に面当てするために上海閥がデモを使嗾したとも噂されているが、当局によって操作されていたとはいえ、いずれにしてもこれは大衆感情抜きには説明できない現象でもあった。デモの主力である「憤青」たちが反対の根拠とした中には、「日本は戦争被害国への謝罪と賠償を拒否している」「日本は歴史教科書を改ざんし、侵略の歴史を教えていない」といった、事実に基づかない典型的ともいえる対日偏見や先入観があり、彼らがいかに政治的な洗脳を受けてきたかが分かる。
他方、50代くらいの中国人に訊くと、口をそろえて「学校では南京大虐殺の事は一度も教わらなかった、われわれはソ連こそが中国の仇敵だと教わった」と言う。ところが、彼らより二十年くらい下の世代になると、「日本のイメージ=南京大虐殺」なのである。中国の歴史教育なるものがいかに政治的で、その時々の権力者次第かという証左である。
この種の“愛国青年”は今や至るところで対日マスヒステリーを暴発させている。スポーツの国際大会では、遠征してきた日本選手に対して罵倒し、物を投げつけ、日本国歌にブーイングする等の異常な反日行動が日常風景になっている。今ではこれが中国人の対日感情の典型なのである。一般の日本人が、このような異様な反日中国人に“遭遇”したのは2000年代の半ばだが、その根は江沢民時代の日本悪魔化政策にあったのだ。
数年前、ウイグル人の“暴動”を鎮圧するために、武装して街をうろうろしていた気味の悪い漢人青年の集団のように、彼らはメンタリティ的には「遅れてきたナチ」そのものだ。今から十年後には、この「中華ナチズム世代」が社会の主要な地位を占めるのである。
戦前の日本に近づく中国の大衆ナショナリズム
問題は、江沢民が育てた反日ナショナリズムによって、今や共産党自身が自縄自縛に陥っていることだ。今では、「日本に対して弱腰だ」として、共産党が民衆から批判されるケースも目立ち始めた。党中央はこの「集団の空気」に容易に逆らえなくなっている。皮肉なことに、かつて共産党が民衆の間に炊きつけた憎日という怪物が当事者にもコントロール不能になり、その民心への迎合と妥協を余儀なくされる状況に陥っているのだ。しかも、党や軍の若手も憎日教育世代である。組織内からも突き上げを食らうのだ。
「共産党は大衆の意志など何とも思っていない。政権を守るためには大量虐殺も辞さない」という見方は古い。それは鄧小平までの話だ。実は、すでに天安門事件の頃から軍部には市民の虐殺に対する物凄い葛藤があった。現代では、容赦なくぶち殺せるのは異民族だけで、同じ漢族を大量虐殺することは、完全に政治的な自殺行為となる。今では、共産党の独裁的意志というより、「大衆」と、大衆が醸し出す「社会の空気」が、対外政策を決める重要なファクターになりつつあるのが、正確なところではないだろうか。

これはちょうど戦前の日本の雰囲気に似ており、極めて危険な兆候である。明治の寡頭政治の時代は、戦争のコントロールが比較的うまくいった。ところが、大衆右翼や農村出身者の多い陸軍が台頭すると、統帥権の独立という欠陥もあり、社会の空気とその後押しを受けた軍部が勝手な行動を始め、政府が事後に追認する形になっていく。ただ、その軍部は軍部で、下克上が蔓延し、将官クラスが青年将校から突き上げを食らっていた。東条英機も総理就任当初は天皇の意を汲んで、対米協調外交を始めた。ところが、東条の自宅には、一般市民からの非難や脅迫文が山のように舞い込んだ。今日、東条は“軍国主義者”とされるが、ではその東条を恫喝した市民はなんと呼べはよいのだろうか。
鄧小平の頃には、共産党指導部が自由に軍を動かせたし、負けてもその事実を大衆に隠せばすむ話だった。独裁政治だからこそ、政治的な利益を最大化する、又は不利益を最小化する合理的な判断が可能だった。ところが、組織の下から突き上げをくらい、大衆から批判されるようになると、その種の「空気」のほうに政治を合わせなければならない。外交でも戦争でも「弱腰」が許されなくなってくる。軍事行動も、それまでの計算されたものから暴走に近づいていくだろう。ましてや、次の習近平政権は保守反動勢力に担ぎ上げられ、習自身もかつての近衛文麿みたいな周囲に引きずられやすいタイプである。
今後、日本は、中国の政治家や軍部のほうが社会の「空気」という怪物に操られ、暴走する可能性を想定したほうがいいと思う。また、中国の政界にばかり顔を向けていないで、まったくの一般市民を対象にした対中世論工作も重要になってくる。日本の大衆文化はこの点で非常に大きな役割を果たしていると思う。これから中国が戦争に突っ走るか、内部闘争で分裂するか、未来は誰にも分からないが、激変を想定し備えておくことは決して無駄ではないと思う。
2012年09月18日「アゴラ」掲載




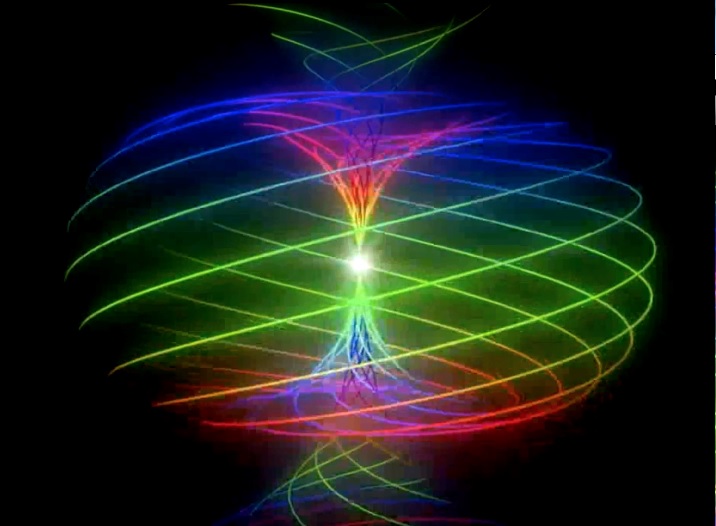




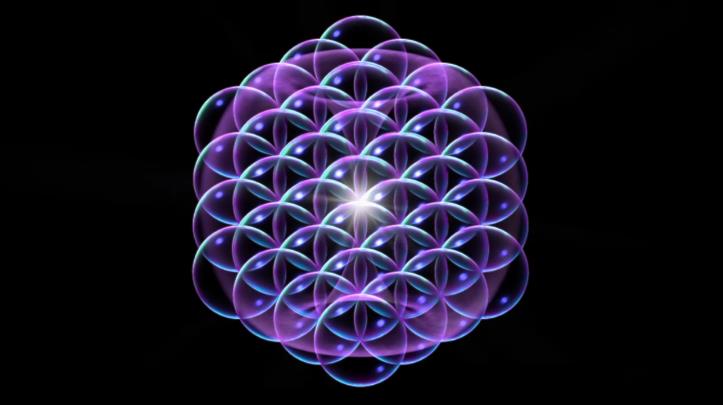


スポンサーリンク