さて、前回。日本は漢城の王宮に乗り込んで閔妃派を追放し、開化派官僚を集めて近代化のための改革断行内閣を組織した(甲午改革)。そして95年初頭、国王高宗に対して「朝鮮の独立宣言」と「国政改革十四か条の誓約」を公の場で行うことを強いた。同4月には清との戦争に決着がつき、朝鮮は公式にも清から独立した(下関条約)。
要するに、「さあ、独立しろ。そして今すぐ近代化しろ」というわけである。この凄まじいお節介の背景には、ロシアがひたひたと迫ってくることへの強い危機感があった。
ただし、日本の強要といっても、李朝内にもそれを望む勢力はあった。とりわけ、袁世凱の強権下で息を殺していた自主独立派にとって、これは再び手にしたチャンスだった。
ただ、一連の改革は、既得権益層に対して自己犠牲を強いるものだ。日本人の想像を超えていたのは、己の特権に対する朝鮮支配層の恐るべき執着と、あくまで宗主国を求める彼らの隷属メンタリティであった。
今回もイザベラ・バードの手を借りてみよう。
三国干渉と守旧派の巻き返し
イザベラ・バードの『朝鮮紀行』(講談社学術文庫)は当時の状況をこう記す。
官吏階級は改革で『搾取』や不正利得がもはやできなくなると見ており、ごまんといる役所の居候や取り巻きとともに、全員が私利私欲という最強の動機で結ばれ、改革には積極的にせよ消極的にせよ反対していた。(略)このように堕落しきった朝鮮の官僚制度の浄化に日本は着手したのであるが、これは困難きわまりなかった。(略)公正な官吏の規範は存在しない。日本が改革に着手したとき、朝鮮には階層が二つしかなかった。盗む側と盗まれる側である。『搾取』と着服は上層部から下級官吏にいたるまで全体を通じての習わしであり、どの職位も売買の対象となっていた(344ページ)
日本は朝鮮人を通して朝鮮の国政を改革することに対し徹頭徹尾誠実であり、じつに多くの改革が制定されたり検討されたりしていた。また一方では悪弊や悪習がすでに排除されていた。国王はその絶対的主権を奪われ、実質的には俸給をもらう法令の登録官となっていた(350ページ)
当時、朝鮮の近代化を確実に妨げていた原因の一つが、国王とその取り巻きによる公私混同であった。
日本は、国家を私物化していた閔妃派を追放した後、王室費を削減させ、年度ごとの予算を組ませた。また、「王室」と「国政」とを切り離して、後者をより近代的な執政体制に取って代えようとした。
だが、朝鮮の支配層からすれば、それは潤沢な私的資金と絶対的な権力を奪われるか又は極端に制限されるに等しい暴挙であった。
95年5月、日本は悪名高き「三国干渉」に屈してしまい、清から割譲した遼東半島の放棄を余儀なくされる。その際、朝鮮支配層の目には、単純に「やはり日本よりもロシアのほうが強者である」と映ったようだ。事実そうだった。
この時、彼らは二つのことを直感したらしい。
一つは「清に代わる次の宗主国はロシアである」ということ。
もう一つは「ロシアの力を借りれば特権を奪還できる可能性がある」ということ。
早速、ロシアと手を組んだ閔妃派を筆頭とする守旧派は、猛烈な巻き返しに出た。
これにより、6月には第二次金弘集“改革断行”内閣が崩壊し、8月に成立した第三次の同内閣では日本派が退けられ、実権は再び閔氏派のものとなった。
この程度で傀儡政権が倒れてしまうのだから、まったくたいした“帝国主義”である。
腐敗した政敵を「官職から遠ざける」だけに留めておいた日本流の「甘さ」が裏目に出たといえよう。朝鮮式のやり方では、クーデターの際は、家族もろとも政敵を連座制で皆殺しにしてしまう。だが、近代国家である日本には、たとえ相手が国民の生き血を啜ってきた魑魅魍魎だとしても、そんな戦国時代のような真似はできない。だから、容易に反撃を許してしまった。
三国干渉の屈辱感が覚めやらぬ日本国内は、己の特権的権力を取り戻すために急速にロシアへと傾斜していく朝鮮支配層を見て、さらに怒りと失望を覚えた。
「日清戦争」と「傀儡政権の樹立」の同時決行という賭けまでしたのに、結局、以前と同じように、閔氏派とその取り巻きが改革の前に立ちはだかっている。いったい、何のために朝鮮を独立させたのか。自分たちが血を流して清と戦争までしたのは、何だったのか。
一方、三国干渉は、後にとんでもない禍を引き起こす。もともと清が対日圧力として列強の力を頼ったことに拠るものだが、それはヤクザに借金するのと同じで、清はその「借り」を返すため、かえって得た以上のものを列強に分捕られる羽目になる。こうして、清と朝鮮の愚劣さから、ロシアは一挙に朝鮮進出を果たすが、それは次回に触れる。
閔妃暗殺事件
ここで日本は下手を打ってしまう。逆襲に対して、日本もまた逆襲に出てしまったのだ。
95年9月、井上公使に代わり三浦梧楼陸軍中将が公使として着任する。閔妃の排除という点で、三浦公使と大院君の利害が一致した。
10月、日本の歩兵大隊、数十名の日本人壮士、禹範善指揮の第二訓練隊(*日本派と見なされ廃止予定だった)がクーデターを決行する。彼らは王宮を占領し、閔妃を殺害した。
この場面をお雇い西洋人が目撃していたため、国際問題化を恐れた日本は、結果的に内政への関与を自粛してしまう。
この事件は、例によって韓国では「すべて日本のせい」とされている。とりわけ事件のイメージを形成するのに大きな役割を果たした『明成皇后』なるドラマだが、私は見ていないので何ともいえないが、伝え聞くところによると、日本人への憎悪を煽り植えつける演出だそうだ。仮に、日本のテレビ局で「朝鮮民族を醜く邪悪に描くドラマ」を放映すれば社会問題になるが、韓国では日本人への差別意識と敵視はむしろ共感される。
だが、果たして、本当に「日本人だけが悪い」のだろうか。これは絶対に釘を刺しておかねばならないが、この事件の責めは日韓双方が負うべきである。なぜなら、首謀者は間違いなく大院君だからだ。なにしろ、事件後に本人が自分だと布告しているのだ。
「王宮内に卑劣な輩がおり、人心が乱れている。ゆえに大院君が政権にもどって国政改革を行い、卑劣な輩を排除し、かつての法を復活させて国王の威信を守るものとする」
「予は国王を補佐するため、卑劣な輩を排除し、善を成し、国を救い、平和をもたらすため王宮に入った」(イザベラ・バード『朝鮮紀行』357ページ)
この二度の布告は大院君が自ら出したものだ。「日本が無理やり言わせた」とする見方は成り立たない(韓国の歴史家は「日本人が宮廷に大院君を強制連行した」などとも主張する)。なぜなら、この数ヶ月後にはロシアが李朝の支配者になり日本が排除されるが、大院君は訂正していない。仮に「不本意ながら閔妃暗殺の首謀者たることを日本によって強制された」のなら、彼は責任回避のために口を極めて日本を誹っていたはずだ。
実際には、大院君は自分が「卑劣な輩(閔妃)を排除した」ことを「誅殺」として正当化し、誇っていたのである。これは当時の閔妃観を知らないと理解できないことだ。支持者といえば利権にありついていた同派の役人だけで、大半の人々は「これほどまでに暮らしが貧しく、役人が横暴で、社会が悲惨なのは閔妃一派のせい」と呪っていた。だからこそ大院君は、元凶に天誅を下したのは私の功績だと、天下万民に堂々宣言したのである。
もっとも、彼には、自派の者をことごとく死刑・流刑にされた私怨も大きかったろうが。
よって、事件の首謀者は、三浦公使と大院君の両方である可能性が高い。また、クーデターは日韓混成団であり、しかも直接的な下手人は日本人とは限らないことにも触れておく必要がある。これまで韓国人は、己の非は一切黙殺し、すべての責任を日本人だけに押し付けてきたが、そのフェアネス・マインドの欠如は咎められるべきだ。
まさにこの時、ソウルにいたイザベラ・バードも、矛盾する内容を書き記している。
事件当時、王宮にいたアメリカ人教官とロシア人技術者の陳述を主に引用する形で、バードは暗殺の場面を記している。一般に流布され、また韓国人が信じて疑わない「明成皇后暗殺場面」のソースとなっているのが、以下のような彼らの“目撃談”である。
一、日本人の暗殺者数名が剣をふりかざして国王の住む建物の部屋に乱入し、王妃の居場所を教えろと、直接的に国王と皇太子を暴行して脅した。
二、皇太子は自分の母親が剣を持った日本人に追いかけられる場面を目撃した。
三、王妃をかばった宮内大臣は両手を切り落とされ、国王のもとで出血死した。
四、日本人は王妃を刺し殺した後、隣の松林に運び、灯油をかけて焼いた。
繰り返すが、これはバード自身の目撃談ではなく、主に西洋人の陳述からの引用である。さて、事件後、日本人は引き上げたが、朝鮮の訓練隊は居座り、王宮をそのまま支配下に置いた。彼らは傍若無人を極め、軍隊と国王の従者たちを指揮下に置いた。国王のそばには、父親の大院君が張り付いていた。バードはその時の国王の様子を記している。
その日は各国公使が国王に謁見した。国王はひどく動揺しており、ときとしてむせび泣いた。王妃は脱出したものと信じており、自分自身の身の安全をひどく案じていた。なにしろ国王は暗殺者の一団に囲まれており、その一団のなかでもいちばん非道な存在が自分の父親だったのである。(略)国王は訓練隊に代わって日本軍が王宮警備に就いてくれることを切望していた(358ページ)
ご覧のように、お雇い西洋人の陳述と、各国公使発と思われる情報とが、見事に食い違っている。各国公使の謁見した高宗は、なぜか朝鮮人兵をひどく恐れて、逆に日本兵による庇護を求めているのだ。とうてい、自身と息子が“日本人”によって暴行され、妃を殺された人物の言葉とは思えない。
だいたい、お雇い西洋人は、乱入した“日本人”が「王妃はどこかと叫んでいた」と言うが、それはいったい「何語」だったのか。
このように矛盾点があるが、しかし直接的な下手人が朝鮮人であり、目撃者の西洋人が日本人と朝鮮人の区別が付かなかったと仮定すると、妙に辻褄が合ってしまう。
下手人に関しては、日本人だけでなく、朝鮮人部隊を率いた禹範善も有力な容疑者である。彼らは閔妃によって粛清されようとしていたので、動機もあった。
禹範善はのちに日本に亡命するが、高宗自ら放ったという2名の刺客により暗殺される。なぜそこまでしたのか。国王一家が彼の犯行を目撃していたからという説もある。クーデターそれ自体は日本政府の黙認があったと思われるが、事件後の慌てようからすると、あくまで閔妃の政治的な排除が本来の意図だったようだ。殺害については三浦・大院君レベルの謀略か、当日の現場の暴走と推測するのが妥当だが、未だ曖昧な部分を残している。
決定打となった「まげ暴動」と日本の撤収
いずれにしても、閔妃亡き後、再び日本の影響下で開化派官僚を再結集し、第四次金弘集内閣が結成された。しかし、また短命に終わる。なぜなら、ある無神経な改革が物凄い反感を買ってしまったからだ。それこそが「断髪令」である。
クーデターが結果的に裏目に出たところへ、断髪令やその他の近代化改革への猛反発が、日本に追い討ちをかける格好になった。イザベラ・バードは次のように記す。
国全体が動揺し何件かの深刻な暴動が起きたのには原因がある。その原因はわたしたちにはばかばかしく思えようとも、(略)一八九五年一二月三〇日の勅令による『まげ』への攻撃である! これが全土を炎と燃えさせた!(459ページ)
しかし朝鮮人にとって『まげ』は朝鮮人たるしるしであり、大昔からの慣習であり(略)、社会的法的に成人であるあかしであり、(略)『まげ』のない朝鮮人はたとえ中年に達していようと、名もない青二才としてしか扱われない(460ページ)
わたしは男性の身だしなみに関するもので朝鮮人の『まげ』ほど重要な役割を演じたり、丁重に扱われたり、固執されたりするものをほかに知らない(462ページ)
バードいわく断髪令は「朝鮮人を日本人と同じような外見にさせて自国の慣習を身につけさせようとする日本の陰謀」とされ、反対する暴動は「日本人への敵意を公然とあらわしており、殺人にいたった場合が多い」。こうして「『まげ』ひとつで社会秩序はその根底から揺らぎだしたのである!」(465ページ)と、彼女は記録する。
翌96年1月から、こういった施策に反対する「初期義兵」と呼ばれるものが発生する。中心になったのは儒者たちだ。彼らにとって断髪令と洋服の奨励、学校教育制度の公布などは、自己の存在を丸ごと否定される等しかったようだ。
また、国内の権力闘争も関係していたと思われる。当時、地域ごとに儒教の書院があり、両班や儒者たち有力者の教育その他行事の拠点となっていた。復権した大院君は、かつて国家と農村の再建のために生産に寄与しない書院を削減した張本人である。対して、守旧派に支持を広げるため書院を復活させてきたのが閔妃一派だった。
このような背景を知ると、「国母を殺されたから朝鮮人民が決起した」という解説が政治的で表面的なものだと分かるし、第一、時期も三ヶ月ほどズレている。
また、今日の韓国人が好む「反日義兵」というより「排外反政府義兵」と称するほうが事実に近い。なぜなら、2月には親露派によるクーデターが成功して日本派が粛清されるが、義兵闘争自体はその年の10月まで継続されるからだ。
さて、この混乱に乗じたのが李完用ら親露派官僚だった。まずロシア公使館内に上陸したロシア兵が駐留する。未明、窓を閉めきった輿を使って、国王と皇太子を秘かに王宮から脱出させ、同公使館内へと拠点を移した。
こうしてロシアと謀った親露派は、国王の身柄を確保すると、断髪令撤回と逆賊斬首の勅令を出させた。「朕は慈悲深き者たらんと努力する。
しかしながら九四年七月と九五年十月の事件に関わる首謀者にはいかなる容赦も加えない」と勅書は言う。事件とは、清との開戦を機とした日本による傀儡政権樹立と、閔妃殺害に至ったクーデターのことを指している。つまり「日本派粛清宣言」である。
金弘集は虐殺され、さらし首にされた。その他、魚允中は殺害、金允植は流刑。残りは日本へと逃亡した。彼らはすべて朝鮮開国初期からの近代化の推進者だった。
かくして、「旧独立党派も穏健開化派も完全に壊滅させられ、日本が精力を傾け続けてきた朝鮮内政改革への流れが終焉するのである」(呉善花『韓国併合への道』)
結局、朝鮮支配層は、日本を追い出して、どこへ向かったのか? イザベラ・バードが96年9月の状況を次のように記している。
日本がその隆盛時に悪弊を改めるために行った試みは大部分が廃止された。国内は不穏で東学党にかわり『義兵』が出現した。地方長官職その他の職位を売買する有害きわまりない習慣は多少抑制されていたが、宮内大臣をはじめ王室の寵臣は破廉恥にもこの習慣を再開した。また国王自身、潤沢な王室費がありながら、公金を私的な目的に流用し、安全な住まいにおさまってしかも日本人その他の支配から自由になると、さまざまな面で王室の因習に引き返してしまった。王権を抑制する試みがあったにもかかわらず、国王の勅令が法であり国王の意思を絶対とする絶対君主制にもどってしまったのである。一方、日本は徐々に撤退し、また撤退を余儀なくされ、日本が朝鮮で失った影響力はことごとくロシアの手に渡った(471ページ)
かくして、革新的な近代化改革も潰え、李朝はまた元の木阿弥に戻ったのである。以前と異なるのは、宗主国が清からロシアへと入れ替わったことくらいだった。
度し難い自主独立精神の欠如が招いた結末
朝鮮がせっかく手にした第二のチャンスは以上のようにして潰えた。いったい何が悪かったのだろうか。なぜ失敗したのだろうか。
原因としては、今述べたように、日本自身の失策が挙げられる。しかし、より大きな理由と責任は韓国人自身に着せられるべきである。
はっきり言ってしまえば、朝鮮支配層には独立する気概も近代化する意志も欠けていたということだ。だから、日本のしたことは「ただのお節介」で終わってしまった。
そのことを明らかにしているのが、第三者のイザベラ・バードに他ならない。なぜ韓国の歴史家とその影響下にある日本の左派が、彼女の手による第一級の史料を黙殺しているのか、もうお分かりだろう。彼女が本当の歴史を記しているからだ。
日清戦争とその結果としての下関条約は、李朝にとって2世紀半に及んだ清の支配からの解放を意味した。韓国の“正しい歴史認識”とは違い、日本は独立を奪うどころか、逆に与えたのだった。そして日本は近代化へのレールを敷いた。その過程で日本が実際に奪ったものとは、国王側の腐敗した特権であり、時代遅れの慣習であった、というのが私の見方である。
それまでの既得権益者に多大な自己犠牲を強いるのが、近代国家の生みの苦しみである。ところが、朝鮮支配層の中で、そのような痛みを甘受してまで「今こそ近代的な独立国家へと生まれ変わろう」と決意したのは、少数派に過ぎなかった。大多数にとって己の特権の維持こそが最優先事項であり、仮に独立や近代化に興味があるとしても、あくまで特権が傷つかない範囲での話だった。だから彼らは、日本の改革に反旗を翻した。
仮にその理由が「日帝から国家の主権と独立を取り戻すため」なら、後世に名分も立っただろう。ところが、実際に彼らが取った行動とは「主権と独立は捨ててもいいから己の特権だけは取り返す」という、実に情けないものであった。そのために彼らは「ロシアの力をバックにしてクーデターを決行する」という、一番やってはいけないことをやってしまった。
詳細は次回に譲るが、以後、彼らはロシアに次々と国の権益を売り飛ばしていく。そして朝鮮は自らロシアの実質植民地へと転落していくのである。
主要参考資料
名越二荒之助編著『日韓共鳴二千年史』(明成社)/呉善花『韓国併合への道 完全版』(文春新書)/海野福寿『韓国併合』(岩波新書)/姜在彦『朝鮮近代史』(平凡社)/イザベラ・バード『朝鮮紀行』(講談社学術文庫)/『入門韓国の歴史 国定韓国中学校国史教科書』(明石書店)/『韓国の高校歴史教科書 高等学校国定国史』(明石書店)
2013年12月20日「アゴラ」掲載
(再掲時付記:この「次回」をずっと書かずに今に至るわけですが、要するに、いったん日本を排除して大韓帝国となった韓国は、実際には、国の権益を次々とロシアをはじめとする欧米列強に売り飛ばしていきます。鉱山とか、森林とか、漁業権など。しかも、その行為を、韓国の教科書は「外国に侵奪された」などと書く。ソウルに電車を敷いた例もあり、そのことを「自主的近代化」などと自賛し始めていますが、あれは外国企業に独占経営権を設定しているわけだから、まさに植民地経営を許しているのと同じことです。満鉄を、中国人は「自主的近代化」とは呼ばないでしょう。本当はこのあと、2、3の記事を書いて、日韓併合の成立をもって締めくくる予定だったのですが、当面後回しになりそうです。いずれにしても、歴史のアマチュアにすぎない私の記事を読んでくれた韓国人もたくさんいたようで、その点は感謝申し上げます。)







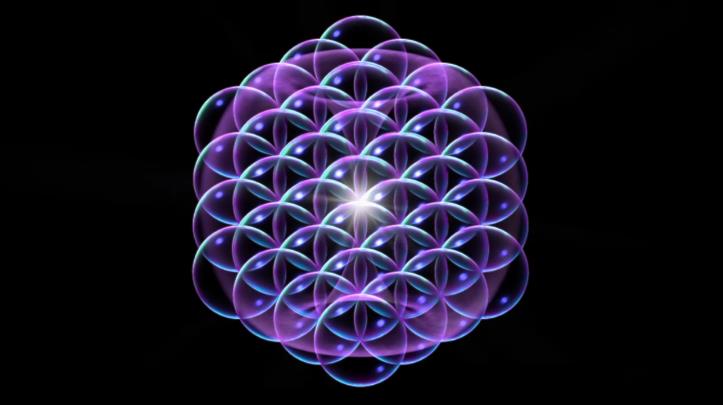




スポンサーリンク